メールをやり倒した「MailZine」から聞く
メールの可能性
ユナイテッドアローズが実践!「顧客との長期的な関係構築」のためのメールマーケ

株式会社ユナイテッドアローズ(以下、ユナイテッドアローズ)は、コンセプトの異なる19のストアブランドを全国に250店舗展開している。同社ではCRMへの取り組みとして、独自のポイントプログラム「UNITED ARROWS LTD. HOUSE CARD(以下、ハウスカード)」を展開している。
ユナイテッドアローズのCRM活用のビジョンは、「お客様に愛され続ける商売を実現するためにハウスカード会員様をより深く理解し最適な会員サービスを提供する」。その実現のため、会員様の購買履歴・顧客情報の分析、顧客を基点としたマーケティング活動、新規会員獲得に向けた活動を日々行っている。
そうしたビジョンのもと、デジタルコミュニケーションチームのリーダーである安藤彩子氏はメールマーケティングの目的を「ハウスカード会員様との長期的な関係構築のためのコミュニケーション」と説明し、メールをCRMの中のコミュニケーションツールの1つとして活用している。
具体的には、どういうコミュニケーションを取りたいのか、目的に沿って「誰に」「何を」を送るのかを整理、最適なセグメント・メッセージ・プラットフォームを選択し、以下のような分類でメール配信を行っている。
ハウスカード会員向け全配信メール
ストアブランド横断メール。普段利用していないストアブランドも知ってもらう目的で、年数回テーマを決めてそれに即したストアブランドのコンテンツを紹介。
ストアブランド全体配信メール
該当ストアブランドのメール受信希望会員に対し、ストアブランド担当者がブランドやアイテムへの想いを語り、ファン化を図るメール。
ストアブランドセグメントメール
普段の活用用途に応じて最適なコンテンツや商品を紹介する。購買履歴から需要をわけて配信など、個人の利用に即してパーソナライズする。
MAシナリオベースメール
お客様のアクションのタイミングに合わせてメールを配信。
メールは、分析のため極力HTML化。ソースが書けなくても簡単にHTMLメールがつくれるHTMLメール専用制作CMS「Lynx」を使い、各ストアブランド担当者が制作している。メール配信後は、デジタルコミュニケーションチームによる結果のフィードバックを実施している。
現在同社のメール開封率は25%以上、ブランドによっては30%を超える高い数値をキープしているが、安藤氏によると、これはメールの特性を生かしたメールマーケティングを実行した結果だと話す。
「私たちはメールを、Pull型・ブランディング・読み物という3つの特性を持ったコミュニケーションツールだと考えています。かつてメールはPush型のツールでしたが、強力なPushチャネルの登場により、今はお客様が自発的に情報を得るようなPull寄りのツールになっています。
そのため、他チャネルでのコミュニケーションへと切り替えるマーケターの方も多いと思いますが、こうした特性を理解して向き合えば、デザインの自由度が高くブランドの世界観を忠実に表現できる・文字数に制限がない・時間をかけてゆっくり味わっていただけるという他のチャネルにはない効果が得られると思っています」(安藤氏)
「『訪問回数』『前回訪問日』などフロー情報が重要」One to Oneメールマーケ最前線
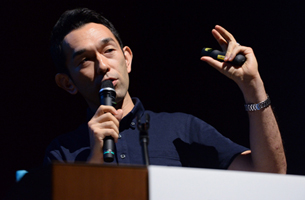
小中高大学生向けのオンライン学習サービス「スタディサプリ」。月額980円で、ユーザー一人ひとりに最適化した学習環境を提供することを強みに会員を伸ばし、42万人以上の会員を誇るサービスに成長している。
そんな「スタディサプリ」を運営しているリクルートマーケティングパートナーズでは、同社が蓄積してきた学習ビッグデータを活用したパーソナライズなメールマーケティングに数年前より取り組み、効果を上げている。
マーケティング基盤はもちろん高度な分析基盤を築き、そこから得られる詳細な分析結果を基に、ユーザーごとに適切なタイミングで自動的にメール配信する仕組みを整備している。
この仕組みを使い、同社では「会員獲得」に向けたメール施策を実行。たとえば、トライアル会員に登録したユーザーを有料会員化の比率を上げるためのメールアプローチとして、1週間のトライアル期間の間、「登録初日」「3日目」「トライアル最終日」と状況に応じて内容を変えたメールを配信するということを、配信システムで自動化して行っている。
ビッグデータエバンジェリストとして「スタディサプリ」のデータ活用を推進する萩原静厳氏は、「『氏名』『性別』などのストック情報でなく、『訪問回数』『前回訪問日』などフローな情報を取っていくことが重要。加えて、"行動ログ""コンテンツ情報"を付け、フロー情報をよりリッチにしていくことで、その人に付与できる情報量、文脈などが圧倒的に増え、非常にパーソナライズしやすくなるし、コミュニケーションがどんどん進化していく」と話す。
また、メールマーケティングの現状に対する自身の考えとして、萩原氏は次の6つの項目を挙げる。
- メールはよりフォーマルな手法になってきている
- 表現力(+情報量)はメールが一番強い
- デバイス横断で閲覧するチャネルはメールが一番
- 他チャネルとのゼロサムではない
- すべては目的と分析(結果)に依存する
- レコメンド等のコンテンツパーソナライズはメールが効く
「メールのコミュニケーション効果を最適化するには、メールの特性や利点を理解することが重要です。また、メアドというのは貴重な資産。当社では欠かせないものとして、今後もメールマーケティングに取り組んでいきます」(萩原氏)
凄腕ECマーケターたちが語る、メールマーケを向上させる4つのポイント

昔からコミュニケーションの主軸を担ってきたメールの価値は、アプリやLINEなど新たなデジタルチャネルが増えている中で変わりつつある。それを理解し、メールの特性を生かした施策を実行できれば、メールマーケティングの効果を高めることができるはず。
10年以上に渡りメールマーケティングを見てきたオイシックスドット大地CMT(チーフマーケティングテクノロジー)西井敏恭氏、ディノス・セシール CECO石川森生氏、2人のECマーケターがイベントで語ったメールマーケティングを成功させるポイントをダイジェストで紹介する。
1.やるべき施策が本当にできているのか
配信環境は劇的に変化したがメールマーケティングの施策自体に変わりはない。
「一番の変化は、メールを受け取るデバイスの中心がスマートフォンになっていること。PCで読まれる前提であった頃と、メールの作り方など大きく変わりました。ただ、タイトルが重要など、メールの効果を高める方法はあまり変わっていません。できること、やるべきことをまだやりきれていない企業が多いように思います。裏を返せばメールマーケティングの伸び代はまだまだ大きいと言えます」(西井氏)
2.ブランドへの入り口を伸ばす役割をメールが担う
メールは、他のチャネルと比べ載せられるコンテンツの質量に差がある。
「『サイトの延長線上』の感覚で、サイトで表現している内容をメールで展開することで、サイトに訪問する前にそこに何があるかわかる状態がつくれる。そういう意味ではブランドへの入り口を伸ばす意識で使えます。メールで知らせる内容は、サイトの中にあるもの以外ないので、メールとサイトの見た目は統一したほうが高い効果が得られると思います」(石川氏)
3.上手にHTMLを活用することでブランドの世界観を伝えるツールに
テキストとHTML、メールのクリエイティブはどう選択するべきか。
「商材によりけりですが、主要デバイスがPCからスマホになったことで、一覧性が担保しにくくなっている。"スマホファースト"で考えるとHTMLメールが有効なのでは。また、メールが自社ブランドを伝えるツールにもなると考えると、HTMLのほうがカスタマイズの自由度が高いと思います。特にウェルカムメール、注文完了メールは、ユーザーとの最初のコミュニケーションになるので、そこではHTMLメールを使ったほうが、効果が出ると考えています」(西井氏)
4.テクニック面を考える前にコンテンツを見直してみる
マーケターが見直すべきポイントは何か。
「結局のところ、メールマーケティングが成功するかどうかはコンテンツにかかってくると思います。テクニカルなことを色々やる前に、お客様に対して価値あるコンテンツをつくれているか、もう一度見直してみると良いと思います。担当者自身がお薦めできる商品・サービスだと思えるまでコンテンツやサービスを作り込めれば、自信をもって顧客へのオファーが出せるはずです」(石川氏)
CDPをフル活用してメール施策を最適化!リクルート×トレジャーデータ事例紹介

全国トップクラスの予備校講師が提供する授業動画を、パソコンやスマートフォン、タブレットでいつでも視聴できる学習支援サービス「スタディサプリ」。
月額980円という手頃な価格で、5教科18科目の学習を自分のペースで進められるサービスとしてユーザーを増やしており、現在は小・中学生向けカリキュラムや、社会人のための英語学習など、さまざまな学習プログラムを提供しています。
そんなスタディサプリを展開している株式会社リクルートマーケティングパートナーズが、ユーザーとのコミュニケーション手段として活用しているのがメールです。
スタディサプリの最大の特長は、一人ひとりの学ぶペースやニーズに合わせて学習環境の個別最適化を実現すること。
学習に要する時間や曜日、時間帯をどのようにしたらはかどるのか。復習重視か予習重視か。履修する単元をどのように組み合わせたら効果的なのか。
蓄積された学習データを基にプライベートDMPを構築して分析し、より良い学習の仕方をメールを使って提案しています。
現在SNSやコミュニケーションアプリなど、さまざまな手段がある中、同社がメールを選んだ理由は、大きく2つあります。
第一に、SNSのように「見に行く」のではなく、プッシュ型なので確実に情報を届けられること。第二に、個別最適化したきめ細かなコミュニケーションを、低コスト・低負荷で実現するには、メールが最適な手段だったためです。
そこでリクルートマーケティングパートナーズは、トレジャーデータのカスタマーデータプラットフォーム(CDP)と、チーターデジタルが提供するメール配信システム「MailPublisher」を連携。詳細な分析結果を基に、ユーザーに適切な時間帯にメールを自動送信する仕組みを整えました。
この仕組みにより、個々のユーザーに対し、メールを送る頻度や時間帯までも最適化することで、コミュニケーションの成果を向上し、ユーザーの学習効果最大化に大きく貢献しています。ユーザーの離反も抑えることができています。
メールを活用することで、本来のサービスの目的である「学ぶこと」の付加価値を上げ、それがユーザーのモチベーション向上につながっているのです。
※本事例の内容は全てインタビュー当時のものであり、現在と異なる場合があります。
【関連】
リクルートマーケティングパートナーズが使い倒すメール配信システムの特長とは
長年メールマーケに携わってきたコンサルタント達が明かす、
成果向上のためのノウハウ
PC向けのルールだけでは通用しない!スマホ時代の読まれるメールの条件とは?

メールを閲覧するデバイスは、PCだけでなく、タブレットやスマートフォン、フィーチャーフォンなど多様化しています。
中でも対策が急務なのが、スマートフォンへの対応です。
チーターデジタルの調査によると、メールマガジンを閲覧するデバイスとして「スマートフォン」を挙げる顧客が20代〜50代以上の全世代で増加しており、逆にPCを使う人は減少傾向にあります。
スマートフォンとPCのメール、一見すると違いがないようですが、実はスマートフォンへのメールを最適な形で届けるには、次の5つの課題があります。
1.会員種別ではスマートフォンユーザーが見分けられない
PCとフィーチャーフォンしかなかった時代には「PC会員」と「モバイル会員」は明確に分かれていました。
スマートフォンユーザーの場合、どちらのリストにも属することが可能なので、どちらの会員DBに属しているかによってスマートフォンユーザーを判別することができません。
2.メールアドレスではスマートフォンユーザーが見分けられない
従来は、会社アドレスやプロバイダーのアドレスやWebメールのアドレスの場合、Outlookなどのメールソフトを使ってデスクトップで閲覧していると見なすことができましたが、近年ではこれらのアドレスでもスマートフォンで見られていることが増えてきています。
3.見ているアプリがバラバラ
スマートフォンでメールを見る場合、ネイティブメールアプリかWebメール用のメールアプリか、またはブラウザを利用してWebメールを見るなど、利用するアプリがバラバラであり、アプリによって見え方が異なってくる場合があります。
4.見ている端末の仕様がバラバラ
同じスマートフォンでも、端末によってメールの表示方法が変わります。たとえばiPhoneとAndroidではHTMLメールの表示に違いがあり、メールが画面内におさまらず横スクロールが出るケースもあります。
5.いつもPC/スマートフォンで見ているとは限らない
同じメールでも、時間やシーンによって閲覧するデバイスを使い分けている人が多く、常にPCまたはスマートフォンでメールを閲覧しているわけではありません。
この課題を踏まえ、スマートフォンに最適なメールを作るには、どこまでスマートフォンに対応するべきかを決めることが第一歩となります。
ただ、どこまでの範囲に対応するべきか、そしてスマートフォンの表示に最適化したデザインとは何か、一から試行錯誤していては、ビジネススピードに対応できません。メールマーケティングの専門家の知見を借りるのも、的確な改善を素早く実行するための一手段です。
マーケティングの成果を上げるレポートの作り方

メールマーケティング施策は、実行して終わりではありません。どんなに高い成果を上げたとしても、その成果を客観的に分析できなければ持続的成長を実現できません。
高い成果を維持し続けるため、そして結果が思わしくなければより高い成果を得るために、レポートの作成は有効な取り組みです。
そんな重要なレポートですが、つい惰性で作成して終わってしまうケースも少なくありません。レポートの作り方を見直すだけで、より大きな成果が期待できるのです。
一般に、レポートを作成する前には、「指標(KPI/KGI)の設定」「比較する対象の設定」「レポートを配信する相手の特定」の3つを行う必要があります。そのうえで、レポートの目的と内容に応じ、作成するレポートの種類を考えなくてはなりません。
さて、レポートには、常に見ておくべき「基本レポート」と、スポットで見る「応用分析レポート」の2つがあります。
基本レポートとは、主に指標の推移を見たり、反応率が高いコンテンツやクリエイティブのナレッジを蓄積したりする目的のもので、具体的には「配信結果の推移レポート」や「クリエイティブ評価レポート」などが挙げられます。
一方、応用分析レポートとは、たとえばA/Bテストの結果を見たり、メール受信者の現状分析をしたりするような、配信結果を深掘するレポートです。具体的には、性年代別のクロス集計レポートや、メールアクティブ率の分析レポートなどがあります。購買や申込みなどメールの目的そのものとメール施策の相関を把握し、課題発見をするような内容も応用分析レポートの1つです。
レポートの目的と特性を踏まえ、適切に成果を評価しなければ、次の施策に活かせません。
たとえばメールの配信結果が必要なのにアクティブ率を分析したり、メールの効果を上げるために深掘した分析をしなければならない時にクリエイティブの評価をしたりしていては、思うような成果につながらないのです。加えて、どのような分析をするためにどんなデータが必要なのかを見きわめる必要もあります。
メールマーケティングの効果を上げるには、目的に沿ったレポートを制作し、正しく活用しなくてはなりません。「基本」と「応用」の違いを踏まえ、より効果を上げるレポート作成・運用を進めていきましょう。
【関連】
メールマーケ改善には、こうしたテクニックが大切ですが、配信システムにおける「ある3つの要件」に対する見解を深めることも非常に重要です。「その再確認すべき3つの要件とは?」
LINE・アプリ・メールの役割を理解し、成果を上げるには

かつて企業が顧客とコミュニケーションを取るには、メールの利用が一般的でした。今日ではメールだけでなく、LINEのようなコミュニケーションアプリや、自社が提供する独自アプリなど、さまざまな選択肢があります。
これらのチャネルを使い分けるには、まず顧客がそれぞれのチャネルに対してどのような印象を持っているのか、何のために利用しているかを理解しなければなりません。
チーターデジタルでは、コミュニケーションチャネルの利用実態を調査した「メール&クロスチャネルユーザー動向調査 2017年版」で、顧客がそれぞれのチャネルに対して抱いている印象や目的を明らかにしています。

LINE
若年層ユーザーが多く、メールやアプリで訴求できない層にリーチできるチャネルです。
またスタンプなどのサービスを通じ、企業や商品そのものに興味がない人に対しても接点を持てるという特徴があり、マーケティングフェーズでいう「顧客の獲得」に適しています。
反面、弱いつながりゆえか、今回のアンケートではLINEをきっかけに購買や申し込みアクションに繋がったユーザは少ない結果がでました。
アプリ
インストールするまでのハードルが高いというデメリットはあるものの、一度インストールすると強固なエンゲージメントを築けるという特長があります。
インセンティブ獲得などインストールする目的が明確なので、購買などの行動につながりやすく、既存顧客との関係の維持・強化に向いています。
メール
LINEとアプリの中間的な位置付けで、顧客獲得から育成・定着、離反防止と、あらゆる面を押さえることができるチャネルです。
企業と接点を持った動機も、「元々商品やサービスに興味があったから」という回答をした割合が、LINEとアプリのちょうど中間に位置し、マーケティングフェーズ全体においてバランス良い打ち手が可能です。
また配信できる情報量がほかの2つのチャネルより多く、コンテンツを通じて商品・サービスに興味を持ってもらったり、購買につながったりと、さまざまな効果が期待できます。
それぞれのチャネルのメリットを生かし、適切なコミュニケーションを行えば、効果は上がるはずです。そのためには、顧客の状況に即した全体的なコミュニケーション設計が成功のポイントです。
なお、生活者が各チャネルをどのように使っているかを調べた最新のレポートが準備できましたので、ぜひご覧ください。
「定期メルマガ開封してもらえない問題」への対処法

「メール会員のうち一定数の層はメールマガジンを送っても、開封もしてくれない」 「メール送信を許諾してくれない顧客も少なくない」
メールに取り組む以上、この課題には必ず直面する時が来ます。
一般的に、定期的なメールマガジンを開封する割合は全体の15%前後。マーケターは、メールを開封してもらうのは簡単なことではない、という基本認識を持つ必要があります。その上で大切なのは、お客様はどうしてメールを開封してくれないのかと想像してみることです。
メルマガ未開封者は大きく2つのタイプに分けられます。1つは、そもそもメールをまったく見ないタイプ。もう1つは、あまりメールマガジンは見ないけれど、関心があるトピックであれば、企業からのメールであっても閲覧するタイプです。
そもそもメールは閲覧しないタイプについては、メール以外のチャネルを活用したアプローチの検討が必要です。電話、DM、 SMS、LINEやアプリなど適切なチャネルをうまく選ぶのが望ましいでしょう。
他方で、興味のあるテーマのメールなら閲覧してくれるタイプについては、顧客理解を深めてニーズを的確に抽出することで、開封率やクリック率を高めることができます。
また、カスタマージャーニーを踏まえて、適切なタイミングでコミュニケーションができているかを確認することも重要でしょう。中でも定期メールマガジン以外のメール施策の立ち上げは有効な取り組みです。
ここでは、顧客満足度の向上を目的としてフォローメール施策を行った宿泊施設の事例を紹介します。この施設では、新着情報やクーポンを載せたメールマガジンを月2回配信していましたが、クーポン利用率やメール許諾率が低いのが悩みのタネでした。
そこで、コンサルタントの協力のもと、リピートのきっかけをつくるためにクーポン以外の訴求ポイントを洗い出すとともに、カスタマージャーニーを考え、どうすれば宿泊前後の満足度を高められるかを考えて施策を設計しました。
まず、クーポン以外の訴求ポイントとして、宿泊した回数に応じて割引率が増していく会員ランク施策や、記念日やライフイベントのタイミングでのお祝いメールを送り、割引・優待をオファーする施策を考案しました。
次に、ユーザのサービス利用導線を整理し、新たにメールを送るタイミングと内容を決めました。
具体的には、初回予約サンクスメールでは初回予約のお礼やホテルの紹介を行い、ホテルへの不安や疑問を減らし、宿泊前日メールでは、前日確認と施設案内などの詳細情報を送り、滞在中に快適に過ごしてもらうことを目指しました。
サンクスメールでは、宿泊の御礼と満足度アンケートを送り、フィードバックをもらいます。その上で、クーポン有効期限お知らせメールを送り、次回宿泊時に利用できるクーポンの有効期限を伝え、次回の旅における宿泊先の選択肢に加えてもらえるように工夫しました。
さらに、会員ランクアップが間近な顧客には、会員ランク変更メールを送り、あと1泊で会員ランクが変更され、次年度の割引率が変わることをお知らせしました。
一連の施策の結果、ホテル利用の満足度が向上し、会員制度も機能することで、顧客のリピート率がアップしました。
このように、定期メールマガジン以外のメール施策を行っていない場合、顧客のインサイトにもとづいて訴求ポイントを開発し、サービス動線に沿ったメール施策を考える取り組みは非常に有効です。
【関連】
メールマーケ改善には、こうしたテクニックが大切ですが、配信システムにおける「ある3つの要件」に対する見解を深めることも非常に重要です。「その再確認すべき3つの要件とは?」
「こんな時はこうする」
場数を踏んだ専門家が送る、特定課題への一問一答
Q. 効果を上げるためにHTMLメール化を考えたいのですが、システム仕様・予算などでまだ実現できません。
A.サマリー
- テキストメールとHTMLメール、個々のメリット・デメリットを把握した上で、両方活用していくのがいい
- HTML化の実現が難しくても、テキストメールをブラッシュアップすることで効果を上げた例も多くある
- テキストメールでは、「コンテンツ」と「レイアウト」がブラッシュアップの鍵
A.詳細
「テキストメールとHTMLメール、どちらが効果的か?」と聞かれた際には、「それぞれのメリット・デメリットを活かし、両方活用していくのが重要」とお伝えしています。
HTMLメールは画像を掲載したり文字色を変えたりすることができ、確かによりユーザーに視覚的に訴求するメールを作ることが可能です。一方で、メーラーにより表示崩れが起こりやすく、時として正しく伝わらないこともあるなど、リスクがない訳ではありません。
テキストメールは開封率が取れない、最後まで読まれにくいなどの懸念はありますが、特別なスキルを必要とせず、すぐに制作・配信できるメリットもあります。 目的・体制などに合わせてうまく使い分けているケースもあるので、媒体定義を行いながら原稿形式を決めていくことがよいかと思います。
テキストメールしか運用できないとしても、テキストメールをブラッシュアップすることで効果を上げたケースも多くあります。
テキストメールでは、「コンテンツ」と「レイアウト」がブラッシュアップの鍵となるので、「このメールで訴求したい内容は何か、掘り下げる」のと「ユーザー目線で読みやすいか見直す」の2点をまず行ってみてはいかがでしょうか。
【関連】
メールマーケ改善には、こうしたテクニックが大切ですが、配信システムにおける「ある3つの要件」に対する見解を深めることも非常に重要です。「その再確認すべき3つの要件とは?」
Q. 件名の文字数は全角30~40文字程度と聞いていますが、今もそれがいいのでしょうか。
A.サマリー
- 標準的な件名の文字数は「全角30~40文字が一般的」と以前は言われていたが、最近ではメールの受信環境により変わってきている
- ユーザーがメールを閲覧する環境は多様化しているため、ユーザーがどのような環境で閲覧しているかを把握することが重要
- 最近では「プリヘッダーテキスト」を工夫することで件名と同様、開封を誘導していく施策も出ている
A.詳細
多くのメールの中で興味を引き、内容を読ませるために重要な要素として、件名が挙げられます。確かにこれまで標準的な件名の文字数は「全角30~40文字が一般的」と言われることが多く、実際にお客様に対してもお伝えすることがありました。
ただ最近では、そのメールの受信環境などによって、最適な文字数が変わってきている傾向にあります。
例えばiPhoneのメールアプリを利用しているユーザーが多い場合、iPhoneのメールアプリではメール一覧画面に表示される件名は14~18文字程度です。となると、これまでの件名の半分くらいしか表示されていない、ということになります。
一方、Outlookなどのメールソフト、PCブラウザからのWebメール利用者が多いメールでは、件名の最後にインセンティブを掲載したところ、反応がよくなりインセンティブへの誘導も向上したケースもありました。
以前に比べ、ユーザーがメールを閲覧する環境は多様化しているため、「対象者はどのような閲覧環境にある傾向が強いか」を把握した上で、その閲覧環境にあった件名を設定していくのが望ましいと思います。
また最近では件名の他に、一覧画面上で件名の下に表示されるメッセージ本文の最初の文章「プリヘッダーテキスト」を工夫することで、メール内容に興味を持たせるようにすることも多くなっています。こちらも併せて検討してみてはいかがでしょうか。
【関連】
メールマーケ改善には、こうしたテクニックが大切ですが、配信システムにおける「ある3つの要件」に対する見解を深めることも非常に重要です。「その再確認すべき3つの要件とは?」
Q. メール施策の効果検証ってどうすればいいですか。気をつけるべきポイントはありますか。
A.サマリー
- ゴール(KGIやKPI)を明確にし、そこに至る各ステップの「どこで」「どの程度離脱」が起こっているか、を明確にするのが効果検証の重要な役割
- 「開封が低いから件名を見直す」は間違いではないが、選択肢の1つでしかない
- 大切なのは、どこで離脱が起きているかを捉え、「なぜユーザーは◯◯しないのか?」という仮説をつくり、検証結果を打ち手に活かし改善を継続すること
A.詳細
まずはメール施策のゴールを明確にすることが大切です。ユーザーにしてほしいことは、購入、資料請求、または特定ページへの遷移のうち、どれでしょうか。
設定したゴールに対し、「ゴールに至るステップのどこで、どんなユーザーが、どの程度離脱したか」を把握することが、効果検証の基本的な考え方です。その上で、「離脱が多い箇所」を課題と捉えるケースが一般的だといえます。
メール施策の効果検証においては、「配信」「配信成功」「開封(HTMLメールのみ)」「クリック」「コンバージョン」をマイルストーンとして、それぞれの間で離脱が起きていないか、順に見ていきます。
例えば、配信~配信成功間で離脱が多ければ、配信リストまたは配信システムを見直す必要がありますし、開封数に対するクリック数の割合が小さい場合は原稿見直しを検討していきます。
なお「開封が低い=件名がよくない」というのはやや結論を急ぎ過ぎで、他にも見直しを検討すべき要素があります。配信対象者へのメール許諾時のコミュニケーションが良くない場合や、許諾を取ってから初回配信までのタイミングが遅いために読み手のモチベーションが落ちている、といったことも考えられます。
また「コンバージョンが低い」という点のみに着目し、一生懸命メールを改善するのも、うまくいかないケースがあります。クリックが少ないのではなく、「クリックした後のコンバージョン率が低い」のであれば、メールでなく飛び先のページを見直すべきです。
大切なことは「コンバージョンに至るステップの、どこで離脱が起こるのか」をしっかり捉えたうえで「なぜユーザーは◯◯せず、離脱してしまうのか」という問いに対して仮説をつくり、打ち手を検討し、実施そして検証のプロセスを繰り返すことです。
【関連】
メールマーケ改善には、こうしたテクニックが大切ですが、配信システムにおける「ある3つの要件」に対する見解を深めることも非常に重要です。「その再確認すべき3つの要件とは?」
Q. お試しや初回購入後に本品購入やリピートに繋がらないユーザーが多く困っています。
A.サマリー
- 現状のコミュニケーションで「商品やサービスの特徴・魅力」は十分に伝わるのか、要検討。サイトや同梱資料のみでは、重要な要素が伝わっていない可能性も
- 「お試しや初回購入で留まってしまう要因」が分かると効果的な打ち手に繋がる
- ユーザーの利用実態を踏まえて、コミュニケーション内容・タイミングを調整することで施策の効果が高まる
A.詳細
ユーザーにとって、商品やサービスのお試し期間や初回購入後は「自分にとってこの商品・サービスが必要か」を見極めるタイミングです。
本品購入やリピートをしてもらうには、ユーザーに商品やサービスを正しく理解してもらうことが重要です。
■ケース:化粧品や健康食品
化粧品やサプリメントなどの美容系付加価値商材は、「製品理解」と「効果の実感」がその後の購入の決め手になります。「商品到着直前」~「商品到着◯日後」ごとに「製品を正しく理解し、効果を感じられやすい」フォローコミュニケーションを実施するのが有効です。
■ケース:月額制有料動画サービス
映画やドラマ、バラエティ番組などの月額制有料動画サービスを提供する企業の事例です。マーケティング担当者は、無料期間中の主な解約理由に「観る時間がない」という回答が多いことを発見しました。
このように解約の主な理由がわかった場合は、「短い時間で楽しめるコンテンツもあること」や「自宅で途中まで閲覧した動画の続きを、外出先でスマートフォンで見られること」を訴求することで、「短い時間でも楽しめるなら続けたい」というニーズがある顧客の継続可能性が高まります。
■まとめ
ウェブサイトや同梱資料には沢山の情報が掲載されていますが、ユーザーが目を通してくれるとは限りません。結果的に「こう使ってほしい」という企業側の想定と異なる形で利用され、「この商品・サービスは良くない」という判断をされることは少なくありません。
アンケートを活用しつつ、ユーザー目線に立って「誤解されやすいことはなにか」「なにが伝わるとユーザーはその商品をよりよく評価してくれるか」について仮説を立てましょう。その上で、プル型だけでなくプッシュ型チャネルも活用し、コミュニケーションをはかることが重要です。
Q. 資料請求数は増えたのですが、商談数や成約数が増えません。
A.サマリー
- 資料請求者向けの電話フォローは、リソース・コスト・繋がらないなどの観点から課題になることが多い
- フォローメールは「電話」というチャネルのデメリットのいくつかを解消し、資料の開封・閲覧・アクションを促進することができる
- 「メールの開封・クリック者から優先的に架電する」など、チャネルを組合せた効果向上の取組みもできる
A.詳細
資料請求者は最も分かりやすい見込客の1つです。あらゆる企業が資料請求後の未アクション者に向けて電話を中心としたフォローを実践しています。
しかし電話は一般的に受ける側の心理的負荷が高いため、「出てもらえない」「本音で話してもらえない」などのリスクも存在します。
また、電話番号の未取得・架電のリソース不足・コスト高などから、絶好のアプローチ機会を逸しているケースも少なくありません。
資料請求者の手元に資料が届いた際のステータスには以下のようなパターンがあるでしょう。
- 到着した資料を開封していない(未開封)
- 開封・閲覧したが、内容がよく分からず検討を止めた(閲覧中止)
- 開封・閲覧し興味を持ったが、次アクションに至らない(未アクション)
上記のような状況において、資料請求者向けフォローメールは有効な打ち手の1つです。ここでのメールの役割は以下のようなものです。
- 資料の発送や到着タイミングを知らせ、開封を促す
- 資料のどこに着目して欲しいかを伝え、改めて閲覧を促す
- 資料を閲覧し興味が高まった方へ向け、アクションを促す
またメールというチャネルの特性から以下のような点はメリットに挙げられます。
- 低コスト
- 心理的負荷の低さ
- 人的リソースに依存しないこと
- 開封有無や開封タイミングが分かること(HTMLメールのみ)
HTMLメールであれば、開封有無やタイミングを活かし「開封者のみへ優先架電」することや「電話に出ない顧客へ電話の主旨を伝え電話に出てもらいやすくする」など、チャネルを組合せて効率化や効果向上を図れます。
特に金融・保険商品などは商品自体が複雑なので、ちょっとしたフォローがあることで 「いったん、この会社に色々聞いてみよう」となるかもしれません。
「資料請求したことの再認識」「見て欲しいポイントの伝達」「アクション促進」などを目的としたフォローメールは、今回取り上げた課題に対する1つの打ち手だと言えます。
【関連】
メールマーケ改善には、こうしたテクニックが大切ですが、配信システムにおける「ある3つの要件」に対する見解を深めることも非常に重要です。「その再確認すべき3つの要件とは?」
Q. スマホ中心になった現在、携帯向けのHTMLメールは必要ないですか?
A.サマリー
- スマートフォンが大半だからといって、すべてのメールをPC向けHTMLメールにするのは難しい
- 画像の表示方式が2種類あり、端末によって方式が異なることにより、PC向けHTMLメールだと画像が表示できない端末がある
- OSや端末、アプリによって仕様や表示が異なるため、ユーザーの状況をしっかり把握することが、スマートフォン対応の第一歩
A.詳細
携帯向けのいわゆる「デコメ」と呼ばれるようなモバイルhtmlメール。現在の携帯利用では、フィーチャーフォンからスマートフォンに主流が変わりつつありますが、ではデコメのようなモバイルhtmlメールは、本当にもう必要ないのでしょうか。
答えは「NO」です。
確かにフィーチャーフォンより画面が大きいスマートフォンでは、PC向けHTMLメールを見る機会が増えてきました。
しかし、携帯会社が発行しているアドレス(docomo.ne.jpやezweb.ne.jpなど)に届いたメールをスマートフォンで見るとき、その端末によってはPC向けHTMLメールが表示できないケースがあるのです。
これには、HTMLメール内の画像をどうやって表示させるか、画像表示方式の違いが影響してきます。
PC向けHTMLメールでは、画像ファイルをWebサーバーにアップロードし、メールを開くたびにWebサーバーにアクセスして画像を読み込む「画像読み込み型」という方式が使われています。
一方、モバイルHTMLメールは画像ファイルをHTMLファイルと一緒に各ユーザーに配信する「画像添付型」方式のため、ユーザーは自身に届けられた画像ファイルを表示させます。
スマートフォンでも画像読み込み型を採用し、PCと同様にHTMLメールを表示できる端末も多くありますが、端末によっては「画像添付型」しか表示できないものもあり、その端末にPC向けHTMLメールを送ると、画像がまったく表示されないメールが出てしまう、というわけです。
これ以外にも「SMSで設定されている場合は表示が異なる」など、スマートフォンではOSや端末、アプリによって仕様や表示が異なってきます。
ユーザーの大半がスマートフォンだからといって、アドレスも確認せず無理やりPC向けHTMLメールのみに一本化しようとしても、届かない恐れもあるので、まずはリストやユーザー状況をしっかり把握することが、スマートフォン対応の第一歩です。
※「デコメール」「デコメ」は株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモの登録商標または商標です。
【関連】
メールマーケ改善には、こうしたテクニックが大切ですが、配信システムにおける「ある3つの要件」に対する見解を深めることも非常に重要です。「その再確認すべき3つの要件とは?」






