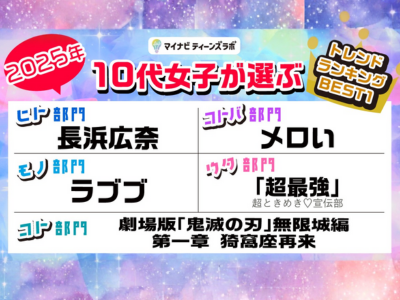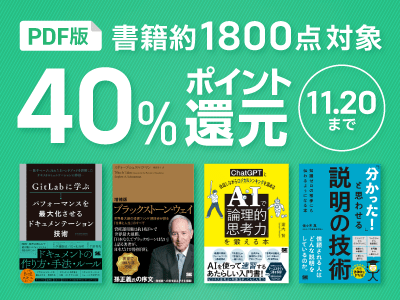スポーツビジネスは縮小するが、スポーツは揺らがない
それはスポーツの外から始まるだろう。現在進行中の「世界同時不況」問題の進展である。これまで4年ごとにスポンサーシップもTV放送権も、「3割、4割、あたりまえ」として値上がりを続けてきた。最大のスポンサーが、米国のTV局であることはよく知られている。が、そんなことが永久に続くはずがない。「どこで止まるのか?」は10年ほど前から議論されていたが、そんな心配を余所に値上がりは永久運動のように続いてきた。
だが、ここにきて、スポーツ界や広告界といった、特定の領域での話に留まらない「全体不況」の姿が見え始めた。サブプライムはその前兆だろう。BRIC’sもそろそろ怪しいし、奇跡的な成長ともてはやされたアイルランドも危うい。そこにきて、南オセチアとグルジア問題で、冷戦再びか?という事態が起きている。
70年代以降のスポーツの巨大化は、背景に「消費」の世界的な膨張があった。その膨張が止まりつつある。日本はある意味でその先取りをしている。可処分所得は伸びず、消費は冷える。一部の贅沢を支えてきた、「金融」産業は、所詮「ギャンブル」であることが露見した。カジノ資本主義は終焉しようとしている。
 結論は悲観なものにならざるを得ない。4年後なら、きっとさらに悲惨なことになっているだろう。このコラムのテーマは経済ではなく、スポーツであることを忘れているわけではない。斯様な悲観的シナリオの中で、スポーツがどうなるのかを予想しよう。
結論は悲観なものにならざるを得ない。4年後なら、きっとさらに悲惨なことになっているだろう。このコラムのテーマは経済ではなく、スポーツであることを忘れているわけではない。斯様な悲観的シナリオの中で、スポーツがどうなるのかを予想しよう。
第一に、五輪を頂点としたスポーツビジネスは、市場規模の縮小を余儀なくされるだろう。…で、それが何か問題でも?そうだ。一部のTV局と広告代理店がつらいだけの話ではないか。それでスポーツが揺らぐわけではない。
むしろ、足元を見つめ直すいい機会ではないか。あえて、「奇禍」とすべくスポーツ関係者は備えるべきである。そして、以上の悲観的なシナリオの中で、スポーツは一般の人たちの心を元気にさせる本来の役割が、余計明らかになるはずなのだ。4年後のロンドン大会を通じて、人々を元気つける本来の役割が。