「やらされる」感覚がポイント。今だからこそ受け入れられたBeReal
MarkeZine編集部(以下、MZ):お二人の対談前編では、よいユーザー体験とそれを実現するためのユーザー理解について話をうかがいました。その内容を踏まえ、最近目にして「これはいいな」と思った体験設計をしているサービスや事例はありますか?
伊藤:私が感銘を受けたサービスは、「BeReal」です。よく「盛れないSNS」と表現され、ライブ感や親しい友人とのコミュニティ内で自己表現を楽しめる点が特徴だと説明されることが多いのですが、私はそれだけではないと思います。
従来のSNSがユーザーの能動的な投稿によって成り立っていたのに対し、BeRealは「やらされる」という受動的なSNSを確立した点が画期的だと感じました。通知が来たら、別にやらなくてもいいはずなのに、つい投稿してしまう。その背後には、情報過多で選択に疲弊している現代人の心理があるのではないでしょうか。すなわち、指示されたことをやりたい欲求ですね。

伊藤:この心理を活用すると、たとえば「ランチガチャ」のようなサービスが生まれる可能性もあると思います。私自身非常に欲しいなと思っているサービスでもあるのですが、オフィスで今日のランチをどうするかと毎日悩む代わりに、ガチャの結果で店が決まる。それはある意味、「選択の自由を放棄することで、楽しさを得ている」ともいえるのではないでしょうか。ダーツやくじで旅行先を自分以外に決めてもらうことも同様です。人々は今、情報の収集・選択・判断を少し「サボりたい」と感じているのかもしれません。
通常、強制されると人間は抵抗するものです。おそらく10年前だったら、このようなサービスは受け入れられなかったでしょうね。
「風が吹けば桶屋が儲かる」?藤井氏が考える、理想の体験設計
MZ:なるほど。藤井さんはいかがですか?
藤井:私は、2025年1月にニューヨークで導入された「渋滞税」が興味深い事例だと思います。これは、特定の時間帯に車が多すぎるという課題解消のため、通行料のような税金を課すものです。
これにより、車の通行量が減少したのは当然ですが、結果として街の犯罪率が低下したのです。実は、渋滞税の導入によって自転車の利用が大幅に増加し、裏道にも人通りが増え、犯罪が減ったわけですね。
また、自転車は気軽に止まれるため、裏道にある小売店に立ち寄る人が増えたことで街全体も活性化したそうです。さらに、自転車移動の習慣が付いたことで運動量が増加し、街の人々が健康的になるという副次効果もありました。

藤井:まるで「風が吹けば桶屋が儲かる」のような話ですが、このような意図しない良い波及効果まで生める体験設計ができるようになりたいと強く感じた事例です。もちろん、設計者は当初からすべてを狙っていたわけではないでしょう。おそらく目の前の渋滞という課題を解決するため、短期的なトラブルシューティングとして導入されたのではないかと思います。しかし、結果としてこれほど多くの好影響をもたらしたことに感銘を受けました。
課題をすべて書き出し、要因や発生源を突き止め、それらがすべて一つの施策で解決できるグランドデザインを描くことができれば、それは理想の体験設計ですね。































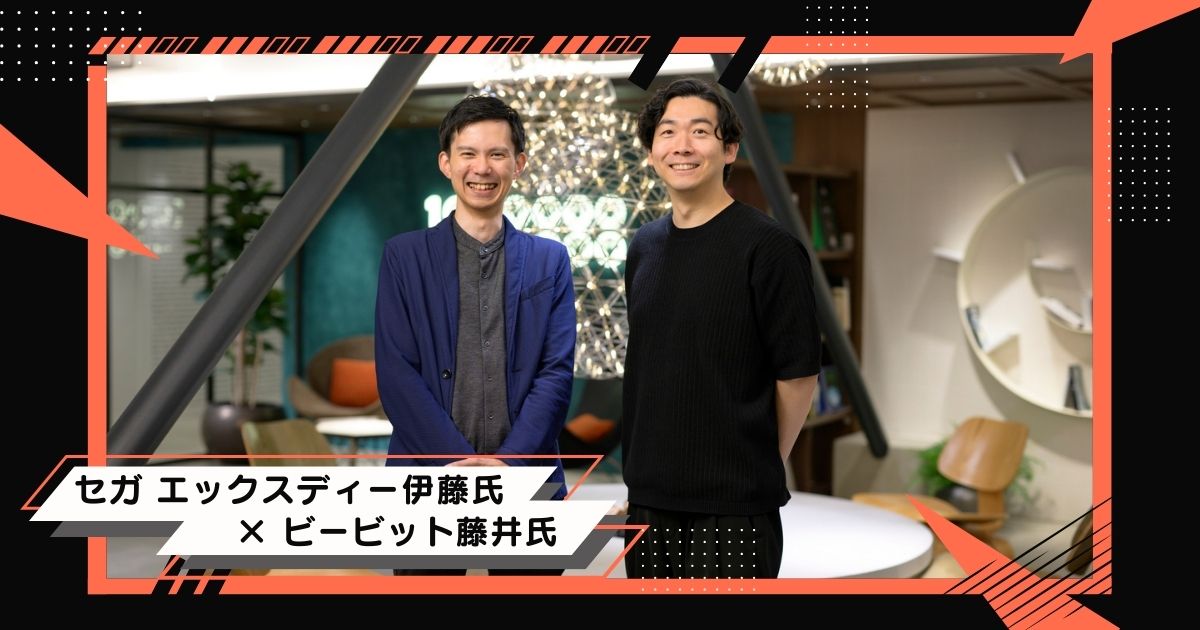
.jpg)
