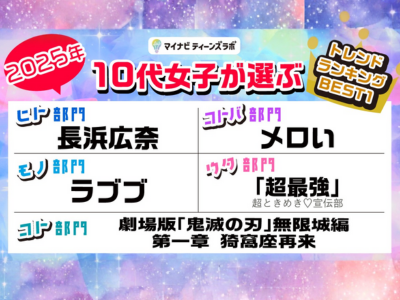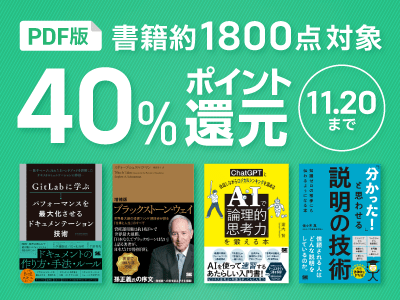目の前の問題は「おもちゃ」と考えて楽しむ

―― 忍耐力はどうやって育まれたのでしょうか。生まれついての気質ですか。
気質かどうかはわかりませんが、確実性のないものの中に自分を置いても、耐えられる感覚はあると思います。
問題というのはある種「トイ(おもちゃ)」と一緒だと思っていまして、小さい問題が積み重なれば大きな問題になりますし、それを解決する楽しみや遊び心もあります。問題解決とはそういうものではないのかなと考えているんです。
―― 問題をおもちゃにたとえるのは、リンダさんらしいですね。講演の中で、新しいことを創造するときは経験していないことの積み重ねなので苛立ちがあるとおっしゃっていましたが、ご自身はその苛立ちをどう解消させているのでしょうか。
まずは「時間軸」の考え方を変えているというのがあります。問題を解決するにあたって、たとえば3ヵ月・6ヵ月・12ヵ月のスパンで見ていくと、その時々にどういうリアクションを取らなければいけないのかが見え、考え方も変わっていくと思います。そうしてイライラを解決しています。
もう一つよくするのが読書です。とある中国の思想家の本で、文化というものと、そこからつながってくる問題や課題について語っているものがあるのですが、そこで色々な問題を解決してきた経緯を見ていくと、自分の問題など大したものではないと思えます(笑)。比較し違う見方をすることで、自分の視野を広げられる点で、読書はとても有効な手段だと思います。
違う見方をもつという点でいうと、日本文化は素晴らしいと思います。肌感ですが若い方と年配の方とのつながりが他の国に比べてあるではないでしょうか。そこから色々な知識の継承ができると思います。若い人たちが自分たちだけの世界に閉じてしまうことで、問題に対してイライラすることってよくあると思うのですが、それも減る。
私は若い方々との接点が多いのですが、もっと年配の方々とも関わりを深めていき、色々な見識を学び広げていきたいと思っています。
みんな一緒じゃつまらない

――確かに違う価値観に触れることは大切なことですね。
そうですね。たとえば、すべての本が男性だけで書かれればつまらないものになってしまうと思うのですが、それがコードであっても男性だけで作られていてはつまらない。同じように、若い方だけでコードや本を作っていると、それもつまらない世界になってしまうと思うんです。
色々なところで、ダイバーシティ、いわゆる多様性が必要になってきていると思っていて、それは年齢はもちろん性別、性格もですよね。これからの時代、より女性がテクノロジーの世界で活躍する時代になってくると思うのですが、それでも常に多様性を保っておかないとつまらない世界になってしまうでしょう。
教育も同じだと思います。私のもとには若い方だけでなく、もう一度勉強したい、スキルをつける機会がほしいと言ってくる年配の方もいます。そうした方々が学ぶ機会を、決して損失してはいけないと思っていますし、社会で支援していかなければいけない。年齢を重ねてから、「自分はテクノロジーやコンピュータが使えないから社会に貢献できない」ということになりますと、社会にとっても非常に大きなロスになりますよね。