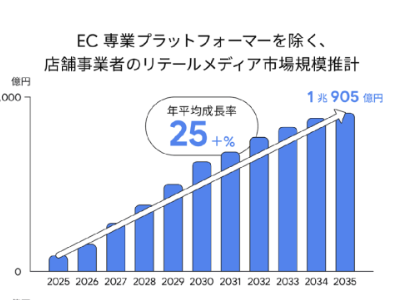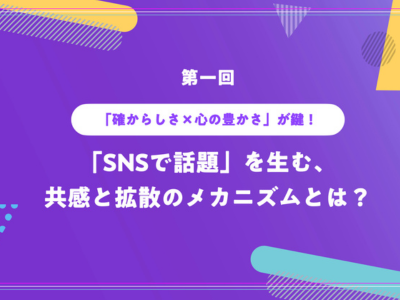CX時代に求められる“体験的価値”
良いモノを作っただけでは売れない時代になった。
消費者はこれまで、製品そのものから得られる「物質的価値」、キャンペーンや割引などによる「金銭的価値」の2つに誘因されモノを購入していたが、現在はそれだけでは購入されない。
この背景にあるのは、スマートフォンが引き金となった情報の氾濫。これにより、コンテンツの希少性が低下し、コンテンツの価値を見直す必要が出てきたとき、3つ目の体験的価値が重視されるようになった。
MarkeZine Day 2019 Autumnのセッション「匿名顧客の『見える化』から生まれる1to1施策とは」では、ギブリーの執行役員である大熊氏が、CX時代に求められるマーケティングとそれを実現するポイントについて解説した。

大熊氏は、体験的価値を「商品やサービスを通じて得られる体験から生まれる価値」と定義する。そして体験的価値は、次の5つに大別されるという。
1.感覚的体験価値
五感を通じて得られる体験的価値
2.想像的体験価値
商品やサービスのコンセプトや企業ブランドにより、消費者の知的好奇心や探求心が刺激され生まれる体験的価値
3.準拠集団や文化との関連づけ
集団に対する帰属意識に関連し、生み出される体験的価値
4.情緒的体験価値
ていねいな接客や気配りなどで消費者の感情に働きかけて生まれる体験的価値
5.ライフスタイル的体験価値
日々のライフスタイルに変化を起こすことで生まれる体験的価値
1to1マーケティングは大前提、その理由は?
体験的価値が重視されるようになった具体例として、大熊氏は飲食店の評価に関するデータを示した。「料理以外に『また行きたい』と思う理由」を聞いてみたところ、実に81.3%もの人が「スタッフの対応が良いこと」を挙げたそうだ。
「料金(コストパフォーマンス)」を挙げた人は57.7%にとどまっていることから、いかに体験的価値が求められているのかがわかるだろう。
「製品の機能など定量的価値だけではなく、ユーザーの心理をしっかり動かせるかどうかが大事。体験的価値を感じてもらうことができれば、エンゲージメントが生まれ、好きになる、ファンになるといったサイクルが生まれていきます」(大熊氏)
では、デジタルでこれを実現するために、マーケターは何をするべきなのだろうか。
大熊氏は、「大前提となるのは1to1マーケティング」と強調。その理由について「過剰にあるコンテンツをあなた向けのコンテンツとして提案することにより、希少性を作り出すことができるから」と説明した。
これを行うには、デジタル上にいる匿名の顧客一人ひとりと向き合い、コミュニケーションを図ることが必要だ。ギブリーでは「Conversation Tech」という部門を新設し、会話を科学するという考えのもと、体験価値を生むための1to1マーケティング支援に注力している。
デジタルでもリアルと同じように“ヒアリング”を
Conversation Techとは、デジタルを介したコミュニケーション履歴に基づく会話データを活用し、顧客一人ひとりに対して適切な情報やより良い体験価値を提案するための技術。つまり、デジタルでもリアルと同じように“ヒアリング”を行うことを可能にするものだ。
ここでのポイントは、ユーザーに情報を探させるのではなく、企業側から提案すること。そのためには、自社の顧客を深く知る、顧客を提案で導くという2ステップを踏むことになる。
自社の顧客を深く知るとは、ユーザー(サイト訪問者)は何に興味があるのか、なぜ興味があるのかなどを知ることだ。何に興味があるかは、Google Analyticsなどのマーケティングツールで得ることができるだろう。
一方、「なぜ」の部分を知るにはヒアリングが必要となり、ここでチャットボットが登場する。企業側から話しかけ会話を促すことで、ユーザーの状況を知り、なぜ興味があるのかをリサーチすることが可能になる。
こうして行動データと会話データから情報を収集しユーザーの温度感を把握した上で、ヒアリングおよびコンテンツの提案をし、企業側から顧客を導いていくのだ。
このようなステップを踏んでいない例として大熊氏は、サイト訪問者全員に対しキャンペーンを打ってしまうケースを挙げた。キャンペーンを使わずとも購入してくれる顧客にまでキャンペーンを提案してしまっていることもあれば、押し売りと思われることもある。
チャットボットは“会話データ収集ツール”である
ここまででわかる通り、チャットボットをFAQのツールとして使うのはもったいない。多くの企業がFAQで活用しているが、大熊氏は「見方を変えると、チャットボットはユーザーの背景を理解するための『会話データ収集ツール』として使うことができる」という。

その活用例の一つとして、大熊氏は“実名顧客の曖昧化の解決策”を紹介した。
名前とメールアドレスを入力すると、無料でサービスや製品を体験できるといった中間コンバージョン型のマーケティングはよく見られる。だが、メールを送信できるようになるだけで、それ以上の顧客データおよびニーズは何も得られず、困っている企業も多いのではないだろうか。
実際に、施策が行き詰まったり、費用対効果で悩んでいるといった声をよく聞くと大熊氏。その背景には「実名顧客の曖昧化」や「ユーザーの多様化」「チャネルの複雑化」といった要因があると大熊氏は分析する。
では、ここでチャットボットを投入するどうなるだろうか。会話データがプラスされることにより、ユーザーの背景・状況・ステータスを知ることができ、顧客へのコンテンツ提案が実現する。
ギブリーが開発・提供する顧客を知るためのチャットボット「SYNALIO(シナリオ)」は、すべてのサイト訪問者の行動に合わせて最適な会話を展開するため、データドリブンな1to1クロージングが可能だ。ユーザーの体験的価値が向上するのは言うまでもない。
このような効果が期待できることから、ローンチから1年半ですでに400社以上の導入実績があると大熊氏は胸を張る。
茨城ロボッツは情報提供型のボットでエンゲージメント向上
たとえば、男子プロバスケットボールチームの茨城ロボッツは、Webサイト上にチームキャラクターを利用したボットを作成。このボットからユーザーが情報を聞き出す形にし、情報量の多いサイトを最大限活用してもらえるように試みた。

すると、サイトの直帰率は14%以上改善。1セッションあたりのPVも1P以上増加し、ポップアップのCTRは平均10%以上の大幅改善に成功した。ファンの心理を捉え、キャラクターを前面に押し出し、よりコンテンツを見たくなる仕組みを作ったことで、サイト内におけるユーザーの体験的価値が向上したいい例だ。
また、クラウド会計ソフトを展開するfreeeも「SYNALIO」を導入している。freeeでは、自分に最適なプランはどれかという問い合わせが多かったこと、営業でも同じ質問を度々受けていたことを踏まえ、質問に答えるだけで自分に最適なサービスプランがわかる「会計freeeプラン診断」のボットをWebサイトに設置。
その結果、課金するユーザーの割合が増え、上位プランを選択するユーザーの割合も大きく増加したという。ボットの内容次第では、意思決定を促すこともできるということだ。

ソサエティ5.0時代にマーケターが意識すべきこと
先に出てきた5つの体験的価値のうち、Conversation Techで引き上げられるのは「情緒的体験価値」と「ライフスタイル的体験価値」だ。
繰り返しになるが、情緒的体験価値はていねいな接客や気配りなどで消費者の感情に働きかけて生まれる体験的価値、ライフスタイル的体験価値は日々のライフスタイルに変化を起こすことで生まれる体験的価値のことをいう。
このような体験価値に働きかける考え方は、AI駆動型の社会とされる“ソサエティ5.0”に出てくる。

仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する新たな未来社会“ソサエティ5.0”は、そう遠い将来のものではない。大熊氏によると、普及しつつあるスマートスピーカーはソサエティ5.0時代の製品だという。
渋谷でおいしい居酒屋を探すとき、これまでは「渋谷」「おいしい」「居酒屋」などのワードを検索し、表示された情報から、ユーザーが行きたいお店を選ぶという流れだった。
しかしスマートスピーカーを使用すると、ユーザーの問いに対しAIが一つの提案を行い、ユーザーはYes/Noを決めるだけ、といった手順に変化するのだ。「生活者の情報の受け取り方が大きく変わろうとしている」と大熊氏はいい、次のようにアドバイスをした。
「ソサエティ5.0に向かうにあたり、顧客に提案をできる情報伝達の仕組みを構築できるか。これは、マーケティング担当者がこれから考えるべきポイントになっていきます」(大熊氏)
体験価値時代のマーケティングで求められているのは、ユーザーの背景の理解だ。「そのためにチャットボットは有用である」と大熊氏は強調し、スピーチを終えた。