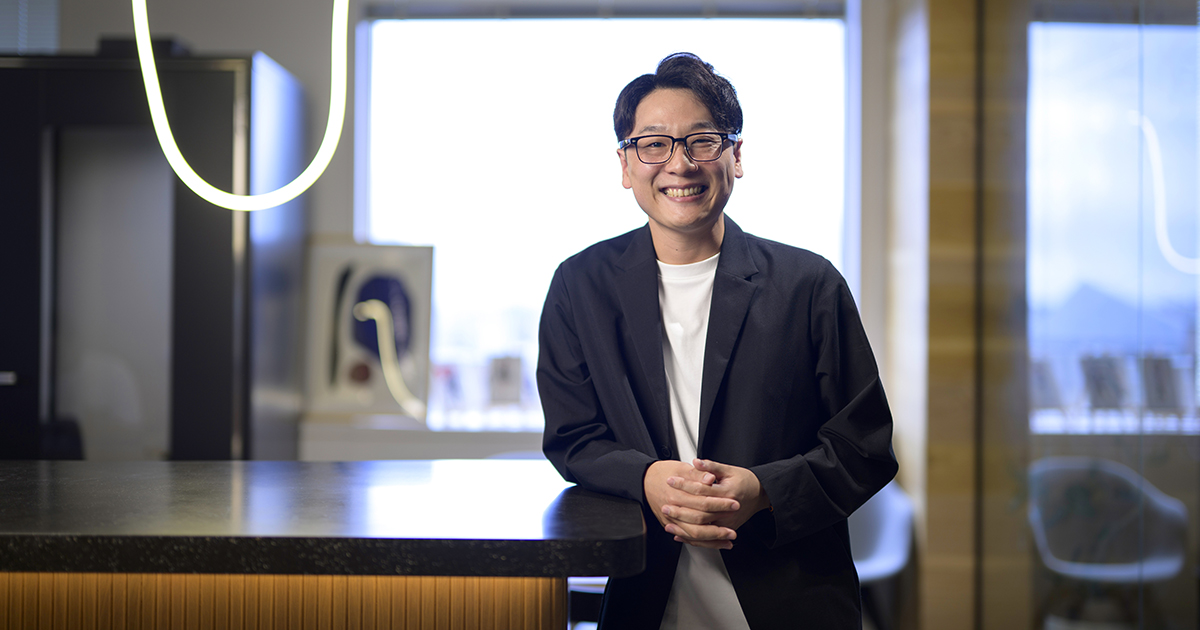「提案が通らない」本当の理由とは?
──富家さんはこれまで、大企業とスタートアップの両方でBtoBマーケティングに携わり、現在は様々な企業の支援もされています。そうした中で、「せっかく考えた提案が通らない」「上司や他部門にうまく伝わらない」といった経験はありましたか?
富家:はい、もう本当に何度も経験しましたね。むしろ提案がそのまま通ったことのほうが少ないくらいです。
私がBtoBマーケに関わるようになったのは、コニカミノルタジャパンに在籍していた9年ほど前からです。事業マーケの立ち上げや拡大に携わった後、責任者として全社マーケの立ち上げを経験しました。自分の提案がうまく伝わらなかった時、かつては「自分の説明が足りないんだ」「もっとロジカルに説明しなければ」と考え、準備に多くの時間をかけたこともありました。正直な話、うまくいかないときにはオフィスを飛び出して、新橋の赤提灯で「マーケティングの勉強をしてから反論してほしいよ」なんて愚痴をこぼしたこともあります(笑)。
そうした失敗を重ねてきて、今考えているのは、提案が通らない理由は個人のスキルや熱量にあるのではなく、組織内の意思決定や合意形成の構造にあるということです。

大手通販会社のマーケティング、広告代理店にてマーケティングコンサルタントを経験。その後、コニカミノルタジャパンにて、営業改革プロジェクト×マーケティング組織立ち上げを推進。マーケティング企画部 部長として、事業部・全社マーケティング組織の責任者を務めた。2023年秋よりEVeMに参画。実践者のひとりとして、マーケティングに「マネジメントの力」を掛け合わせた成果創出に挑戦している。著書に最高の打ち手が見つかるマーケティングの実践ガイド(翔泳社)
──どういうことでしょうか。
富家:提案が通らない多くのケースで起きているのは、相手とのコミュニケーションのズレです。提案を通すには、社長や上司、他部門など、異なる視点を持つ人と合意形成をしなければいけませんよね。ところが、共通言語が欠如していたり、前提のすり合わせがなかったりすると、マーケターがやろうとしている施策の目的や根拠が相手に理解してもらえず、逆に相手が抱いている疑問や違和感に対しても明確に応えられなくなります。
すると議論は平行線となり、最終的な意思決定は、役職や部門の力関係で決着がついてしまうのです。マーケと営業の「分断」や「対立」といった話もよく聞きますが、実際には対立すら起きていない「静かな分断」のほうが多いのではないでしょうか。つまりお互い何も言わず、それぞれのKPIをただ追い続けてしまう状態です。
この状況に直面し、マーケターの方々が自信をなくしたり、「今の会社は自分に合わない」と判断して離れてしまうのは、とてももったいないと思います。そうした思いがあり、合意形成を円滑にするためのフレームワークとして、「8つの視点」と「CABフレーム」を考えました。
AIが台頭する今、最大のボトルネックは合意形成
──コミュニケーションがズレていると、どんな困りごとが起きてしまうのでしょうか?
富家:ある施策に関して「やる・やらない」の二元論に陥るケースをよく見ます。
たとえば「展示会をやろう」という提案に対し、過去の出展結果を見て「リードは取れても、受注につながらなかったから出展する意味がない」と即断されてしまいます。本来的には、施策の良し悪しを即断する前に、成果を上げるために何が改善できるかを検討すべきですよね。
そうならないのは、そもそも何を理想とするかがステークホルダーの間で合意できていないからです。展示会で言えば、「展示会でどんな成果を得たいのか」「お客様にとって価値のあるブース体験はなにか」「そのための理想的な応対はなにか」これらを言語化した上で、それができたのか、どこに課題があるのかを議論しなければなりません。これらの理想状態が言語化もされず合意もできていないと、やるかやらないかの判断材料が数字的な結果しかなくなってしまいます。
──これは展示会に限らず、様々な施策に言えることですね。
富家:はい。マーケティング活動において、合意形成は今、最大のボトルネックになっています。AIによって、情報収集や施策の実行、レビューの仕方は大きく効率化されました。その一方で、合意形成も含む人と人との対話だけは、AIに代替できません。
合意形成ができていないと、上司や関係者が期待していることと、メンバーが実行していることにズレが生じてしまいます。組織人である以上、その状態では良い評価はもらえません。評価されなければ、人・金・時間といったリソースが調達できなくなり、できることが狭まってしまいます。
9月11日(木)開催の「MarkeZine Day」に富家氏が登壇します!
施策の全体像や優先順位を“伝わる形”に整理し、経営層や営業との対話をスムーズにするメソッド「CABフレーム」。その開発者であり、現場支援に豊富な経験を持つ富家翔平氏が登壇し、実践的なノウハウを公開します。
聴講者には、すぐに使える『CABフレーム』のスプレッドシートをプレゼント! ぜひご参加ください。