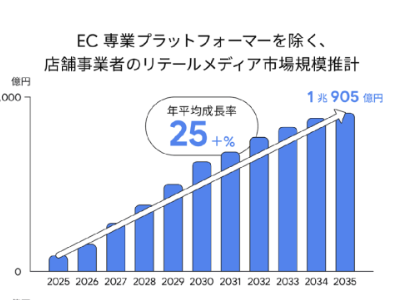「可視化へのニーズ」がMMM導入のきっかけに
MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)は、様々な施策の効果を定量的に可視化し、中長期的な戦略策定や予算配分など適切な意思決定を実現する手法だ。デジタルシフトにともない注目されてきた手法である一方、導入や運用の実体験が語られる場面はまだ少ない。そこで本セッションでは、モデレーターのEVERRISE 松本健太郎氏の進行のもと、味の素と日本ピザハットの実践が明かされた。

はじめに日本ピザハットの薮内浩平氏が、MMMを導入した背景を紹介した。同社では長らくチラシ配布やテレビCMといったオフライン広告に多額の広告費を投じてきたが、2020年頃から、デジタル広告にシフトする必要性をより強く認識するようになった。ところが、それを実践に移すのは簡単ではなかったそうだ。
「皆、心の中ではデジタル広告をもっとやるべきだとわかっていながらも、今までと変えること、つまりテレビCMやチラシを減らすことに対する怖さがありました。そこで、これまで不透明だった広告効果を可視化できれば、デジタル広告への移行の後押しになると考え、MMMの導入を進めました」(薮内氏)

これを受けて松本氏は、MMM導入を通じて目指す姿について掘り下げた。「広告費をデジタルに寄せるための根拠を探していて、MMMにたどり着いたのか。それとも、まずはフラットに可視化しようというスタンスだったのか」という質問に対し、薮内氏は「見えないオフライン広告と、ほとんどの数字が可視化されているデジタル広告の間に、大きなギャップがありました。まずはフラットに、両者の効果を可視化することを目指しました」と回答した。
マーケティングの見える化と投資の最適化が課題
次にMMMの導入背景を語ったのは、味の素の金子拓実氏だ。同社で本格的にMMMの導入が始まったのは、およそ10年前。その背景には二つの要因があった。
一つはマネジメント層からの要望である。同社の生産部門や研究部門では、工場や設備への投資など、億単位の支出に対しては厳格な計画と稟議、導入後のレビューが求められてきた。そうした支出と比較すると、マーケティング投資に関しては、予算の枠組みこそあれ、費用の使い道や成果の検証は十分に行われていなかったという。この点に違和感を覚えたマネジメント層から、「マーケティングの見える化」を強く求められるようになった。
もう一つは現場の課題感だ。当時はデジタルシフトの流れを受け、全社戦略として「デジタル比率30%達成」といった目標が掲げられていた。しかし現場のマーケターには、「売り上げを牽引しているのは依然としてテレビ広告である」という肌感覚があり、限られた予算の中でテレビの配分を減らし、デジタルに振り向ける決定はしづらかった。
「このジレンマを解決するために、MMMが使えるのではないかと考えました。一部のブランドから解析を始め、やがて広告の売り上げ貢献度を定量的に説明できるようになり、さらにはテレビ広告を減らしてデジタル投資を増やした場合の売り上げシミュレーションも可能になりました。これが現場の安心感につながり、2019年頃からは全社規模でMMMを活用しています」(金子氏)

MMM導入の過程では、ビジネスモデルや扱う商材に由来する苦労もあった。味の素の商品は一部の直販チャネルを除き、卸店や量販店を介して生活者に届く。すなわち、広告コミュニケーションの接触から購買までをシングルソースで確認できない。
また、調味料のように生活者が家にストックする商品は、広告を見たからといってすぐに購入が発生するわけではない。認知や興味を蓄積し、次の購買のタイミングで選ばれることが重要になる。金子氏は「こうした事情を前提に、MMMの活用法についても、自社の特性に合うよう工夫しています」と補足した。