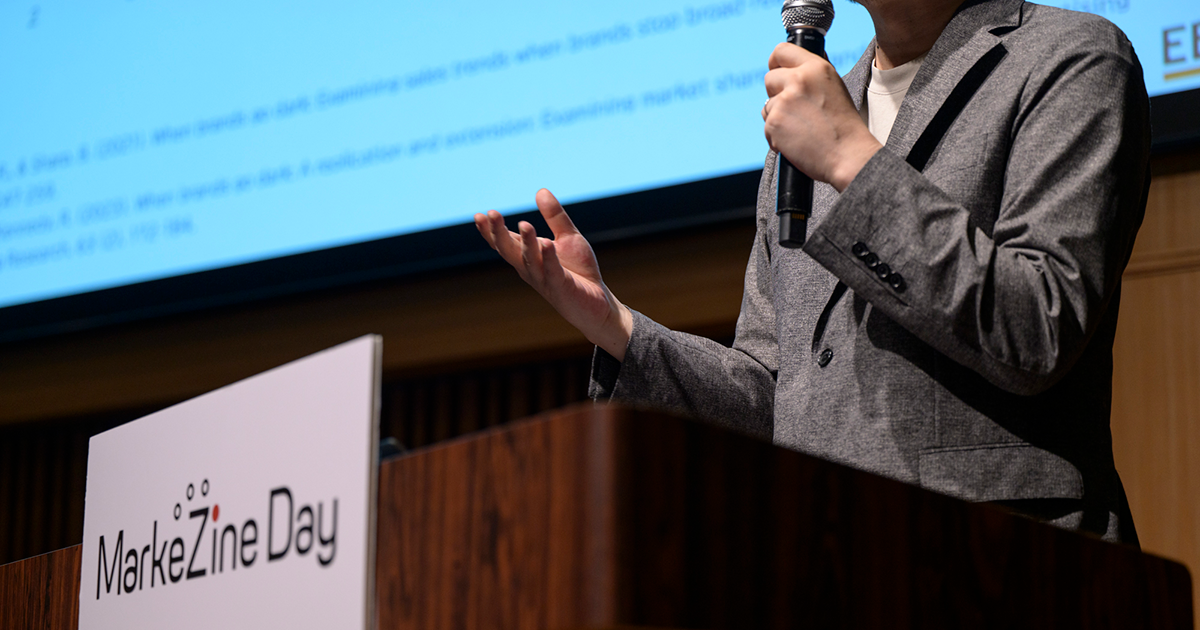マーケティングの意思決定にも「根拠」を
「なぜ広告がすぐに売上に結び付かないのか」「今月使った広告費はいつ・いくら返ってくるのか」と上司やクライアントに質問されて、みなさんは自信を持って答えられるだろうか。
広告は大きな予算が動くにもかかわらず、未だにエビデンスベースの考え方が浸透しておらず、根拠のある意思決定がなされていない。広告はどう効くのか? 広告には何ができて何ができないのか? 基本的な部分を正しく理解できている人のほうが、むしろ少ないかもしれない。
そうした時に役立つのが「エビデンスベーストマーケティング(EBM)」だ。EBMは、市場で繰り返し観測される「規則性」と「例外」を導き出し、それらをマーケティングの意思決定に活かそうとするもの。要は、「根拠のあるマーケティングをしよう」とする考え方である。

「日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(EBMI)」で研究主幹を務める芹澤連氏は、『戦略ごっこ』など自身の著書も含めた様々な場所でEBMの考え方や実証研究からの発見を啓蒙している。EBMIでは日本市場ならではの研究成果を発表しており、広告主が正しく意思決定するための学習リソース「広告意思決定論」も提供しているそうだ。
今回のMarkeZine Dayでは、「広告の効き方」「広告投資の考え方」に焦点を置いた講演が行われた。
広告に“買わせる力”はあるのか?
はじめに提示されたのは、「広告にできること/できないこと」というテーマ。芹澤氏は、次の2つのうち、どちらのイメージで広告業務に取り組んでいるか聴講者に問いかけた。
A:Strong Theory
広告を見せることで商品評価や知覚品質を変えたり、もっと好きになってもらったりすることができる。つまり広告には消費者を説得して買わせる力があるという考え方。
B:Weak Theory
広告に消費者を変えて動かすような力はなく、むしろブランドに関する記憶を維持・強化して、購買時に想起されやすくすることが主な役割だとする考え方。
「Strong TheoryとWeak Theoryとでは、広告の効き方に関する“世界観”がずいぶん違いますよね。Strong Theoryについては新興市場や高関与カテゴリなどで一部有効とする研究はありますが、広く一般的に有効だとするエビデンスは見当たりません。広告効果の実証研究から浮かび上がってくるのは、Weak Theory的な効き方のほうです。つまり、広告の役割は消費者を説得して選ばせることではなく、想起形成することにあります」(芹澤氏)
ここで、そもそも広告は購買プロセスのどの段階に効くのかを考えてみよう。購買プロセスを考慮集合が形成される前と後、つまり「認知・想起」段階と「評価・選択」段階に分けた時、大半の人は両方の段階で等価に広告が効くと思っている。しかし実際に広告が効くのは主に前者だ。実際、約20のカテゴリで300以上のブランドを対象に実施された大規模研究でも、広告で知覚品質に有意な影響を与えることは難しいという結果が出ているとのこと。
「広告は考慮集合に入る前の想起形成には役立つものの、既にブランドを想起できる人に対してたくさん広告したからといって、商品の理解をさらに深めたり、ブランドへの評価を高めたりする効果は薄いことがわかっています。そういう期待感で広告をすると、肩透かしを食らう可能性が高いでしょう」(芹澤氏)
まずは広告の効き方に関する世界観を、Strong TheoryからWeak Theoryに変えること。その上で、コミュニケーションの役割を正しく理解する必要があると言えるだろう。