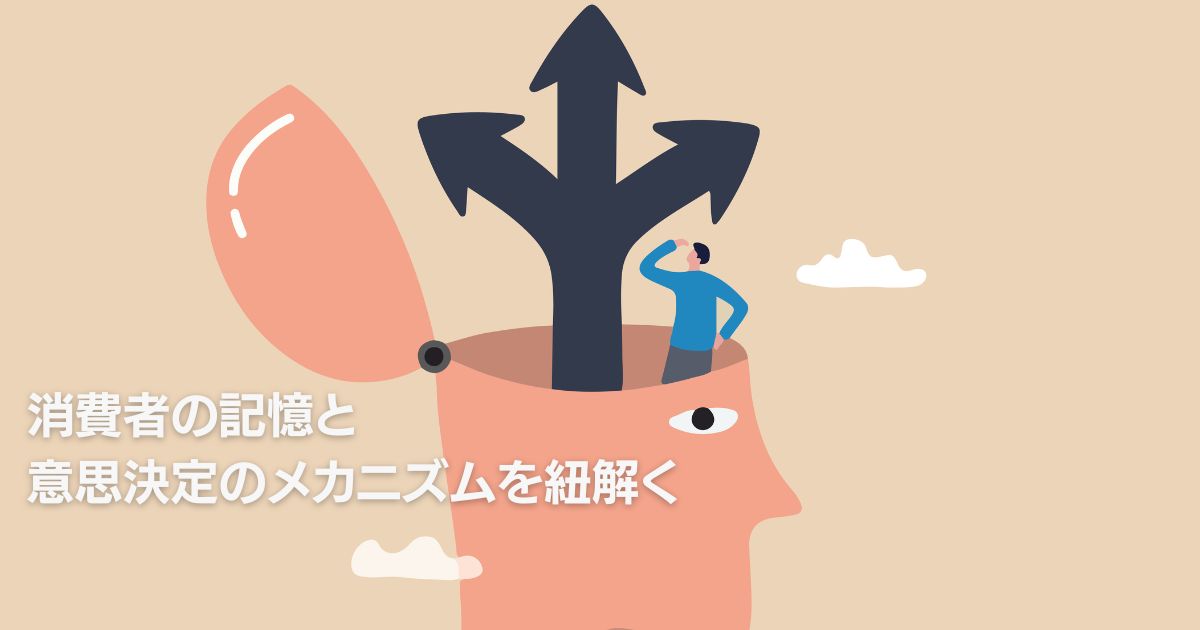正しいブランディングがビジネス成長の源泉
近年、広告コミュニケーションのデジタルシフトが進む中、マーケティング活動の在り方は大きく変化しました。特にデジタル広告は、クリック数やコンバージョン率といった消費者の行動指標によって成果を数値化しやすいため、様々なデジタルメディアの活用が加速しています。結果が可視化しやすいことは、施策の成果や投資対効果(ROI)を説明する上で、大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、このデジタルシフトは、意図せず新たな課題も生み出しています。それは、本来は区別されるべき「ブランド構築」と「販売促進」の境界が曖昧になり、両者が混同されるケースが増えている点です。
従来、テレビCMに代表されるような広告宣伝活動は、ブランドに対するポジティブなイメージを消費者の記憶に築くことを目的としていました。一方、販売促進活動は、カテゴリーニーズの顕在層に対して、検索連動広告や割引クーポン、店頭POP/サイネージなどを通じて、消費者の購買決定場面で行動を促す施策です。
ところが、短期的な成果が測定しやすくなった現在のデジタル環境では、本来、中長期的な視点で取り組むべきブランド構築の活動までもが、短期的な視点で評価される傾向があります。その結果、ブランディングへの投資が、将来の顧客基盤を育むための中長期的な資産形成であるにも関わらず、そのメカニズムが正しく理解されていないまま評価されてしまうケースが見受けられます。
短期的な販売促進活動に偏重すると、常に新たな投資が必要となり、持続的な成長が困難になります。持続的なビジネス成長を実現するためには、ブランディングのメカニズムを正しく理解し、中長期的な視点で取り組むことが不可欠です。これこそが、ビジネス成長の源泉となります。
ブランディングの目的と役割
では、持続的な成長につながる「ブランディング」とは、具体的にどのような目的と役割があるのでしょうか。その本質は、消費者の頭の中に働きかけ、自社ブランドが選ばれる仕組みを構築し、利益を創出することにあります。
ブランディングとは
- ブランドに対する「記憶」を創ること
- ブランドに意味を持たせ、付加価値(消費価値)を創ること
ブランディング投資によってビジネスを成長させるには、まず曖昧になりがちなブランディングの目的・役割を明確に定義し、マーケティングプロセス全体で共通認識を持つことが出発点となります。
そもそもマーケティングにおける「ブランド」とは、競合他社の商品・サービスと差別化を図るための「記号」を指します。名称やロゴなどは、他の商品・サービスと区別するための手段に過ぎません。ブランディングとは、その「記号」にどのような記憶や意味、すなわち「ブランド連想」を付与するかという点にあります。
言い換えれば、ブランディング活動とは、この記号に意味を与え、消費者の主観的な価値を築き上げていくプロセスです。この消費者が認識する価値を「消費価値」と呼びます。