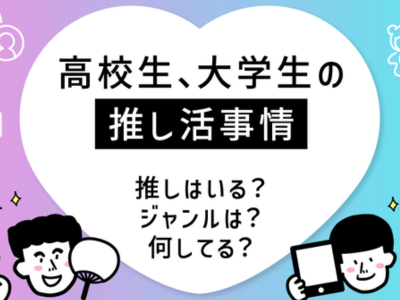iphoneならぬTwitterFone…一体なにができるのか?
1toNという双方向コミュニケーション方式をとる「Twitter」だが、ここのところスケーラビリティ構築の失敗でサービスダウンを繰り返し、果てにはCTO(最高技術責任者)の連続交代でシステム面の脆弱性が顕著となっているのは誰もが知るところだろう。
しかしながら、そんな逆境の中でも、Twitterユーザー(特に海外の)はその利便性ゆえにTwitterを支持し、成長性の面では目下驀進中だ。さて、そんなTwitterにとあるサードパーティーが乱入してきた。2008年5月にアイルランドの起業家Pat Phelanがはじめた「TwitterFone」という新サービスである。

どのようなサービスなのかというと、サービス上で自分の電話番号とTwitterアカウントの認証を行うと「録音用の電話番号(所属する地域の市内電話番号)」が付与され、音声ベースでTwitterにテキストメッセージの投稿ができるのだ。
もちろん、指定された電話番号を使って吹き込んだ音声は、音声認識ソフトウェアでテキストに自動変換されるのだが、全てが自動化されているというわけではない。認識できない部分については、人力で変換されているようである。
さて、このTwitterFoneだが…今年の8月に入って、急速にカバーエリアを拡大しつつある。拡大エリアの対象国には、日本も含まれており数ヶ月内には日本でも利用が可能になるとのこと。
現状、約2万人程度のTwitterユーザーが認証を済ませ、利用しているとのことだが、ユーザーの拡大に伴い、機能面でも充実が図られてきている。これまでは、発信者側からのメッセージがテキスト化されて投稿されるだけであったが、逆に自分に向けて発信されたテキストメッセージを、音声で聞くことができるようになった。
サードパーティーのサービス(TwitterFone)の乱入で、日本でもTwitterが再認識され、このような(またはこれに類似した)サービスのボトムアップにつながるのだろうか?
日本にも既にTwitterライクなサービスはあるが…
Twitterの登場を機に、日本でもTwitterライクなサービスは山ほど出てきたのは有名だ。例えば、ライブドア社が展開しているミニブログサービス「nowa」や、Movable Typeの開発元であるSix Apart社が運営する「vox」に類似機能が搭載されている。
しかしながら、これらが目に見えて”流行した”という兆候は一向に見られないのが現状である。なぜなのだろうか?
一般的には、ローカライズの問題・文化の異なりがよく指摘されるが、それではあまりにも抽象的である。では、具体的にはどうなのか…というと、私見ではあるが、日本及び日本人という人種がクローズ型コミュティを好む傾向にあるからと推測できる。簡単に言ってしまえば「村社会」という考え方だ。
日本では、「mixi」にも見られるように、常に内側に向いたコミュニティを形成しようとする。対して欧米諸国では、匿名性はいざ知らず、本名・顔写真を堂々と公開し、外へ外へとコミュニティの広がりをみせていく。つまり、欧米諸国はオープンソーシャルが常なのである。そう捉えれば、Twitterの普及が日本と欧米諸国で異なってくるのは当然のことなのではないかと思う。
日本の場合、双方向型コミュニティサービスは1toNではなく「1to特定N」というスタイルがポイントとなる。結局のところ、前記したような日本特有の指向性がある限り、Twitter及びTwitterライクなサービスは大きな成長を望むことはできないのではないだろうか。