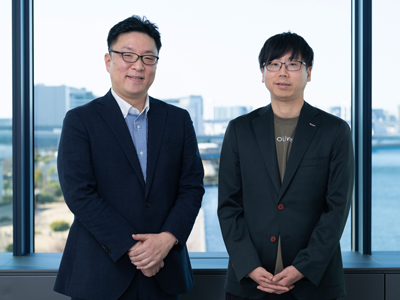調査・分析部門に求められる現場との伴走
明峯氏がログデータ分析の力に気づいたのは、前職のインテージ時代にあるメーカーと一緒に仕事をしたのがきっかけだったという。「ユーザーマインドの変化を探ってほしい」「販売量が変化した理由を知りたい」「ブランドの今後のポテンシャルを知りたい」などの要望をもらい、個人・個店のログデータを懸命に分析した明峯氏。

その過程で気づいたのは、データ粒度を細かくすると、サマリーベースではわからない多くの示唆を得ることができる反面、個人・個店ベースのブレ(個性)が分析結果の誤差として積み上がり、汎用的な知見を得るためのデータ解釈が難しくなるケースもあることだ。
もちろん、分析の精度を高めるにはデータ粒度が細かい方が良い。だが、調査を活用する部門が大きな粒度での意思決定を行っている場合、細かな粒度のデータから導いたミクロすぎて一般化しづらい調査分析を提供しても役に立たない。かつ、個人・個店ベースのブレが色濃く反映されたら、精度の高い全体像は描けない。つまり、実務上は「データ粒度は細ければ細かいほどいい」わけではないのだ。
明峯氏は「マーケティングデータには癖があります。データに翻弄されないようにするには、意思決定の目的に合わせた分析方法の見極めが大事と気付いたのです」と経験を通じて学んだことを打ち明けた。

現在はパナソニックに勤務する明峯氏だが、インテージ時代の経験から、多くの事業会社において、調査・分析を担当する部門は、製造、マーケティング、営業部門などに比べて軽視されやすい傾向があると感じているという。
事実、経営環境が悪化すれば、調査・分析部門はコストカットの対象になりやすい。さらには経営トップが代わると部門が縮小されることも珍しくなく、社内での立場が弱い。
そうなると、依頼元の部門が作る計画を通すための調査になったり、都合の良い分析結果を求められたりすることも少なくない。しかし、そのような出来レースの調査に甘んじていては、生活者と会社の長期的な利益につながらない、と明峯氏は考えている。
本来、組織の中で調査・分析を担当する部門は、第三者の立場で正しい意思決定をするための材料を提供しなければならない。だからこそ、「正しく調査を設計して実行することはプロとして当然のこと。分析だけしかやらないのではなく、事業部門との伴走が必要なのではないでしょうか」と明峯氏は訴える。
つまり、調査結果を提出して終わりにするのではなく、現場が調査結果を有効に使えるように、現場がどのような意思決定を行っているかを理解し、そのために調査を設計するとともに、現場からのフィードバックをうけて調査を改善することも求められているというのだ。

製造、マーケティング、営業といった各部門の同僚とタッグを組むには、調査・分析部門が彼らと共通言語を持ち、それぞれの業務を理解することが求められる。業務を理解することが、相互のコンセンサス形成では不可欠と明峯氏は語った。
広告効果測定で求められるオンラインとオフラインの統合評価
現在、明峯氏はパナソニックの国内家電事業で広告の効果測定を担当している。同社はブランドスローガン「A Better Life, A Better World」のもと、「家電」「住宅」「車載」「BtoB」の四つの事業領域でビジネスを展開している。
そのうち、明峯氏が担当する国内家電事業の商品は多岐にわたる。オーディオやテレビといった黒物家電に調理家電、空調機器に至るまで取扱商品は1万品番を超える。そうした各商品で様々なプロモーション施策を展開しているのだ。

たとえば、コーヒー豆の焙煎専用マシンの「The Roast」ではFacebookページの運用や商品説明会のを開催している。一方、エアコンの「Eolia(エオリア)」、ブルーレイ/DVDレコーダーの「DIGA(ディーガ)」などでは、王道のテレビCMを展開しており、次亜塩素酸を用いる空間除菌脱臭機「ziaino(ジアイーノ)」の場合、テレビCMに加えて交通広告や動画広告も実施している。
ここまで様々な施策を展開していると、どの施策がどの程度売り上げに貢献したかを確かめ、効果の高い施策に投資を割り当てる最適化を行うことが難しい。オンラインとオフラインという性質が異なる施策の効果を、同じ土俵で比較しなければならないからだ。
オンラインの施策は比較的簡単に効果を測定できる。CVR、CTR、CPAなど、個人レベルで行動のログデータを収集し、そのデータをすぐに集計して見ることは容易だ。データが豊富にある分、効果測定のスピードも速い。

ただし、オンライン単独で完結する施策は少ないため、オフライン施策とのつながりを把握する必要がある。
家電の場合、オフラインの施策は、専門雑誌、屋外広告、店頭販促などがある。しかし、これらの媒体は出稿してもログとして接触履歴を得ることができない。さらに、マス広告は認知獲得を目的としたものが多く、購買の意思決定から遠いという問題もある。その貢献度を明らかにするには、高度なデータ解析を行う必要があり、時間を要するのだ。

オフライン施策とオンライン施策を合わせ、全体を評価するにはどうしたらいいのか。チャネルを超えて、同一人物のメディア接触から購買行動までのデータを取得する「シングルソースデータ」が解決策の1つである。
だが、シングルソースデータにはまだ課題も多いのだという。そもそもテレビ・スマートフォン・PCの三つのデバイス全てに接触するモニター数が少ない。また、オフラインはテレビCMが中心で、雑誌や屋外広告のような他媒体の接触データの捕捉が難しい。さらに家電の場合、量販店で購入されることが多く、メディア接触と購買が分断されている。
これらの課題を踏まえ、明峯氏は「オンラインとオフラインの施策の統合評価では、『施策の実施実績』と『売上データ』の相関を見ることにしています」と明かした。
ログデータの分析にこだわりすぎると、オンラインとオフラインの施策を別々に評価することになってしまう。生活者から見れば、媒体は違っても同じ広告だということにかんがみれば、オンラインとオフラインの施策を統合的に評価することが望ましい。そのためには、相関分析でおおまかな傾向をつかむのが適切と考えたのだ。