あるべき体験を逆算する場のコンセプトとメッセージをつくる
体験の全体像が整理できたら、何をどのような順番で、具体的な体験としてデザインしていくのが良いのかを考えていく必要があります。
UXの期間においては「予期的UX」から始まりますが、最初にあるべき「体験全体 ≒ 累積(全体)的UX」の視点から考えていくことが重要です。
どのような体験や場をつくりたいのかといった場のコンセプトが明確にされていないとプロジェクトメンバーでも認識がずれてしまい、ワークショップの開催意図を社内に伝えていく上でもメッセージがぼんやりしたものになってしまうためです。
では、場のコンセプトをどのように導き出していくのか。そのために、まず経営メンバーの思いや意思をヒアリングします。その内容をふまえ、全体を通して「どのような場にしたいのか」についてキーワードをだしながらイメージをすり合わせていきます。
ヘイで重視したキーワードは「多様さ」「対話」「葛藤」の3つでした。ヘイはそれぞれユニークな組織文化を持った事業会社3社が一緒になった会社であり、多様な価値観や視点を持ったメンバーがいることが背景にあったからです。
多様でユニークなメンバーによる対話的なプロセスを、数百人を超える規模、かつフルオンラインで実現したい。そのために、オンラインカンファレンスの場のように、誰もが主役として認め合うことから始めたい――。そんな思いから導き出されたキーワードは「オールスター」でした。
オールスターなヘイのメンバーが集い、未来へ進んでいくことを目指す場。そこからワークショップのプログラムタイトルを「オールスターヘイ」と定め、次のようなキービジュアルとメッセージへと落とし込んで、社内へアナウンスしていきました。

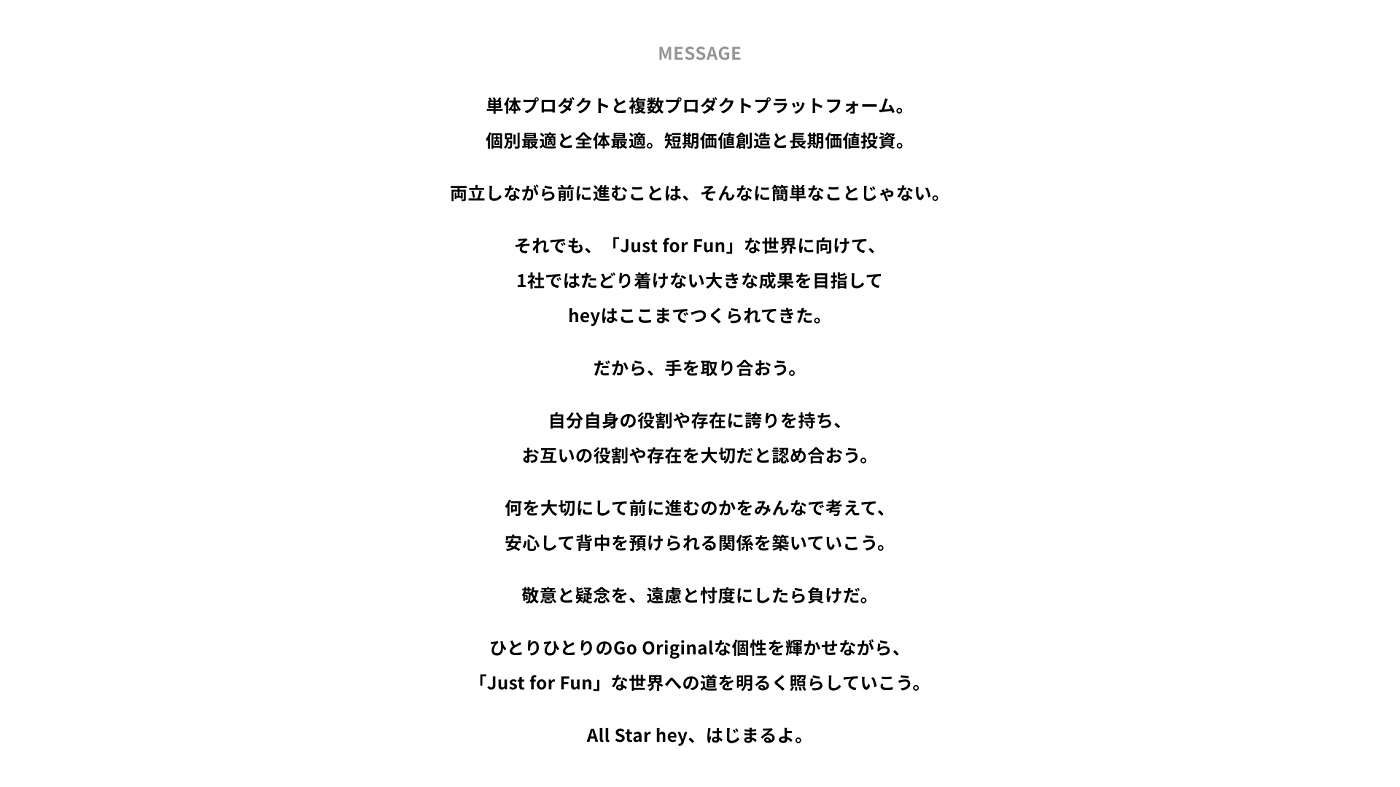
ジャーニー全体のタイムラインをつくり青写真を共有する
次のステップで重要なのは、体験設計の核となるコンセプトとメッセージをふまえ、UXのどの期間においても場のコンセプトにある思いが感じられるような体験を設計に落とし込んでいくことです。
いつ、どこで、どのようなコンテンツに触れ、何を体験するのか、そこからどんなことを感じてもらいたいか。最初に作成したUXの期間のマップを土台に、UXのジャーニーマップをつくるときの流れを踏襲し、体験のパートごとにやるべきこと、実現すべきことを参加するメンバーの視点で整理していきます。
ヘイでは、2週間にわたるプログラムを、チャネル、コンテンツ、フィーリングの軸で体験全体を設計していきました。とくにコンテンツに関しては一度に情報過多にならないように配慮しながら、開催直前期は徐々に関心を高めていけるよう、日ごとに期間を区切ってコンテンツを用意。設計したタイムラインをもとにプロジェクトメンバーで体験のイメージをすり合わせていき、各タイムスパンごとに新たなメンバーを巻き込みながら具体的な準備を進めていきました。

具体的な体験の青写真ができたところで、必要に応じて関係者を巻き込みながら、ワークショップの設計したり、コンテンツを制作し実行するフェーズに移っていきます。
では、実際のワークショップやコンテンツをどのようにデザインし、届けていくのが良いのか。次回の記事では実際の事例をもとに、制作や進行のポイントをお伝えします。

































