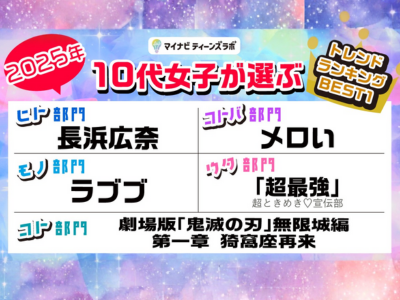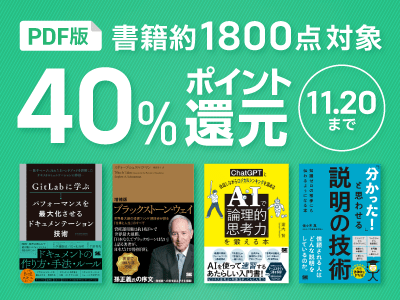LGBTQ+の権利について声を上げるキャンペーン、そのインパクトは?
白石:同性婚の法制化の問題は今、社会的にも注目されています。このテーマでキャンペーンを実施した目的は何ですか。
小山:私たちはLGBTQ+の権利について、以前から声を上げています。もちろん、性的マイノリティに関する問題は同性婚の法制化だけではありません。しかし、同性婚が認められれば、より多くの人の理解が深まったり、差別的な考えが緩和されたりすることにつながります。社会に対するインパクトが大きいと考え、このテーマを設定しました。
私たちのチャリティパートナーに「結婚の自由をすべての人に」という団体があり、その団体名をそのままキャンペーンの名称にしました。草の根で社会課題に取り組む団体に企業として関わることで、尽力している人たちの声を広く波及させることができます。2022年3月に第1弾、7月に第2弾と、2段構えでキャンペーンを実施しました。
キャンペーンでは、同性カップルが結婚できないことでどんな支障があるのか、メッセージとして伝えることから始めました。パートナーシップ制度が広がっているのはすばらしいですが、結婚との違いを理解できていない人が多いのが現状です。また、チャリティ商品としてソープも用意しました。英国の商品開発者とやりとりして、一目でメッセージが伝わるようなものを作ってもらいました。

白石:私の小学生の息子は、ニュースなどを見て「男の子同士でも結婚できるんでしょ?」と聞いてきます。日本では現状では法的に結婚できないことを伝えると、「なぜなのか?」「できる国はどこか?」という質問が出てきます。LUSHのキャンペーンは、基本的な“知る権利”を満たすことにつながると思いました。

キャンペーン=商品販売のためのマーケティング活動ではない
白石:ちなみに、日本で展開するキャンペーンは、日本法人を中心に進めているのですか? 英国の本社からの指示などもあるのでしょうか。
小山:LUSHで社会課題をテーマにしたキャンペーンを実施する際、世界共通の社会課題であっても、現地の状況やその土地の人たちの肌感覚は現地法人でないとわかりませんので、基本的に「こうしないといけない」と言われることはありません。社会課題の根本的な解決が最大の目的なので、「商品販売のためのマーケティング活動にならないようにする」など、最も大切にしていること以外は信じて任せてもらえます。
白石:グローバル本社からのコントロールが強い、という傾向については外資系企業からはよく聞くことがあります。具体的なメッセージを発信しているLUSHがどうなのか気になっていました。
小山:グローバルとローカル、オフィスと店舗、スタッフとお客さま。そういったすべての関係において「強要しない」のがLUSHです。「こうしなさい」というインストラクションではなく、インスピレーションを提供します。自分たちで責任をもって考えることが基本です。
白石:スタッフにはキャンペーンへの参加も強制しないそうですね。方針を浸透させることに力を入れる企業は多いと思いますが、「自由で良い」というスタンスを明確に示すのは、なかなかできることではありません。同性婚の法制化キャンペーンでは、店舗スタッフにどのように伝えたのでしょうか。
小山:まずはラーニングの機会を設けて、現状を知ってもらいました。その際、賛成派だけでなく反対派も含めていろいろな声があることを伝えています。それによって、“自分の意見”を考えてもらいたいからです。
お客さまの中には反対意見を持つ人もいます。お客さまの意見を踏まえて、自分がどう思うのか伝えることが大切です。会社から与えられた台本を読むのではなく、お客さまと会話をする。それによって、お客さまがこの問題についてさらに考えるきっかけをつくる。それが私たちのやりたいことです。