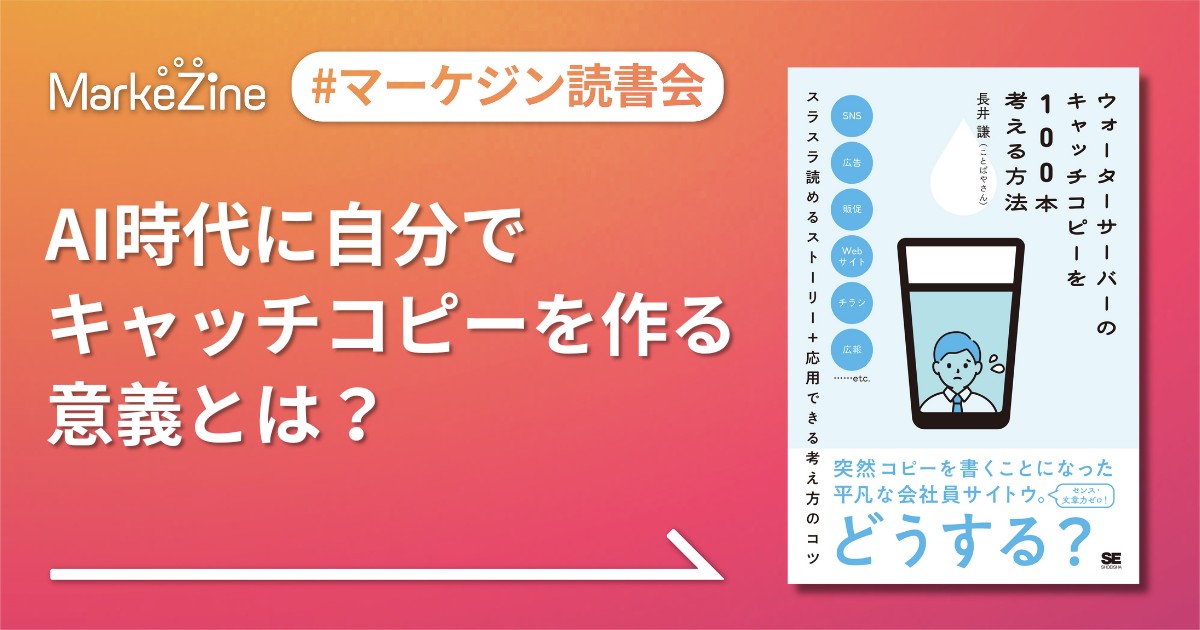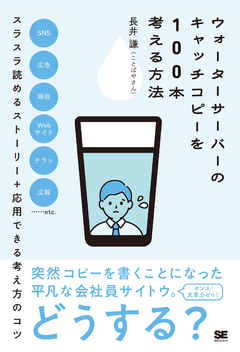AI時代になぜコピーライティングを学ぶべきか
『ウォーターサーバーのキャッチコピーを100本考える方法』という書名を見た瞬間、こう思いませんでしたか?
「AIでいくらでもキャッチコピーを作れるようになったのに、この本って読む必要ある?」
実際、私もそうでした。
キャッチコピーを自分で100本作るのは大変ですが、AIを使えば数秒で100個でも1000個でも作れてしまいます。
その中からよさげなのを選んでAIにブラッシュアップさせれば、どんな商品でもどんな媒体でも、それなりに使えそうなキャッチコピーができるでしょう(つぎはぎして構成する手も)。
こういうことが誰にでも簡単にできるようになったのに、なぜ自分でキャッチコピーを作れるようになるための本が必要なのでしょうか。
実は本書は、単にキャッチコピーの作り方を解説しているだけではありません。
本書はキャッチコピーの作り方を通して、消費者や顧客のインサイトを深く理解し、商品の本質的な提供価値を見出し、それを言葉で表現して伝えたい相手に伝えるための方法を解説している本なのです。
これはまさにマーケターにとって最も重要なスキルであり、実力そのものと言っても過言ではありません。むしろこれから先、どんな仕事をするうえでも役に立つスキルです。片手間でAIにキャッチコピーを作らせているだけだと、絶対に身につかないでしょう。
本書を読んでキャッチコピーを作れるようになるということは、すなわち「消費者のインサイトに合致した商品価値をターゲットに響く言葉で表現する」スキルを習得できるということです。
そしてこのスキルがあることで、自分でキャッチコピーを作れるだけでなく、AIにより効果的なキャッチコピーを作らせることができるようにもなります。
売上や想起率の向上など結果を出せるキャッチコピーの作り方に興味がある人に、もちろん本書はおすすめです。
そして、ただキャッチコピーの作り方を学べるだけでは食指が動かない人も、本書が顧客理解の方法と密接につながっていると知れば、ちょっと気になってくるのではないでしょうか。
物語形式で学ぶキャッチコピーのいろは
さて、本書の内容を紹介しましょう。
本書には広告制作会社に勤める平凡な会社員、斎藤さんが主人公として登場します。斎藤さんは広告営業が仕事であり、コピーライティングについて経験は言わずもがな、センスもないと自覚しています。
そんな斎藤さんがある日、クライアントの商品であるウォーターサーバー「MIZUTO」のキャッチコピーを作ることになる、というところからストーリーが始まります。
このストーリーを読み進めることで、読者は斎藤さんと一緒にキャッチコピーの作り方を学べるのです。
最初、斎藤さんはAIにキャッチコピーを作らせます。
- いつでも、どこでも、純粋な一杯を。
- おいしい水が、あなたのそばに。
- 家族の健康を守る、一滴の安心。
- ピュアな水で、心と身体に癒やしを。
これらは即却下。「MIZUTOらしさがない」「どのウォーターサーバーにも当てはまる」など散々な評価を受けます。
たしかに、それっぽいキャッチコピーではあります。しかし、現在のAIは「それっぽい」、つまり平均的なクリエイティブを作るのが得意なので、商品の特徴や想定ユーザーのこと、利用文脈などの情報をかなりしっかり与えないと、商品の独自性を伝える言葉は作ってくれません。
そのことを痛感した斎藤さんは、ここから試行錯誤して、様々な角度からキャッチコピーの作り方を学んでいきます。
大事なのは伝えたい中身と伝えたい相手の理解
最初の失敗のあと、斎藤さんは自分でもキャッチコピーを作りますが、どれも全然ウケない。資料でウォーターサーバー「MIZUTO」の特徴を読み込んでみても、いろいろあってどうすればいいのかわからないのです。
その中でなんとかひねり出したのが「おいしい水を、自由自在に。」。ちょっと自信ありげです。
しかし……特徴をまとめすぎて抽象的になり、かえって何の特徴も伝わってこない、と新入社員の泉さんが一刀両断。またもや悩む斎藤さんは、ふとクライアントの「水を選べる」という言葉を思い出します。
この「水を選べる」という特徴に絞ることで生まれたのが、「飲んでみたい水が、たくさんある。」というキャッチコピーです。これには上司の橋本さんからもいいキャッチコピーとお褒めの言葉。
さらに、斎藤さんは妻との会話から、ウォーターサーバーのターゲットである自分たちのような夫婦が「子どもにおいしい水を飲ませてあげたい」と感じるような、利用者の気持ちに寄り添った言葉の必要性を学びます。
これは、データ分析だけでは見えてこない顧客インサイトを、身近な視点から発見する方法です。
また、水を飲みたくなるときや具体的な利用シーンを思い浮かべることも、キャッチコピーを作るための大きなヒントになると気づきます。
そのあと斎藤さんが作ったキャッチコピーがこれ。
- 子どもに飲ませたい水ばかり。
- お風呂上がりは、いい水を飲みたい。
斎藤さん、一歩前進。
心を動かす表現のテクニックも大事
本書では具体的な表現のテクニックも紹介されています。
たとえば、漢字を置き換える。
斎藤さんが赤面しながら作ったのが「どの水も、おい水(すい)ぃ〜!」です。上司の橋本さんは「かっこいい言葉だけが、キャッチコピーじゃない」と高評価。
あるいは、オノマトペも効果的です。「スーッと染みわたる、おいしさ。」は、水が体に染み込んでいく印象を与えます。
他にはことわざのアレンジや擬人法、比喩も有効です。
- 急がば、休め。
- 日本の名水が、身体を流れる。
- うちには、水のなる樹がある。
こうした表現のテクニックは、顧客や商品の理解があってこそ。最初の斎藤さんのようにテクニックから入ってしまうと、やはり中身がなく、なんとなくエモい感じがするだけになりがちです。
エモいコピー、どうする?
ところで、キャッチコピーといえば「エモい」とは切っても切れない関係にあります。
ネットや街中で見かけるキャッチコピーは、どれもエモさを感じる(または「感じさせようとする」)ものが多いですよね。
斎藤さんも数々のキャッチコピーを作ったあと、とうとうクライアントに「もっと"エモーショナル"なコピーも見てみたい」と言われてしまいます。
ここまで来たらやり遂げるしかないということで、「そうだ 京都、行こう。」などの名コピーを参考に研究。
エモいキャッチコピーは「心が動く瞬間にシャッターを切るように、心が動く瞬間」を書き取ったものがキャッチコピーなのだと思い至ります。
さらに、本書で強調されるのが体験することの重要性です。斎藤さん、実はこの段階でもまだMIZUTOを使っておらず、その水も飲んでいませんでした。
それって最初にやることでは!? と、ついツッコミたくなりますが、斎藤さんは友人からの指摘で気づき、いざ実践。「実際に体験してこそ、リアリティを持った言葉にできる」ことを発見します。
そうやってできたキャッチコピーの1つが、「はじめてワクワクして水を飲んだ。」。
書くよりも引き出す、才能よりも執念
このあとも斎藤さんは商品開発者へヒアリングをしたり、キャッチコピーがどんな役割を持つべきかを学んだり、家電量販店のスタッフのトークにヒントを得たりして、表現に磨きをかけていきます。そのプロセスはまさしくマーケティング全般に通じるものです。
コピーライティングにおいて書く作業は全体の2割、他の8割はヒアリングとリサーチに費やすべきというコラムも印象的です。書くよりも、引き出すことが大事ということですね。
また、斎藤さんが体現してくれるように、心動かすコピーを生み出すには才能よりも執念が大事なのです(これ自体は上司の橋本さんの言葉)。
斎藤さんは何度も案を却下されながら、めげずに試行錯誤した末にクライアントも納得のキャッチコピーを作り上げました。最終的にどんなキャッチコピーができたのかは、ぜひ本書で確かめてください。
本書を読み終える頃には、きっと皆さんも自分でキャッチコピーを作ってみたい、作れそうだと思っているかもしれません。
もしすでに仕事として実践している人なら、キャッチコピーを作るために顧客のインサイトに精神を研ぎ澄ませ、商品が持つ本当の価値は何なのかを問い直したくなるでしょう。
キャッチコピーは取ってつけたような言葉で飾った単なる宣伝文句ではなく、顧客と関係を築き、ブランドの価値を高める力を持つものです。
人がそうしたキャッチコピーに心を込めることは、いよいよAI時代に突入するこれからは、以前よりも大きな意味を持つようになっています。
本書は、あなたがAIに使われる作業者で終わるのか、それともAIを自在に操る戦略家になれるのか、その分水嶺となりうる1冊です。
#マーケジン読書会に参加しませんか?
マーケターのための読書コミュニティ「#マーケジン読書会」を始めました。
ぜひ本書を読んで、気づきや感想に「#マーケジン読書会」のハッシュタグをつけて、X(旧Twitter)に投稿してください。あなたの投稿が、次なるマーケティングのヒントにつながるかもしれません。