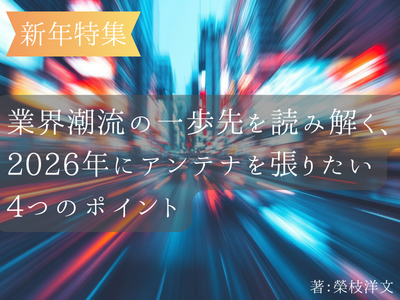従来のMMMモデルでは機能不全に。再定義が急務

IABが主催する「2025 Measurement Leadership Summit」で鮮明に浮かび上がったのは、MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)の再定義が急務であるという事実でした。従来のMMMは、テレビ・ラジオ・デジタル・OOHといった主要メディアのインパクトを長期的視点で捉えることに長けていましたが、消費者行動やメディア環境の変化はその前提を大きく揺るがしています。
セッション「Recalibrating Reality(新しい現実に即したメディア計測の再設計)」では、新興プラットフォームや購買行動の多様化によって、従来モデルでは取りこぼす要素が増えていることが指摘されました。米国では、CTVやDigital Video、Brand Safetyを含む複合メディア群を分析対象に組み込み、従来の到達率(Reach)や頻度(Frequency)指標を掛け合わせた高度なモデル設計が進行中です。これにより、ブランドリフトや購買貢献度をより精緻に把握し、戦略レベルの最適化に活用する事例が増えています。
また、AIやクラウド基盤の進化により、MMMデータを毎日更新できる環境が整いつつありますが、登壇者らは「更新頻度が高ければ良いわけではない」と警鐘を鳴らしました。粒度・意思決定サイクル・ラグ効果を踏まえ、戦略判断に適した更新頻度を見極めることが重要であり、分析を「動かしすぎない」勇気も必要だというのです。さらに、MMMは「長期的な戦略設計」、アトリビューション(AT)は「短期的な運用最適化」として役割を明確化し、それぞれを組織的に連携させる設計が求められると強調されました。
米国ではインクリメンタリティ系のプレーヤーが台頭

クロスチャネルの測定では、チャネル間の効果の重複や、プラットフォームごとに異なるイベント定義が足かせとなることが多いのが現実です。セッション「Making It Make Sense(クロスチャネル測定を意味あるものにする)」では、このアトリビューション重複問題を解消するための標準化と、それを阻害しない柔軟性の両立が議論されました。
具体的には、MMM、インクリメンタリティテスト、Conversion APIを組み合わせ、異なる時間軸と粒度を持つ複数手法を統合的に使うアプローチが米国では定着しつつあります。特に、Conversion APIの活用は、手動レポートからの脱却と測定精度の向上を同時に実現し、大手小売業ではリアルタイムに近い意思決定を可能にしました。
さらに、今米国ではMeasuredやLiftLabといったインクリメンタリティ系(※)の新興プレイヤーが台頭しています。これらはMMMとマルチタッチアトリビューション(MTA)の中間に位置し、即時性と精度のバランスを取る役割を担います。今後は、年次の戦略策定にMMM、月次にインクリメンタリティ、日次にMTAという縦割りではなく、各レイヤーのデータを一つのダッシュボードで横並びに表示し、すべての数値を加味した意思決定が次世代の広告運用標準になる可能性が高いでしょう。日本でもこうした統合型の意思決定環境は、近い将来、競争力の鍵となるはずです。
※インクリメンタリティ(Incrementality):あるマーケティング施策を実施した結果、「実施しなかった場合」と比較して、どれだけ追加で「増分」となる成果が生まれたかを測定する概念。ユーザーを2つのグループに分けて比較し、その差分によって施策の純粋な効果を把握する。