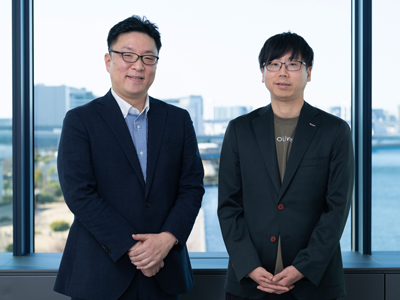デザイナーの仮説生成力は、市場創造においてどのように有効なのか
大﨑氏は著書『デザイナーのビジネススキル』の中で、「マーケティングの良い意味での対立軸として『デザイン』が機能すれば、事業や経営の成果を最大化できると考えている」と述べ、マーケティングから見たデザインへの期待として、次の2点を挙げている。
- 市場という集団の視点を補填する形で、個人視点から仮説生成やプロトタイピングをすること
- 感性を具現化し、買い手の認知形成を具体的に設計すること

総じて「集団」が起点となる市場創造のプロセスにおいて、「個人」起点からの発想を入れることで、買い手のニーズの輪郭をよりはっきりと浮き上がらせ、インサイトの獲得につなげていく。
アイデアが曖昧な段階から可視化し、仮説検討の解像度を上げていく。言葉だけでは抽象的になりがちな認知形成のストーリーを、感性の領域からも具体的に描いて洗練させていく。
デザイナーとの協働はこのようにマーケティングの検討の精度を上げ前進させる役割を果たすが、その価値の核心はデザイナーがもつ「仮説生成力」にある。
この「仮説生成力」とは何か。市場創造においてどのように有効なのか。大﨑氏の著書をもとに見ていこう。
デザイナーの「仮説生成力」とは?
仮説を立て検証や改善を繰り返しながら意思決定していくという仮説思考法自体は決して珍しいものではない。では、デザイナーの仮説生成力の特徴はどこにあるのだろうか。大﨑氏が考えるのは次の2つだ。
- 顧客やユーザーという「人」の視点に立ち、具体的に可視化される点
- 多義的な創発的思考として機能する点
まずは前者の「顧客やユーザーという『人』の視点に立ち、具体的に可視化される点」について、一般的な仮説思考と比較しながら次のように解説している。
一般的に仮説思考と言うと、膨大な情報量に対して確からしい仮説を設定し、情報を絞った検討の起点をつくること。そして、それに対して検証と修正を繰り返し、解決策の精度を上げていくことが挙げられます。(中略)仮説思考の起点となるのは、社会や市場や企業といった広範な概念です。マクロな視点からクローズアップするように仮説を組み立てていくのです。
一方、デザイナーはこのような仮説を把握しながらも、具体的な風景に思いをはせ、自分の構想を交え、人を起点に仮説を可視化します。企業が提案する価値は何か。どんな体験としてそれを感じるのか。感情の動きと反応はどのような流れか。魅力を感じる情報や機能は何か。どんな意志に共感するのか。行動を阻害する原因と促進する原因は何か──。事業の利益の源泉となるのは顧客やユーザーです。その視点から見える事業やその接点を具体化し、チームに鋭く突きつけます。
『デザイナーのビジネススキル』(p.121〜122)
一般的な仮説思考においても、「人」つまり「個人」視点がないわけではない。両者の違いは、仮説の「起点」がマクロなのか、人というミクロなのかだ。概念だったものがUIモックアップや体験シナリオ、ビジネスモデルの図といった見える形で具体化され、議論が活性化し、検討のスピードがより加速していく。
アブダクション思考を発揮する装置に
この個人視点を用いながら「具体的に可視化する」という点は、近年注目が高まりつつあるアブダクション思考とともに見ていきたい。
商品やサービスを一度可視化し、買い手の反応から改善していく手法はプロトタイピングとして知られているが、試作品をつくる前にまずは仮説を固めないといけないと思われがちだ。
もちろん仮説検証の手法としても有効だが、活用範囲はそれだけにとどまらない。これまでにない価値やニーズを生み出す市場創造においては、「アブダクション思考」を進めるものとなり得る。
アブダクション思考とは、アメリカの哲学者のチャールズ・サンダース・パース氏により提唱されたもので、「観察された驚くべき事実から、それを説明しうる仮説を発想的に導き出す推論」である。
演繹法や帰納法で導き出される推論の方が確実性は高いものの、不確実性の高いVUCAの時代においてはそもそも演繹法や帰納法で用いるべき前提の設定が難しいことからも注目されている。
アブダクション思考では、どのような仮説を設定するかは推論する人の発想力に委ねられることになるが、その際、「具体的に可視化」するというデザイナーの力が効力を発揮する。
アイデアやコンセプトが曖昧な段階でも、まずは手を動かして形にしてみる。そしてつくったものをマーケターや他のプロジェクトメンバーの多角的な視点でじっくり観察し、アイデアや着眼点を得て検討し、プロトタイピングを重ねながら新たな価値につながる仮説を見出していく。
生成AIの進化により、データをもとに論理的に仮説を立てることは以前よりも容易になっている。一方、市場創造においては、どの前提に立ち、どんな切り口から構想するかによって、仮説そのものや一連の意思決定の質が大きく左右される。
個人視点で体験や感情、文脈を考え発想し、可視化していくことで観察と議論を促進するデザイナーの仮説生成力は、アブダクション思考を発揮させる装置となり、将来予測が難しい時代においても新たな価値やニーズを生み出す可能性を広げるだろう。
「創発的思考」×「戦略的思考」で、仮説思考のデメリットをカバーする
デザイナーの仮説生成力のもう1つの特徴の「多義的な創発的思考として機能する」とはどういうことだろうか?
一般的な仮説思考は、無数の情報から必要な情報を残して削ぎ落とし、戦略的なベクトルを示すように作用することが多いものです。それは検討チームの活動方向を揃えるための一義的な推進力として機能します。『選択と集中』を軸においた戦略的思考です。
一方、デザイナーの仮説生成は可視化されるがゆえに、自然と対話の装置となっていきます。情報を削ぎ落とすよりも、共創によって情報が増えていくこともあります。それは、一義的な戦略的思考というよりも、多義的な創発的思考として機能するもの。創発とは、個々のメンバーの相互作用によって予想し得ない新たな成果が生み出されることです。多様な専門性を持ったチームの中で、それぞれの発想を掛け合わせて仮説を発展させていく活動なのです。
『デザイナーのビジネススキル』(p.122)
戦略的思考と創発的思考に優劣があるということではない。重要なのは両者のバランスをどうとるかだ。「戦略的思考が活動の軸をつくり、創発的思考はそこに柔軟性を与え実現につなげる。バランスが重要なのです。」(『デザイナーのビジネススキル』より)
仮説が具体化されたものを目にすることで、対話が生まれる。それぞれがもつ専門分野における感性が刺激され、新たな観点が共有される。それらが交差することで、当初予想し得なかった新しいアイデアが生まれる。
情報が増えていくことは、一見非効率とも思えるかもしれない。しかしながらこうした創発的な作用を起こすデザイナーの仮説生成力は、一般的な仮説思考のデメリットとして言われる最適解の見落としや、イノベーションの起こりにくさといった面を解消するのではないだろうか。
マーケターとデザイナーとの協働に向けたコミュニケーションのあり方
ここまで見てきたように、可視化を伴う仮説生成力をもつデザイナーとの協働は、市場創造における仮説設定や意思決定をしていくプロセスにおいて、検討の質を高め、新たな価値・ニーズを生み出す可能性を広げる上で有用と言える。では具体的にどのように協働していけば、最大の効果を発揮できるのだろうか。
ここからは、ビジネスパーソン向けのデザインスクールを主宰する稲葉氏の著書『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』と、大﨑氏と稲葉氏の対談イベントの内容をもとに、より良いパートナーシップを築くための具体的な手掛かりを見ていきたい。
なぜデザインは「わかりにくい」と感じてしまうのか?
そもそも「デザイン」とは何か? 色や形のことだけではないということはわかるが、その本質や全容がどうもつかみきれない。デザインという営みそのものは、アウトプットから思考プロセスまで射程が広く文脈によって意味合いも変わるために、こう思っている方も多いだろう。
ビジネスパーソンにとってデザインがわかりづらい理由の一つとして、稲葉氏は著書の中で「『デザインとは何か?』の定義のずれ」を示唆している。
少し難しい言い方にはなりますが、先に結論をいうと、優秀なデザイナーはデザインを包括的に捉えたいと思い、一般的なビジネスパーソンは分割的に捉えたいと思っています。
だから、認識する定義がずれるのです。
『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』(p.99)
「包括的」と「分割的」に捉えるとはどういうことだろうか?
稲葉:一般的に企業は、マーケティング部や営業部など分野ごとに部署が分かれています。つまり縦割りの組織になっていて、能力について「分割」して考えるということが基本です。
一方でデザイナーは、デザイナーとしての専門知識だけではなく、マーケティングやセールス、経営などすべてを横断的に理解した「包括的」な視点をもっていないと、デザインはできないし、デザイナーとは言えないと捉えているんです。
なぜならモノをつくるにしても、例えば顧客のインサイトを理解したり、製造工程上の判断があったり、アフターサービスができるかどうかという観点で決めたりといったことが不可欠で、そうしないとつくれないためです。
こうしたデザイナーの考えを説明すると、ビジネスパーソンの方は分割で捉えようとするため、「デザイナーはどの分野なんですか?」となってしまう。デザイナーが何をしている人なのかがわかりづらくなってしまうんです。

「圧倒的な3つの強み」からデザインを理解する
では、デザインを理解するにはどうすればいいのだろうか?
稲葉氏は著書の中で、ビジネスパーソンの「分割的」な視点で捉えられるように、デザイナーがもつ圧倒的な「3つの強み」を挙げている。
一つ目は、視覚から情報を伝えること
二つ目は、感性的価値を生むこと
三つ目は、人間中心で考えること『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』(p.110)
デザイナーの強みを整理することは、マーケターにとってデザインの理解に役立つだけでなく、どのタイミングでデザイナーを巻き込むべきかを見極める手がかりにもなる。1つずつ見ていこう。
1つ目の「視覚から情報を伝えること」は、最もイメージしやすいだろう。企業ロゴや商品パッケージ、製品そのものがもつイメージやコンセプトといったさまざまな情報を、色や形を通して「可視化」して伝えていくことだ。だがこの可視化の力は、大﨑氏の著書で見てきたように、伝えたい情報が決まった後に活用できるだけではない。たとえばマーケティング施策を検討している初期段階にも大いに活かせる。
施策検討の初期段階では、仮説や選択肢が言葉で整理されがちだが、それらを視覚的に配し、関係者全員で共有することで、全体を俯瞰しながら関係性を捉え直したり、検討が曖昧なところに気づけたりするようになる。つまりデザイナーの「視覚から情報を伝える能力」は、意思決定に必要な論点を浮かび上がらせることにも寄与する。
2つ目の「感性的価値を生むこと」を、稲葉氏は著書の中で「美的、情緒的、精神的などの観点において喜びを感じること」「役に立つわけではないが、価値があるもの」と紹介している。前述の大﨑氏の言葉で言えば「感性の具現化」の能力だ。
マーケターが得意とする「合理的価値」は、機能や価格、利便性といった比較可能な指標としておかれるところで、感性的価値の対とも言える。マーケティングの世界でも感性的価値は重視されているが、デザイナーは人間の感情や記憶、姿勢に働きかける感性的価値を具現化することに長けている。
AIの進化により、合理的価値の最適化や一般解が導きやすくなった今、企業が選ばれ続けるためには「なぜそれを選ぶのか」という意味づけがより重要になる。マーケターの合理的価値とデザイナーの感性的価値が重なり合うことで、その企業ならではの「選ばれる理由」が明確になっていくだろう。
前述した大﨑氏の「個人視点」ともつながるのが、3つ目の「人間中心で考えること」だが、これもマーケターにとって特別なことではない。人間中心で考えてプロセスを回しインサイトを探索していくといったことは、日々の業務の中で行われている。
デザイナーが特徴的なのは、人間中心の捉え方を「ユーザー」にとどめず、人間を取り巻く社会や環境、さらには未来にまで視野を広げて思考し「よりよい姿とは何か?」「新たに考えるべきことはないか?」と問いを探し続ける点にある、と稲葉氏は著書で語っている。
これは「今、何が求められているか」だけではなく、「これからどのような価値や意味を社会に提示すべきか」を考える上で、マーケターに新たな問いをもたらすのではないだろうか。人間中心で考えるということを、より長期的に構造的に捉え直すことで、市場創造につながる可能性がある。
「デザイン判断ができる人」を目指そう
こうした強みをもつデザイナーとの協働で最大の効果を出すために、マーケターに求められるのは、「市場創造のプロセスのどこにどうデザインを組み込むか」を判断できる存在となることだ。
稲葉氏は、そうした存在を「デザイン判断できるクリエイティブリーダー」と表現している。「デザイン判断」とは、「その時々のデザインが、目的にとって最適かどうかということをジャッジする」(稲葉氏)ことだが、必要な能力として以下の3つを紹介している。
- どこでデザインを使うかを決める力
- デザイナーに相談し、議論しながらアウトプットを判断する力
- 適切なデザイナーを選ぶ力
『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』(p.172)
稲葉:どの段階のデザインかによって、デザイン判断が発生するパートは変わってきます。つまり、色や形といったアウトプットのビジュアルなのか、サービスやコンセプト設計なのか、経営レベルでのデザイン導入に対するジャッジなのかにより、見るべき項目が異なります。
具体的な判断方法の一つとして、大﨑氏から、ある管理職の方が自身はデザイナーではない中で、アプリのUIデザインについてどのように判断しているかの例が語られた。
大﨑:色や形といったアウトプットを見るのではなく、何を考えてそれをつくったのか、どのような課題に対する対応としてそのデザインが生じているのかを、デザイナーに問いながら言語化し、その言語をもとに判断しているそうです。
デザイン組織の管理職の方であっても、ご自身はデザイナーではないケースは多いです。ビジネスにおけるデザインの活用が広がり続ける中、こうした能力は、デザイナーと一緒に動くマーケターや営業といった方などにも求められるものだと思います。

「できないことを理解する」ことが、協働の出発点
デザイン判断できるクリエイティブリーダーになるにあたり、「できないことを知る」ことの重要性についても対談イベントで語られた。
「できないことを知る」ことが、具体的にどのタイミングでデザイナーを巻き込むかを見極めたり、あらゆる段階でのデザインを判断していったりする能力の向上につながるのだという。
稲葉:デザインについてあまり知らない状態のときには、例えば「色と形を並べているだけだから、自分にもできそう」というふうに思ったことはありませんか?
「デザインを修正してほしいときに、『これをちょっとずらしてくれればいい』とオーダーしてしまい、デザイナーとのコミュニケーションがうまくいかなくなった経験はありませんか?」とお聞きすると、よくあるという反応をされるビジネスパーソンの方が多くいらっしゃいます。
これは、デザイナーの仕事の工程や能力の範囲というのを理解していないために、つい言ってしまうような状態だと思うんです。
コミュニケーションをよくしていくためには、事例をたくさん見ながら、そのデザインの何がいいのか、どうしてそのデザインにしているのかといった理由や背景を言語化しながら理解を深めていくことが必要です。
デザインスクールの授業でも実践しているのですが、デザイン事例を見て考えることで、多くの方が「こうつくったり考えたりするのは自分では無理だ」と気づきます。
ここで大事なのが、「できるかと言われたらできないが、これがいいというのはわかる」状態になることなんです。たとえばグルメ評論家は、料理人のようにはお料理はできないけれど、食べたら「これはすごい。なぜなら……」というのはわかる。
この状態が目指したいところです。デザイナーの専門性を理解することで、その能力をどう活かせばいいのか、どうバランスを取りながら意見を出し合うのがいいのか、デザイナーに何を聞き何を相談したらいいのかといったことが、見極められるようになってきます。
大﨑氏は「『できないことを知ること』は、リスペクトのある状態をいかにつくれるかにつながってくる」と示唆した。
相互理解とリスペクトが、市場創造の仮説と意思決定の質を上げる
対談イベントでは、「デザイン判断をする人がデザイナーからリスペクトされる存在となるには、どのようにすればよいのか?」という問いが参加者から投げかけられた。
稲葉:いろいろある中で一つお伝えするならば、「“how”ではなくて、“why”を軸に話そう」ということです。
リスペクトされないデザイン判断者がやりがちなのが、「この青色を赤色に変えてほしい」といったように、手段=howを具体的に指摘してしまうことです。するとデザイナーは「デザインは全体のバランスで見る必要があるのに、一部のことしか考えていないんだな」と思い、話しづらいデザイン判断者と捉えてしまう。
もちろんそのデザイン判断者に悪気はなく、具体的に指示した方が親切だと信じてやっているケースも多いのですが、デザイナーの立場からすると、親切ではなくなってしまうという齟齬が起きているんですよね。
そこで、「なぜ、そうしたいのか」というwhyを伝えることが大事になるんです。
whyを伝えるというのは、たとえば、「高級感を出したいので、この部分のデザインは他の可能性があると思うんですが、どう思いますか?」というふうに、理由や目的を示すことです。
その上で「どういうやり方がありますか?」と相談をする。すごく基本的なことのように思われるかもしれませんが、「そういう相談の仕方の方がよかったんですか!?」と驚かれるビジネスパーソンの方は意外と多いです。
whyを示されて相談されることで、デザイナーは「この人はデザインを議論する方法をわかっている。デザイナーに対するリスペクトをもって相談してくれている」となり、「だから自分もリスペクトできる」と思える。
お互いにリスペクトし合える関係性を築くための、大切なコミュニケーションのあり方の一つだと思っています。

大﨑:デザイナー側もマーケティングやセールスといった、デザイン判断者の方の役割や業務に関する知識をもち理解することが大事です。
たとえばデザイン判断者がセールスの方の場合、この局面においてはこれぐらいの期間で行い、このくらいの成果を上げなければいけないといった立場にあります。
デザイナーにセールスに関する知識がなく、相手の状況を尊重せずに話をしたら、当然ながら相手からのリスペクトは得られません。同時に、デザイン判断者に対してもリスペクトをもっているとは言えないでしょう。
デザイン判断者の仕事を理解する。その方が所属する組織全体で達成すべきことや個人として達成すべきことを理解する。こうしたことを基本に行うのが大事だと思います。

市場創造とは、新しい価値をつくると同時に、その価値がなぜ生まれ、なぜ選ばれるのかという「文脈」をも社会に提示していく営みとも言える。
個人視点や可視化を伴う仮説生成力をもつデザイナーと協働する意義は、アウトプットの質を高めるだけではなく、顧客理解から課題の発見と定義、仮説立案、顧客自身がハッとする潜在ニーズに刺さるサービスや製品を生み出すという一連のプロセスを、顧客や市場、社会からどのような意味として受け取られるのかという「文脈」まで含めて深められる点が大きい。
対談イベントの最後に、稲葉氏は「マーケターではないけれどマーケティングのことは大体知っている、営業パーソンではないけれど営業のことはなんとなくわかっているといったように、デザイン以外の領域では他の職域の理解をし合った上でチームになって動くことができている。その中にデザインへの知識も入っていけばいいだけ」と語った。
デザインが「意匠」という一側面のみで語られることも多く専門領域だけのものと思われがちだが、本稿で紹介してきた能力や機能で捉え直したとき、「マーケティングに詳しい人ほど、マーケティングとデザインを区分して話す行為はナンセンスだと感じるかもしれない」という著書の中での大﨑氏の言葉も腑に落ちるだろう。
マーケターとデザイナーが互いの専門性への理解とリスペクトをもって試行錯誤を重ねながら仮説と意思決定の精度を上げていく。そうした協働のあり方が、市場創造の可能性を広げていくのではないだろうか。