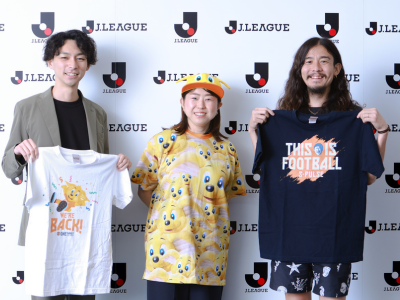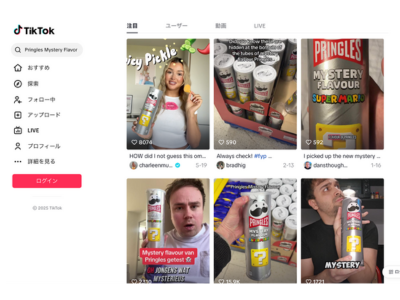人生における体験を考える
アストリッド・クライン氏は、日本を拠点として国際的に活躍する建築家。グーグル、ツタヤ、ソニー、ナイキなどをクライアントに持ち、Google日本オフィス、TUTAYA T-SITEなどを出がけてきた。ロフトワーク主催のイベント「Experience Design 2015 SPRING」キーノートセッションにおいて同氏は、自身の作品の制作背景をもとに、体験の重要性を語った。この記事では2つの事例を紹介したい。

アストリッド・クライン氏
クライン氏は「大事にしたいのはエクスペリエンス、体験です。建物の雰囲気に人は影響を受けます。建物を訪れた人が壁や床をどのように感じるか考えることは非常に重要です。また、建物に付帯する「人生における体験」を意識することが大切だと考えています」と考えを示し、具体的な事例の紹介に入った。
山梨県の小淵沢にあるリゾートホテル、リゾナーレ八ヶ岳に建てられたチャペルはクライン氏の作品の一つだ。他に類を見ないドーム型のチャペルは、二枚の葉が合わさった様子をイメージしたもの。そして、天井が開閉するようになっている。

結婚は人生で最も重要な経験の一つ。その経験の場である結婚式場を、見たことのないユニークなものにしよう、とクライン氏は考えたという。「結婚式で花嫁のヴェールが上げられ、誓いのキスをする。同じタイミングで、屋根の部分が開き、美しい自然が広がります。これは、思い出にのこる体験だと思います」(クライン氏)
体験とは、そこにいた人々が心を動かすことだ。もちろん、式を挙げた当事者だけでなく、参列者がチャペルで驚きを感じ、「今日はこういうことがあった」と家族や友人に伝えてもらうことも狙いだという。
良い体験をしている人が、更なる人を引き寄せる「T-SITE」
クライン氏の近年の代表作が、カルチュア・コンビニエンス・クラブがクライアントとなった「代官山 T-SITE」と「湘南 T-SITE」だ。プロジェクトで同社社長の増田 宗昭氏は、クライン氏にT-SITEを一つのパッケージにすることをオーダーした。つまり、建物や内容、商品やコンテンツ、サービスがすべて溶け込んで一つのものになっている空間の創出だ。

要求に対しクライン氏が出した答えの一つが、“建物にサイネージをする(看板をつける)のではなく、建物がサイネージになっている(建物自体が看板としての役割を持つ)”デザインだった。「よく見ると、建物がTのマークになっています。それだけだと、分かりにくかったので外壁も小さなTでできています」(クライン氏)

また、クライン氏が意識したのが「家のようにゆったりできる空間」の演出だ。内装も商業施設ではなく、自宅のリビングのように感じられる雰囲気作りがされている。「誰もが自分の家では落ち着くことができます。ですから、“おうち感”を出したいと思いました」(クライン氏)
家の特徴には「サイン(広告・宣伝など目印となるものもの)」が存在しないという点がある。そのため、T-SITEはアンチサインの方針がとられた。例えば、通常の商業施設の窓際や壁にはポスターなどが貼られている。一方、T-SITEでは窓際にテーブルが設置され、訪れた人が本や音楽、飲み物を楽しめるようになっている。「家のサインは表札くらい。あとはコンテンツと体験で構成されています。T-SITEも同様です。リラックスできる良質な時間を過ごしてもらえば、気分が高揚します。そうすれば、今日は自分にご褒美をしてもいいかな、と購買意欲もアップするかもしれません」(クライン氏)
そして、来訪者の体験は、さらなる来訪者の創出につながるとクライン氏は語る。なぜならば、店舗の外からは“自分の時間を楽しんでいる人の様子”が目に入るように設計されているからだ。窓の向こうに、気持ちよさそうに寛いでいる人々がいれば、どんな広告や看板よりも魅力がダイレクトに伝わる。これは高い集客効果につながるという。

加えて、品質も体験のデザインにおいて重要な要因になるという。「会社によっては、来店者を足の付いた財布だと考えている側面があります。そして、低コスト低品質の素材で建物を建ててしまう。そうではなくて、「私のためにそこまでしてくれるんだ」と感じてもらいたい。すると、店舗や施設に対する尊敬の気持ちが生まれます」(クライン氏)
また、クライン氏は体験のデザインについて、常識的に考えることが大切だと説明した。「あまり難しいことは考えません。体験で重視すべきは、お客様が何を考えているか・何が欲しいのかに対して、ストレートに答えられるかどうかです。そのためには、事業者目線ではなくお客様目線になることが重要です」(クライン氏)
インターネットが普及した今、家に居ながらできることが非常に多くなった。生活者にわざわざ足を運んでもらえるかどうかは、体験の有無が大きな分かれ目になる。「体験を考えることが一番なのです」クライン氏はセッションの最後をこの言葉で締めくくった。