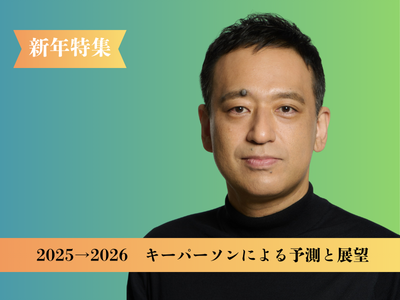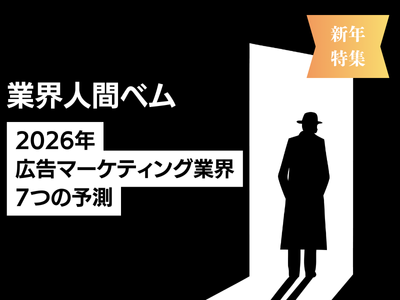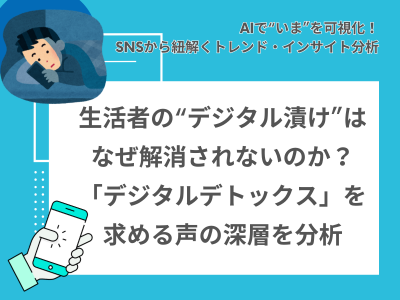メールマーケティングの投資対効果をどう判断するか
さて、メールマーケティングに取り組むにあたり、事前に考えておかなければならないことがある。その成果や投資対効果をどう判断するかという問題だ。

実際、マーケティング部がクロスセルを強化する施策を展開し売上単価が昨対比10%上がったとしても、別の事業部では「それは現場の店員が接客で努力したからだ」と捉えていることもある。またメールの目的範囲を「店舗への集客まで」として来客数を増加させたものの、経営層は実際に上がる店舗の売上額しか見ておらず、自身の活動が成果として認識されないケースも多い。
このように、マーケターが考える「成果」と、経営層から見る「成果」との間に大きな乖離があるケースは珍しくない。この乖離を放置しておくと、ある日突然「本当に投資に見合う効果があるのか?」と疑問を呈され、せっかく現場で手応えを感じていても、予算の削減や施策自体が打ち切りになる可能性がある。
この点に関し、チーターデジタル コンサルティング部 松田吉広氏は「各部署や立場で異なる成果やコストの考え方を、日ごろから整理しておく必要があります」と指摘する。

実際、投資対効果を測る上で定量的な把握がしやすいコストについても、「キャンペーンのインセンティブ費用をどこの事業部が担うのか」「施策に関わる社内人件費をどこまで計上するのか」など、企業ごとに試算する範囲に関するルールはまちまちだ。
成果に関してはさらに複雑で、たとえば集客している会員数やサイトへの誘導数、発生した売上額など、購買プロセスの中間指標と最終指標が混在する場合もあれば、認知度やブランド力など定量的な評価が難しいものもある。
松田氏は「中間指標と最終指標の関係性を可視化し、定量化できるデータで実態を押さえることがポイントになります」という。
たとえばある保険会社のメールマーケティング施策の場合、契約に至るまでの顧客行動をモデル化し、配信システムやWeb解析ツール、購買データベースから実際に取得できる中間指標と最終指標を設定。「資料請求数」をメールマーケティングの成果指標として定め、資料請求から契約に結びつく遷移率を係数としてかけ合わせることで売上に対する貢献度を数値化していったそうだ。
こういったルール作りは、業種・業態や製品・サービスの特性などにより状況が異なるため、ケースごとに考えていく必要があるという。

成果をいかに出しやすくするか
メールマーケティングも、ほかの様々な施策と同じく、導入期から成長期、そして成熟期、衰退期と、4つのフェーズを経て、次の新たな施策へと移行していく。松田氏は「投資対効果の最大化を目指すには、このプロセスに合わせて戦略を練る必要があります」という。
たとえば、初期投資が大きい導入期から、ノウハウが蓄積されて効果が上がっていく成長期にかけては、顧客との「関係構築」と「成果の刈り取り」のバランス、顧客視点からのフォローアップ・情報の取捨選択など、全体を俯瞰したシナリオ設計の作り込みやPDCAの推進が成果を大きく左右する。成熟期に入ると、むしろ業務効率化でコストカットを目指す方向に切り替えたほうが、リターン率が高くなる。
そして最も難しいのは、衰退期に入った時の対応だ。施策が衰退する理由は、年月が経つうちにユーザー構造が変化したり、技術革新によりコミュニケーション手段が多様化・陳腐化したりなど、いろいろな要因が考えられるが、いくら施策別の対策を打っても成果指標の数値が低い水準で定着してしまう場合は、視点を変えた別の取り組みが必要になる。
「こうなった場合、システムの刷新を含め、コミュニケーション設計・施策全体の見直しを図ったほうが効果的です」と松田氏はいう。メール経由の売上高・コミュニケーション満足度の低下をきっかけに、MA導入、シナリオの大規模なリニューアルを推進、結果停滞していた各種数値が大きく上昇したケースもあるという。
このように、自社のメールマーケティング施策がどういったプロジェクトのフェーズにあるのかを見定めた上で、戦略を練ることが、投資対効果を改善していくために重要だといえそうだ。