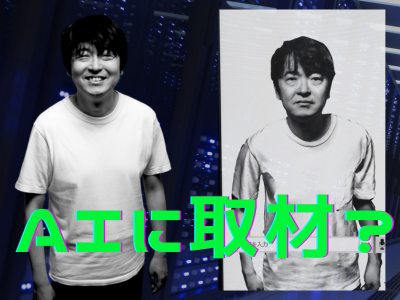DXはマーケティングの範疇を超え、経営レベルへ
安成:MarkeZine編集長の安成です。今回は、アドビで自社のDXを推進されている祖谷考克さんと、DX JAPANの植野大輔さんをお迎えし、2020年に生まれたDXの機運をさらに推進していくための考え方をうかがいます。まず、ご自身のキャリアでDXにどう関わってこられたか、うかがえますか?
祖谷:私は前職の博報堂、現職のアドビにて、長く企業のマーケティング支援に携わり、2019年からはアドビ自体のDXに取り組んでいます。企業の支援、また現職においても、博報堂で刷り込まれた「生活者発想」の姿勢が、自分の発想のベースになっています。
また近年では、支援する部門が狭義のマーケティングの範疇を超えて経営レベルになってきています。それに応じて、アドビも組織体制や支援の仕方を変えてきました。実は、植野さんともファミリーマートにいらした際、経営層に提案する中でご縁をいただいたんです。

博報堂で約15年にわたり、ブランドマーケティングとデジタル活用を中心に企業のマーケティングを支援。2013年、さらなるデジタル変革支援を志し、アドビに入社。Adobe Experience Cloudを中心としたマーケティングのサポートを経て、2016年に企業の経営レベルからデジタルシフトをサポートするデジタルストラテジー部門のリーダーに。2019年11月より、アドビ自体のDXを推進する部門の責任者を務める。
植野:そうでしたね。私の場合、DXについて2つのキャリア上の経験があります。ひとつはやはり2017年から約3年携わったファミリーマートでの経験が大きいです。といっても参画当初はDXというより、役割は会社全体のトランスフォーメーションでした。はじめはデジタルではなく、店頭業務の効率化、アルバイトスタッフ対応、販促PDCAの構築などに取り組みました。たとえば店頭の業務効率化のために、ストップウォッチを持って店舗に出向き、ファミチキを揚げるのにどれだけ時間がかかっているかを調査したこともあります。

三菱商事に入社、情報産業グループにて事業企画に従事。在籍中、ローソンに出向。ボストンコンサルティンググループ(BCG)を経て、2016年にファミリーマート澤田貴司社長に招聘され、ファミリーマート改革推進室長、マーケティング本部長などを歴任。直近では、デジタル統括責任者として全社デジタル戦略の策定、ファミペイの垂直立ち上げなどのDXを全面的に指揮した。2020年、企業のDXを支援するためDX JAPANを設立。
安成:えっ、店頭に立って調査をされていたんですか!
植野:そうなんです。24時間、調べました。とにかく緊急度と重要度が高い経営アジェンダに、経営直轄でひたすら取り組んできました。それが次第にDXになっていった、という感じです。
好評のAdobe Summitも「反省点ばかり」
安成:キャリアとDXについて、ひとつはファミリーマートでとおっしゃいましたが、もうひとつは?
植野:2013年にBCGに転職した際、入社初日のトレーニングから「トランスフォーメーション」という言葉が飛び出しました。当初、私は「なんだそれ? トランスフォーマーの映画じゃあるまいし」と思っていたんですが……理解が足りなかったのは私のほうだったと、今になってよく思い出す一件です。
現在の社名は「DX JAPAN」ですが、実はデジタルよりもトランスフォームのほうが本質です。実は、アドビさんは、ソリューションだけでなく、グローバルで自社のトランスフォームを掲げ、ソフトウェアのサブスクサービスに代表されるDXを成し遂げた会社として、ずっと着目していました。
安成:そうですね。アドビさんでは、毎年業界が注目しているAdobe Summitを、2020年はオンラインで開催されました。シャンタヌ・ナラヤンCEOをはじめとする経営層から繰り返し発せられたCXM(顧客体験管理)の概念が印象的でしたし、オンライン開催のクオリティも勉強になりました。
祖谷:ありがとうございます。リアルでつながれたころは、デジタルはどこかサブチャネルのように捉えられていましたが、2020年は完全に「デジタル上でどう顧客との関係を築くか」という課題が表面化した年でした。
ただ、Adobe Summitは1ヵ月足らずで準備したので、実は反省点ばかりだったんです。500以上予定していたセッションを140ほどに減らし、ライブ配信はリスクが高いので録画にして、内容もスライドに音声を重ねたものが中心でした。Twitterでは「深夜に起きたのに録画だった」と不満の声があり、胸に刺さりましたね。総合的に見て、私が考える理想には到達していなかった。デジタル上でも「その体験が受け入れていただけるのか」が最大の価値基準なのだという考えを、改めて痛感しました。ですから、その学びを7月のAdobe Experience Makers Liveでは、できる限り実行に移したつもりです。

“リアルイベントのオンライン版”という発想を捨て、オンラインでの新しいイベント体験をイチから構築した「Adobe Experience Makers Live 2020」。コンテンツの質だけでなく、心地よい視聴体験を提供。また、聴講者のセッションへの反響をデータとして収集する一方で、ワンクリックでの資料ダウンロードを実現するなど、シームレスな仕組みを整えた。まさにアドビの使命「デジタル体験を通じて世界を変える」を体現したオンラインイベントとなった。
CXM――顧客体験マネジメントの重要性
安成:そんなふうに感じられていたとは、意外です。ただ、確かに今、イベントに関わらず「心を動かす体験を提供できるか」が企業に問われるようになっています。その観点で、顧客体験をマネジメントするというCXMも提唱されているのだと思いますが、少し解説していただけますか?
祖谷:CXMを端的に言うと、顧客の視点で本当に望まれている体験を提供し続けることです。
これまでも、チャネルをまたいだ体験の設計が重視されてきましたが、あくまで1回のトランザクションに閉じて議論されていることが多かったのではないでしょうか。ですが、単発ではなく生涯にわたって自社と付き合ってほしいなら、トランザクションの発生時以外でも顧客を理解することが大事になります。その上で、一貫した整合性のある体験を提供し続けないと、それはいい体験になりません。
そうした根本的な発想の下で、チャネルもタイミングもメッセージも最適化した体験をマネジメントするのが、CXMです。それを支えるAdobe Experience Cloudも、どんどん進化しています。
安成:企業から届ける単発の体験を考えるのではなく、顧客のライフタイムの中で、自社の体験が全体としてどうあるべきかを考える、ということですか?
祖谷:そうですね。先ほど植野さんも「デジタルよりトランスフォーメーションが本質」と言われましたが、企業目線かつ単発で考えていくと、どうしてもデジタルという手段にフォーカスしがちです。でも、既に生活者はデジタルにすっかり親しみ、デジタル上で生み出される価値への期待値も上がっています。企業がその変わりゆく生活や価値観全体を捉えて、顧客が求めるサービスや困りごとへの解決策を提供できれば、成長の余地がすごく大きいと思います。あくまで、デジタルはそこに介在する手段です。
解消しつつある経営層の“DX幻想”
安成:なるほど。ひとつ、2020年9月にMarkeZine読者1,063人に回答いただいた調査結果を紹介すると、企業規模によらず4割近い企業が、「今後3年でマーケティング・販促予算は増える」と答えていました。特に中堅規模以下の企業では4割超で、デジタル投資が柱のひとつになると捉えると、DXへの遅れを課題と感じていることがうかがえます。ただ、祖谷さんが指摘されるように、手段が目的化しないようにすべきですね。

出典:『マーケティング最新動向調査2021』速報版レポート
祖谷:本当に、無駄な投資にならないようにしていただきたいと思います。
安成:植野さんはDX JAPANを設立されてすぐ後に、経営陣が抱く「DX幻想」を詳細に解説した連載記事を発表し、話題になりました(参考記事)。DXはデジタルマーケティングの強化だとか、データとAIですべてが解決できるといった7つの幻想を追い求めてしまうと、まさしく無駄な投資になってしまうと思います。
ただ、この半年でDXに向き合わざるを得なかった企業も多い中で、これらの幻想は晴れましたか? それともまだ残っている?
植野:幻想は晴れてきたと感じますが、その上で二極化しています。「DXとは単にデジタルツールで効率化することではない、経営アジェンダなのだ」と気づいて腹を括った企業と、現実はわかったけれど“DX疲れ”してしまった企業。
DX自体がバズワードになってしまい、最近ではDXと冠してもセミナーなどの集客が難しくなっているとも聞きます。これは、DXの議論が進んで具体的なフェーズになっているというポジティブな見方もできますが、飽き飽きしてきたネガティブな傾向もありそうです。

デジタルをトレンドとして捉えるなら、“DXごっこ”にしかならないと解説する
出典:定期誌『MarkeZine』第56号特集記事
DXが経営ごとなら、どの組織が推進すべき?
安成:顧客理解を起点に、自社がどうトランスフォーメーションしていくべきかを描いた上でDXが進むといいですが、なかなかそうではない現状があるわけですね。腹を括った企業では、幻想に惑わされずにDXを推進できているのでしょうか?
植野:その中でも、二分されています。トップダウンですぐに動けている企業と、次の中期経営計画にDX要素を盛り込むために1~2年かけて、これからプランニングする、などと悠長なことを言っている企業です。アジャイルと言いますが、小さく始められるのがデジタルの利点ですから、“Just do it!"で後者の企業は素早く着手してほしいですね。
祖谷さんが言われたように、今では生活者のほうがデジタルに慣れ、行動も変わっています。生活者起点で、まさに今現在のリアルなタッチポイントやライフタイムを押さえて、きめ細やかな体験を作っていかなければ。簡単なことではありませんが、ゆっくり計画している場合ではありません。
安成:では、DXが経営アジェンダなら、どのような組織が担うべきなのでしょうか。
植野:企業のDXを推進させる組織は、2つしかないと思います。ひとつは経営直轄の組織で、ITシステムの刷新からサプライチェーンの見直し、新規事業開発など全社の複数のDXプログラムを走らせる。そしてそれらを統括する、今だとCDOになるでしょうが、CDOが権限をもって経営トップとしっかりコミュニケーションを図っていく。
その実現には軋轢が多いようなら、“出島”ですね。自社社員と外部採用のデジタル人材を本業と離れた別組織に集めて“デジタル特区”を作って、進めていく。
祖谷:いずれにしても、権限がない組織には実行力がともなわないので、経営直轄であることが重要ですね。同時に、マーケティングとITの両方の視点も必ず必要だと思います。
“ラストワンマイル”を考えてきたマーケターの強み
植野:本当ですね。このマーケティングとITの両方の視点は欠かせません。DXを丸ごと外注なんてありえませんが、自社社員と外部採用の人では足りないマ―ケティングとITの専門の知見を外部パートナーから借りることは、とても大事です。この3者をうまく組み立てていくことが肝だと思います。
その点で、アドビさんのようなマーケティングとITにおいて屈指の力を持つ企業の役割はとても大きいと思っています。単に小手先のツールを導入して終わりという事業者と違って、自らDXを成し遂げた企業として、クライアントのトランスフォーメーションを見据えてしっかり並走してくれる熱量とケーパビリティがあるから。この数年、シリコンバレーなどでは「MTP(マッシブ・トランスフォーマティブ・パーパス)」という概念が言われています。野心的な変革の目標を持ち、実現できるかは、外部も含めた座組も非常に重要になるはずです。
安成:それは納得ですね。では、本質的なDXを見据えた体制の中で、マーケターはどう貢献できるでしょうか?
祖谷:DX推進組織でも、マーケターの「顧客に価値をどう届けるか」の、いわば“ラストワンマイル”を常に考え実践してきた強みは大いに生かせるはずです。アドビはずっと、顧客のために何を届けるべきかを考えて実践する“Experience Maker”の重要性を提唱しています。それは発想次第ですし、キャリアに捕らわれずに活躍できる可能性はあるでしょうが、やはりマーケターへの期待は大きいです。
植野:付け加えるなら、今後ますますあらゆるものがサービス化していくので、マーケターにはブランド体験を顧客起点でデザインする力が求められると思います。単発のデジタルマーケティング施策とは違う、プロダクトやサービス開発の筋肉が必要ですね。もしプロダクトがリアルなものなら、物流などの知見も大切ですし、最適なパートナーを見つけるビジネスプロデューサー的な視点も養えるといいと思います。