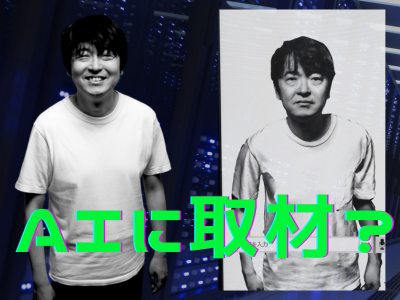最優秀賞は丸亀製麺に対する企画提案を行ったセプテーニが2年連続の受賞
今回の「LINE Planning Contest 2021」では、協賛企業として本田技研工業株式会社・公益社団法人Jリーグ・株式会社トリドールホールディングス(以下、トリドール)がRFPを提供。23社68プランの応募があり、一次選考を通過した11社15プランが最終選考に臨んだ。
結果、最優秀賞にはトリドールの飲食店ブランド「丸亀製麺」に対して企画提案を行った株式会社セプテーニ(以下、セプテーニ)が選出された。セプテーニは2年連続の受賞となり、昨年も参加した西原裕史郎氏と、今西洋平氏を中心とした4名体制のチームだ。

チーム編成について西原氏は「LINEというプラットフォームの特長を理解し、それをコミュニケーション設計に生かす業務を担う今西と、私を含めデータを用いたクリエイティブとコミュニケーション戦略を担当するメンバー編成です。企業とユーザーを繋ぐプロフェッショナル集団として臨むことができました」と胸を張る。
店舗外で「丸亀製麵」を体験してもらう方法
トリドールが提出したRFPでは、「店舗外における『丸亀製麺のブランドの強み』を生かした顧客体験の提供」が課題とされた。同社執行役員CMOの南雲克明氏は、RFP提出の背景とブランドの課題を振り返る。

南雲:店内だけでなく、店舗外でも丸亀製麺のブランド体験をお客様に伝えたいと考えていました。そのために、これまでSNSやテレビCMなど様々な施策を実施していますが、表現方法やコミュニケーション方法について、まだまだ工夫の余地があると思っていました。また、お客様へのタッチポイントとしても限定的であったため、日本のコミュニケーションインフラとなっているLINEを有効活用できないかと考えたのがRFP提出の背景です。
他のSNSと比較し、LINEを活用するメリットについて、今西氏はこう分析する。
今西:LINEは他のSNSと比較してクローズドなコミュニケーションが展開されるという特徴を持っています。今回企画したようなマンガを使ったコンテンツマーケティングでは、ユーザーからのエンゲージメントや拡散力の強いメディアを活用するケースが多いのですが、あえてLINEで送ることによって特別感を演出しています。投稿したコンテンツに紐づけてクーポンを配信し、LINEを経由したクーポン使用率等の数値を可視化することも可能です。また、トーク画面を開けば、過去に配信されたコンテンツやクーポンにスムーズにアクセスできる点もメリットとなっています。
セプテーニでは、RFPを読み込んだ上で、メンバーそれぞれが丸亀製麵の情報をできる限り集めた。トリドールが公開している情報や掲載記事に目を通すだけでなく、実際に店舗に足を運び、店内を観察したり、食事をしたり、五感を通じたインプットを行ったという。
西原:丸亀製麵が他社と異なる点は、店内製麺です。これは、外食産業の中でも特徴的で、どの店舗でも新鮮なうどんが食べられることは大きな強みだと思います。一方、そのことが半数近いお客様に伝わっていないこともわかりました。実際に私も店舗に行ったのですが、メニューや並べられている天ぷらを中心に来店客の目線が限定的で、店舗全体や製麺している様子にまで注意が向いていないことに気が付きました。そのため、店内製麺も含め「丸亀製麺らしさ」が詰まっている店舗自体のことを来店前に知ってもらえる設計が組めれば、店舗外でも丸亀製麺を体験でき、かつ入店した際の印象もより良くなる。そう考え、今回の企画を立案しました。
「LINE」と「マンガ」で今まで情報が届かなかった層とコネクト
丸亀製麺というブランドではなく、その店舗のことをユーザーに理解してもらうためには、どんな方法が適切か?セプテーニが導き出した回答は、「マンガ」を使ったコミュニケーションだった。
西原:マンガは手軽に閲覧できることに加え、しっかりと読み込んでもらえるので内容の理解度も高い傾向にあります。言い換えれば、マンガは老若男女が能動的に情報を取得しやすい表現方法です。そのため提案はLINE公式アカウントから配信したマンガを読めば、丸亀製麺の特長を自然とインプットできるコミュニケーション設計にしました。マンガの内容も、店内製麺や麺匠(めんしょう)という国内外合わせて1000店舗以上展開する丸亀製麺で麺を統括している唯一の存在を伝え、“丸亀製麵の裏側”の理解を進めるものにしました。

マンガのストーリー構成やマンガ家の選定は小野千代子氏と白井菜摘氏が中心となって行った。
小野:私も白井もクリエイターとしての経験があるため、「マンガ」というコンテンツの効果的な見せ方を理解しています。制作過程では一つひとつ絵に起こしながら、実際に店舗で感じた丸亀製麺らしさを最も魅力的に伝える方法を考えていきました。
白井:短い準備期間の中でテーマを決め、ストーリー展開や絵を仕上げていくことは骨の折れる作業でしたが、出来上がったときにチームメンバー全員が「これならいける」と自信が持てるものになりました。
「クリエイティブ」を重視しているセプテーニでは、グループ会社でマンガアプリを展開していることから多くのマンガ家を抱えている。また提案の上で「実際にユーザーとして体験すること」を信条としている。この2点が、今回の企画を形にする上で強みとなった。
企画のキャッチーさと伝え方のインパクトで審査員の心を掴む
昨年も最優秀賞を受賞しているため、コンテストに出場すること自体を迷ったと語る西原氏。だが、蓋を開ければ2年連続の最優秀賞。昨年の経験はどのように生かされたのだろうか。
西原:心がけたことは、プレゼンを聞く側の方々を飽きさせない工夫です。当日は複数の企業がプレゼンをしますし、今回はオンラインでの開催でした。聞く側の記憶に残るためには、企画のキャッチーさと短時間でもインパクトのある見せ方、伝え方を意識する必要があると考えました。キャッチーさはマンガで担保されているとはいえ、小さくてコマ数が多いものをプレゼンで表示しても見ている人のPC画面では一つ一つが読みにくいため、せっかくのドラマチックさが伝わりません。そこで、作った静止画マンガをさらに伝わりやすいように「動画化」し、BGMも付け加えてインパクトのある見せ方に工夫することで、飽きのこないプレゼンに仕上げました。
セプテーニのプレゼンを実際に聞いていた南雲氏は、「これなら実行できると思った」と企画を評価する。
南雲:私はマーケティング責任者として、机上の空論だと考えず、実現可能性とその結果をイメージしながらプレゼンを聞いていました。その中でセプテーニさんの企画は一番完成度が高く、実践的でした。今思うと、西原さんの計算されていた通りだったのですね(笑)。企画のロジックもしっかりしていましたし、お客様のインサイトもしっかり把握されていました。さらに表現手法もマンガという日本人が好きなものを選択されていて、マンガ自体の内容も面白かった。例えば、「麺匠」の絵が本人ととても似ていたんです。そういった細部のクリエイティブの質も高かったですね。これならば、お客様も楽しみながら丸亀製麺を知っていただけるのではないかと手応えを感じました。

今回のコンテストを機に、トリドールとセプテーニでは実際のビジネスにも発展。まさに「実践」につながる機会となった。
変化が激しい現在、新たな手法の模索・チャレンジが不可欠
最後に、セプテーニメンバーと南雲氏に、本コンテストを振り返ってもらった。
西原:セプテーニの強みである「クリエイティブ」を高く評価いただきとても嬉しく思っています。また、各社趣向を凝らしたプレゼンで、レベルの高い企画提案を拝見することができ、非常に勉強になることが多く、刺激になりました。
今西:去年とは違ってオンライン上で各社のプレゼンを拝見しましたが、企画の内容、各社の強み、それらの伝え方など多種多様なプレゼンを見ることができ、このコンテスト自体のレベルがグッと高まった事を感じていました。その中で2年連続の最優秀賞、そして唯一「Planning Partner」のDiamond認定代理店としてご評価いただけたことは大変光栄に思います。私たちが日ごろ取り組んでいるのは、8,900万人(LINEアプリMAU 2021年6月時点)という国内最大規模のユーザー基盤を活かした、「ユーザーとの接点の場」をどのようにデザインしていくかということです。それは企業側からの一方的な発信の場としてではなく、ユーザーのアクションを生み出す場、そしてそのアクションによるデータが生み出される場として、これからも企業のDX支援を担ってまいりたいと思います。

小野:実はコンテスト参加時、データコミュニケーション部は結成して半年ほどでした。その段階で企画に挑戦したことで、チームの結束にもつながる機会となりました。結果もついてきて嬉しいですし、今後のモチベーションにもなりました。
白井:コンテストをきっかけに実際に案件に繋がり、実納品に進められたことも、私達にとって新たな試みとなりました。今後もぜひお取り組みを続けられたらと思います。
南雲:自社では気づかないような提案をいただけたこと、実践につなげられていることが非常に有意義でした。会社としても個人としても、今の不確実な世の中で、新たな着眼点を用いたソリューションには積極的にチャレンジしていきたいと思っています。今後も機会があればまたコンテストに参加させていただくなど、いろいろな気付きをいただきたいと思います。
コロナ禍を契機にデジタルや非接触コミュニケーションが増加し、これまでの伝え方が通用しない中では、常に新しいコミュニケーション方法を模索していく必要がある。西原氏は「現在、ビジネスはこれまで以上に生ぬるい気持ちでは太刀打ちできない状況です。経験が生かせないからこそ、新たな手法を考えチャレンジしていきたい」と締めくくった。
「LINE Planning Contest」は新たな視点、施策に出会う機会になっているといえるだろう。