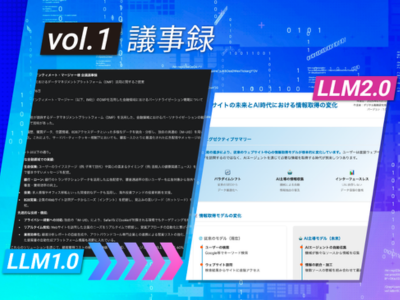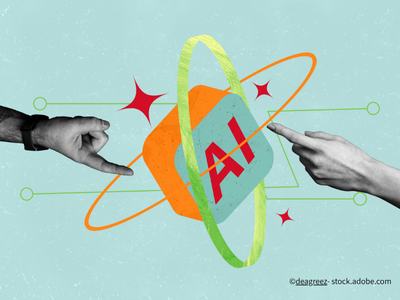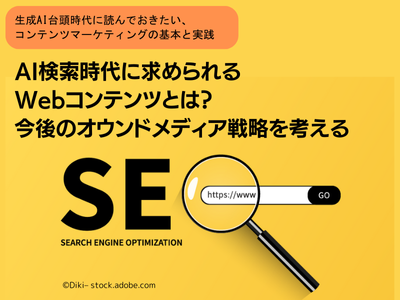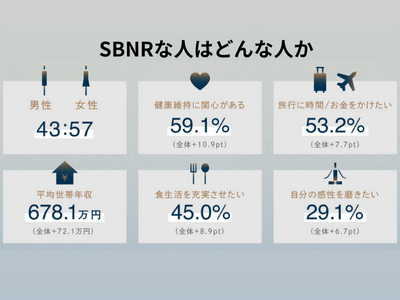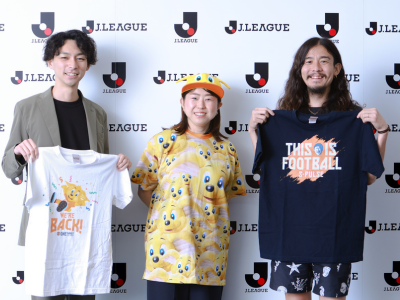プロダクトもCSもマーケティングの思考が必要
MZ:先ほど、PLGは協働とおっしゃっていました。マーケティング以外のチームのメンバーも、マーケティングのスキルや知識が必要なのでしょうか?
佐々木:PLGはプロダクトとマーケティングの領域がグラデーションです。マーケティングの基礎はある程度みんなが勉強していかなければならないし、キャッチアップが必要ですね。
例えば、弊社の場合はマーケティングチームのメインKPIは登録ユーザー数の最大化です。formrunはフリーミアムのサービスなので、登録されたお客様に有料プランへ移行していただくことが次のステップです。そこはファネル&データチームという別グループが担っています。
この時点でマーケティングをどこで定義するのかは難しく、幅が広いですよね。さらに、実利用を開始していただいたお客様の体験をより良くするために、カスタマーサクセスやサポートがMAツールを活用してシナリオを作成したり、提供するコンテンツを選定したりしています。ですから、彼らにもマーケティングの知識が必要です。
MZ:そうなると、反対にマーケターもプロダクトやCSのことを知っている必要がありますね。
佐々木:もちろんです。組織としても、プロダクトマネージャーを中心にユーザーエクスペリエンスとマーケティングとCSが一緒になっています。マーケターであれば、プロダクトマネージャーとセットでエンジニアやデザイナーと話し合いながら企画を詰めていきます。
データ面でもそれぞれの連携が欠かせません。例えばformrunには資料請求、問い合わせ、営業管理など、代表的な7大用途がありますが、それぞれ契約継続率も異なります。そのため、用途×契約継続率=LTVの数式が成り立ちます。マーケターが集客のためにSEOのキーワードを考える際も、このキーワードはボリュームが多いけどLTVは短い、などと先のことを考える必要がありますし、CSが持っているデータを知っている必要があります。
他にも、マーケティングが持つ検索キーワードやボリュームのデータと、CSが持つ獲得できたユーザー数と定着率を突合すると、登録を促せていても定着していないキーワードが見えてきます。これをユーザーからのシグナルと呼び、機能改善のヒントにしています。検索したものの「イケてないな」と思って離脱するわけですから、キーワードに関連する機能を作り込めば、離脱が減るはずですよね。
プロダクトチームが開発ロードマップを考える際に、これらのデータを参考に「この順番に開発すると新規ユーザーが増えそうだね」という会話をしています。
このように、プロダクトチームを中核に部署間がデータを共有し合って、わかり合っている組織を作らないとPLGは回りません。
SLGとPLGの使い分けをどう考える?
MZ:PLGはプロダクトの条件が揃うと非常に強いと感じます。一方で、すべてがPLGでまかなえるものではないですよね。御社にはSLG型のSaaSもありますが、企業全体が成長するためには、どのような舵取りが必要だとお考えですか?
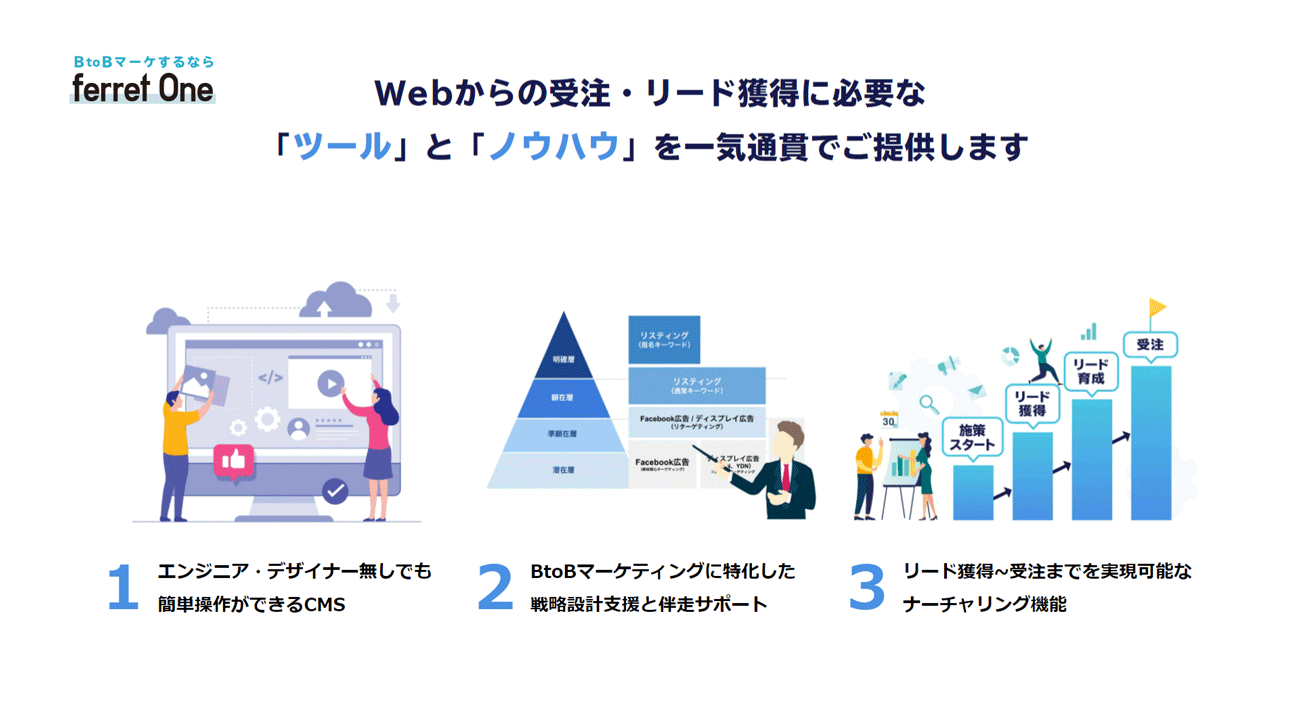
佐々木:SLGとPLGの切り分けとして、人を介在して商談化させる必要がある(=説明コストが必要)なプロダクトは、比較的アーリーマジョリティーからレイトマジョリティーに向けられたものだと思います。一方、PLGはユーザーが自分で探して使い始めることが前提になっているので、アーリーアダプター向けのプロダクトが得意だと考えています。
また、PLGは複合商品化させないことが大原則です。1つの課題に1個ずつ答えていく考え方です。そこで、弊社ではSLGはオールインワン型を志向するお客様向け。一方で、自分でツール類をそれぞれ選びたい方はPLG、という区別ができてきているように感じます。単価とビジネスモデルによって切り分けをして、市場面積の最大化を狙っているイメージですね。
MZ:PLG組織をこれから作る場合には、何から手をつけるべきでしょうか?
佐々木:プロダクトチームにしっかりと市民権を与えることです。プロダクトが中核であると決め切らない限りPLGは絶対に成立しません。これが最初のステップだと思います。次に、先程申し上げたPLGの条件をプロダクトが満たしているかを考えます。
そして、弊社で言うファネル改善をしっかりとやること。マーケティングチームは登録を追う、その後の有料転換をファネルチームが行う、その後のユーザーのアップセルクロスセルをCSが行うという組織自体は模倣できるのではないかなと思います。並行して、それぞれのチームの正しいアクションを導き出すデータチームを作ることが欠かせません。
実際にPLGをやっている人間からすると、PLGのあとにSLGに展開できても逆は無理だと思います。先程のスキル要件や低単価である必要を加味すると難しい。高単価商材のサービスが低単価商材をローンチさせると、ユーザーがそちらに行くリスクがありますよね。
これからPLGをやるなら、組織は新しいものをSLGとは別で作るといいでしょう。弊社も最初から私に組織を預けていただき、PLGでいくことを経営会議で握れたことも成長に大きく寄与していると感じています。
PLGによる経済圏を構築していきたい
MZ:ありがとうございます。取材の冒頭でPLG事業部では今後プロダクトを増やしていくと仰っていましたが、もう少し詳しく今後のお取り組みについて伺えますか?
佐々木:短期的な視点では、今年中にローンチするプロダクトがもう決まっています。これはformrunを利用するお客様から見た時に、前後のバリューチェーンに影響を与えるプロダクトです。
また、弊社が提供する各プロダクトがシームレスにつながることは大原則だと捉えていますので、中長期的には共通基盤の提供にもチャレンジしていきたいと思っています。その共通基盤とプロダクトを来年再来年と複数生み出していくことによって、PLGによる経済圏のようなものを構築していきたいと思っています。
MZ:次にローンチされるプロダクトが、PLG事業部が狙って生み出したものだと考えると、今後の動向が非常に楽しみですね。本日はありがとうございました。