データ環境を整備し、不快なコミュニケーションを回避せよ
お客様だけでなく、デジタル施策も多様化が進んでいます。認知獲得を目的としたオンラインイベントの増加などがその一例です。それらの変化を踏まえてフォローアップを準備できなければ、時に温度差のあるコミュニケーションによってお客様に不快な思いをもたらしてしまう危険性があります。
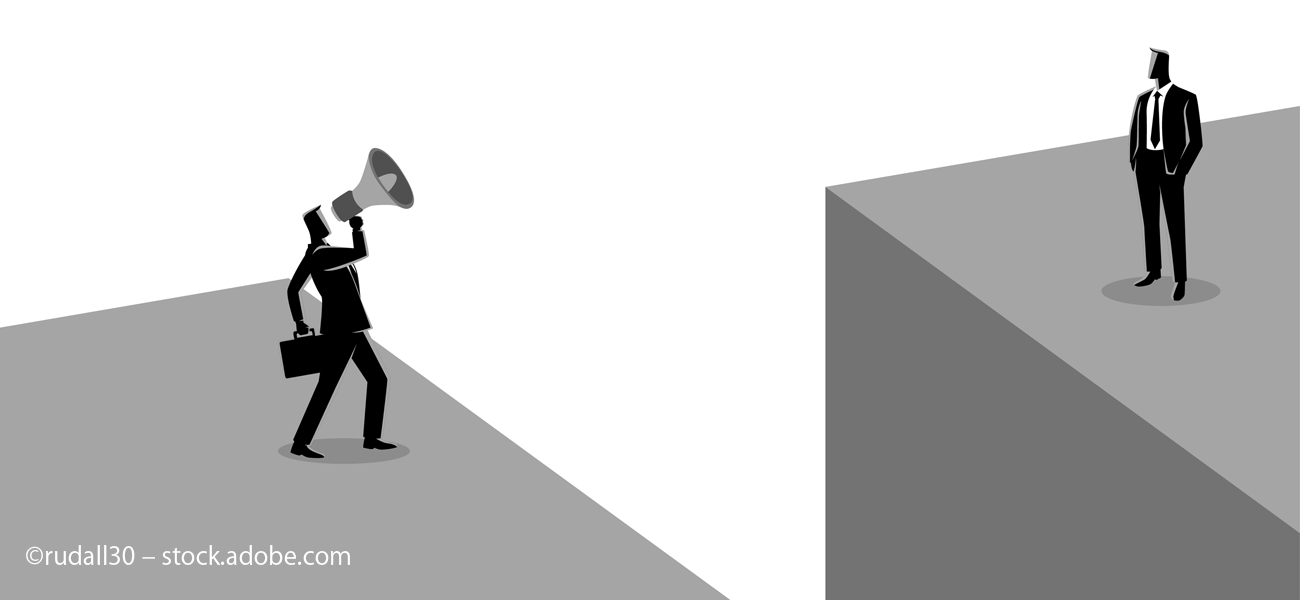
ただ、お客様にとって不快なコミュニケーションをゼロにすることは、実際には簡単ではありません。第1回で「日本のBtoB企業がデジタルツールをうまく使いこなせない理由の1つはデータハイジーンの問題(データが汚い/正確ではないこと)にある」と述べました。もしお客様とのやりとりが正しく記録されていなかった場合、お客様に同じ質問を何度も繰り返してしまったり、お客様のご希望とは異なる提案を行ったりしてしまいます。データの精度はコミュニケーションの質にも大きく関わってくるのです。
お客様との接点となる部門が多岐に亘ると、問題はさらに複雑になります。私たちアドビの場合も、データは日々の活動を通じて常にアップデートしているものの、お客様と直接コミュニケーションを取っている部門が複数存在しているため、それらの部門との連携を考える必要があります。直接販売だけでなく間接販売のビジネスにも力を入れている場合は、販売パートナーとの連携も必要になります。
今の企業には「信頼性の高い顧客プロファイルを常に参照可能な環境が整備されているかどうか」が問われているのです。
いつか訪れる「今です」に備えたMAツール
環境を整備した上で、お客様の状況に合わせたコミュニケーションを立案・実行していくわけですが、人的な対応では当然限界があります。そのためHOTなお客様への対応が優先され、特に多様化している「今じゃない」お客様への対応は後回しにされがちです。マーケティングの視点で考えれば、それは非常に大きな機会損失だと言えます。
現時点では「今じゃない」「今後もない」だとしても、人事異動や何かのイベントをきっかけに検討が進み「今です」に変わる時期が来る。母数は多いわけですから、潜在的なビジネスチャンスは決して少なくありません。だからこそ気持ちが変わるタイミングに備えてコミュニケーションを絶やさないようにし、ナーチャリングを行うことが重要なのです。
お客様それぞれに合わせたナーチャリングプログラムを展開しようとすると、キャンペーンの数は当然増えるため、何らかのルールに基づいた運用が必要になります。とは言え、ナーチャリング結果を集約して共有しようにも、集約自体が難しいのが実情。同じ人物が複数部署のお客様リストに登録されることもあり、最悪の場合お客様の心象を損ねる結果にもつながりかねません。マーケターにとっては深刻な問題です。だからこそMarketo EngageのようなMAツールを活用してプログラムを整理し、適切に運用していく必要があるのです。


































