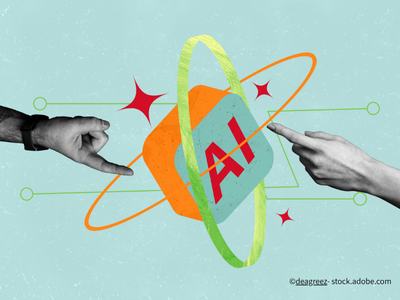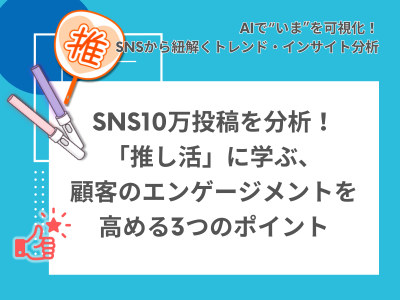ファンケルブランドを体現するリアル店舗
磯山:ファンケルさんは、自社ECだけでなくECモールでも商品を販売されています。どのような目的で使い分けていますか。

長谷川:ECモールに出店する前の前提として、我々は「商品」に関して自信を持って売ることができる恵まれた環境にいると思っています。だからこそ、Amazonや楽天市場のような競合ブランドが集まる場所でも十分に戦えると考えています。
ECモールを利用される方の中には、そこのモールでしか商品を買わない方がたくさんいらっしゃいます。我々としても自信を持っておすすめできる商品は、なるべく多くの方に使っていただきたいので、やはりECモールに戦いに行くべきだと思っています。
磯山:「商品に自信が持てる」というのは大前提ですよね。
長谷川:はい、そう思います。ただ、ECモールへの出店は最初から上手く言ったわけではなく、2010年にYahoo!ショッピングに進出した際はまったく売れず、上司から「今年ダメだったら店を閉めなさい」と言われたほどでした。
しかし、それまでの自社通販で得た知見を全部捨てて、モール独自の方法で販売し始めたところ、これが上手くいき売上が跳ね上がったんです。Yahoo!ショッピングで成功したノウハウをもとにAmazonや楽天市場などにも進出し、各モールから年間表彰されるほどになりました。
磯山:ファンケルさんは、通販以外にリアル店舗にも大きな強みがありますよね。オンライン/オフラインを融合させるOMOの取り組みはどのようなものを行っていますか?
長谷川:以前は店舗と通販それぞれでアプリを用意していたのですが、2021年の10月に統合しました。統合することで、利益率の高い販売チャネルに寄せようというわけではなく、あくまでお客様の体験価値を最大化するためのアプリを提供しています。
磯山:店舗と通販の体験は、やはりそれぞれ違いがあるものですか。
長谷川:ファンケルというブランドを体験してもらえる最高の場所は、店舗だと思っています。私は通販の担当ですが、店舗で行われる接客のレベルの高さには驚きます。
たとえば、明後日からキャンペーンが始まる商品を求めて来店いただいたお客様がいた場合、「明後日からキャンペーンが始まるので、今日は買わないでいいです」と数日分のサンプルを渡して、「もし商品が気に入ったら、キャンペーンが始まったら買いに来てくださいね」と帰っていただくこともあります。
磯山:その日の売上は減るかもしれないけど、それがお客様のためだし、長期的に見ればブランドの価値向上にもつながるということですよね。
長谷川:お客様には悲しんでほしくないんです。どこの店舗でもそういう接客ができるのが素晴らしいと思います。だから、基本的にはお客様の好きなところで買っていただいて構わないのですが、私としてはできれば店舗を使ってみてほしいと思います。
磯山:通販営業本部からそういう声が出るってすごいですね。店舗では接客に関する細かなマニュアルがあるんですか?
長谷川:マニュアルはありますが、先ほどお伝えしたような対応まで細かい部分のマニュアルはありません。一人ひとりがお客様を思い、お客様のために何ができるかを考えて行動することが大事ですので、お客様のために何ができるかを考え・学ぶ研修はあります。
磯山:確かに、今日お聞きしたようなファンケルブランドの考え方や価値観を共有していれば、自ずと取るべき行動は決まってくる、ということですね。
お客様の声は経営ミーティングで共有
磯山:販売した後のお客様の声の拾い方や、社内での共有はどのようにしていますか?
長谷川:週1回、経営陣も含めた部門長が集まる定例ミーティングで、最初に必ずお客様の声の共有をしています。また、お客様の声はデータベース化されていて、分類や時期を指定すれば社員は誰でも一覧で見られるようになってます。お電話のやり取りも登録されています。
ある時「今まで水につけたらすぐ剥がれていたジャムの瓶のラベルが、急に剥がれなくなった」という声が入ったことがあります。担当者に確認したところ、実は水につけなくても剥がれやすい素材に変更していて、逆に水につけると剥がれにくくなっていたことがわかりました。
ただ、その変更をお客様に伝えていなかったんですよね。それで「良いことをしたらちゃんと告知をしよう」と社長も含めて協議しました。
磯山:商品アンケートなどで声を集めたりもしますか?
長谷川:発売直後の感想に関するアンケートは商品開発担当が必ず行いますし、NPS定点調査も実施しています。
アンケート結果を自分たちの企画を通すための定量的な証拠として使うのではなく、お客様に喜んでいただける製品作りやサービス改善に本気で取り組むための仮説の材料として使っています。
磯山:発売直後の声で「今回はいけそうだ」や「まずそうだ」など大体わかるものですか?
長谷川:これまでもずっとお客様の声を丁寧に見てきましたので、ある程度わかります。
新商品の場合、売上の状態はそこそこでも、声の内容や数を見ながら「これは伸びるな」と読めたりします。一方で、リニューアル商品の場合には、発売直後は喜びの声よりもクレームが多くなることがあります。
磯山:そうなんですか。リニューアル前と比べてしまうからでしょうか。
長谷川:リニューアルしたことにともない、「前の商品は肌荒れを起こさなかったけど、今回は肌荒れを起こした」というパターンのクレームがわずかですが起こります。そして、そういった声ほど口コミに書きやすい側面があると思います。気を付けなくてはいけないのは、こういった声の一方で、今までと同じように使えている人はわざわざ声を上げにくいということです。
磯山:その人にとっては、リニューアルしたと言えど、以前と同じ系列の商品を使い続けているだけですもんね。
長谷川:もちろんクレームは真摯に受け止めますが、クレームだけを見て「このリニューアルは失敗だった」と考えてしまうと道を見誤ります。売上推移だけでなく、いただいた声の内容やアクセス状況などのデータから、満足いただいているお客様の存在も想像しながら、仮説検証に取り組むようにしています。