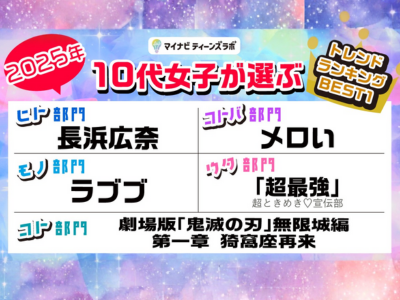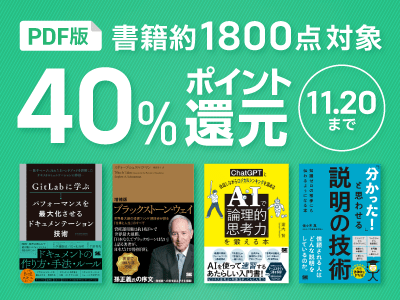マスコットはオリンピック三大収入源の1つ
ところで、「スポーツイベントにマスコット」というのはいつからだろうか? 実は歴史はけっこう古い。が、こんなに注目を浴びるようになったのは、84年のロス五輪からだ。以前にも触れたが、大会の組織委員長で、ビジネスの天才ユベロスの仕掛けによる。
70年代にかけてTVの普及が、五輪の大会規模拡大化に拍車をかけ、その結果大会の運営経費はうなぎ上りに上昇した。そしてついに、1976年のモントリオール大会では、組織委員会が破産してしまうという深刻な事態が生じた。その結果、開催地に立候補する都市がなくなってしまい、五輪は自ら運営経費を捻出する、つまり事業化する必要に迫られていた。
そういった状況下で颯爽と登場したのが、商売の天才「ピーター・ユベロス」で、五輪の商業化を徹底して進めた。その最大の基礎は「TVでの露出」に基づいたメディア価値。「五輪のTV放送権は、1ヵ国1局」という原則を確立し、放送権料を従来と比べ格段に高い値段に設定することに成功した。スポンサーシップも同様に、「一業種一社」制を確立した。富士フィルムにカテゴリーを取られたコダックは、地団太を踏んだのである。で、3つ目の収入の柱が、公式マスコットだった。
ユベロス氏の炯眼(けいがん)は、「権利」という商品の本質を見抜いていた。この商品は自然界に物理的には存在しない、知的にしか定義ができないので、ビジネスにするには法定が必要である。「知的財産権」と呼ばれるゆえんだ。
こういった「権利」という財の感覚は、ユベロス氏がユダヤ人であることと無関係ではないだろう。ハリウッドなどのソフト産業はユダヤ系の独壇場である。なぜか。ユダヤ人の迫害の歴史を見れば、彼らが「モノ」を持つことの危険性を身をもって知り尽くしていることがわかるはずだ。流浪の民である彼らは、時の為政者からいつなんどき「立ち退き」を命じられるかもしれないのだ(名作ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」を思い出すがいい)。

「即刻退去」では、持てるものは限られている。小さくて価値のあるもの(たとえば「ダイヤモンド」のような宝石がそれだ)を持とうとする。不動産などはもってのほかだ。IBMやシティーなどのユダヤ系の会社は、つい最近まで海外拠点として自社ビルを持たない方針だった。宝石よりも持ち運びやすい価値あるものが、「契約書」に書かれた権利だったのだ。