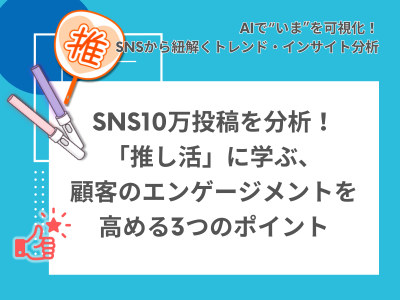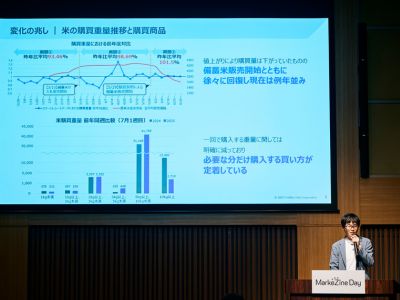情報発信のクオリティでスクリーニング……ブロガー、Facebook運営者
最近は、IT・Web業界においても、学生ブロガーが目立つようになってきました。内容も、読者モデルをしている女子学生の日記といったものではなく、キュレーションブログや、Webサービスを紹介するブログなど、コンテンツで勝負する、読ませるブログです。
有名な学生ブログ
- little_shotaro's blog (http://www.littleshotaro.com/)
- Nishilog (http://paranishian.blogspot.com/)
- For 智民生活 (http://d.hatena.ne.jp/gangjun/)

今後は、「ブログで月間2万PV以上の学生のみ」といった採用基準が設けられることも十分に考えられます。Facebookなら、「1000いいね!以上のFacebookページ運営者」になるでしょうか。
これらの基準は、「ソーシャルメディアを使いこなしていること」はもちろん、「情報発信側であること」と解釈できます。また、ソーシャルメディアを活用すれば、情報発信に特別なスキルが必要ないことから、よりその人の人間性など、ソフト面が評価されるのも大きなポイントです。
企業名は公開しませんが、昨年度の選考で、面接では評価が低かったにもかかわらず、ブログの内容を見て通過させた実例を知っています。今後、ますますこのような事例は増えてくるでしょう。
ネット上の行動履歴でスクリーニング……コメント、ディスカッション
ソーシャルメディア上(特にFacebook)での行動は、現実世界での行動に似ていることが多く、「積極的にコメントをする人は積極的に発言する人」、「多くの人と交流している人は交友関係が広い人」と捉えることができます。また、日本人のFacebookの使い方として、「他人のウォールに書き込まない」という特徴があるようです。この点を踏まえると、Facebookでコメントをするということは、「ハードルが高い」行為になります。
そのハードルの高さを巧みに使ったのが、エイチームです。Facebookの「ディスカッションボード」タブを使い、通常のエントリーシートにおいて、問題として扱われるような内容を「お題」として掲載していました。そして、学生にそのお題に回答してもらい、通常の一次選考と同じ扱いとしたそうです。なお、お題は一定期間ごとに変更し、どのお題に回答したとしても、一次選考の扱いとしました。また、投稿する内容を選ぶことも可能でした。
昨年度は、Facebookの実名制、顔写真付きという状況、かつ誰でも見ることができるオープンな中で、自らの考えを発信するという行動は、社会性と論理性の優れたアクティブ人材だと評価したのでしょう。
本年度は、すでに600社以上がFacebook採用ページを持っていることを考えると、さらにいろいろなスクリーニング方法が出てくることでしょう。いかに自社の採用戦略と整合性の取れたものにするかがポイントになります。