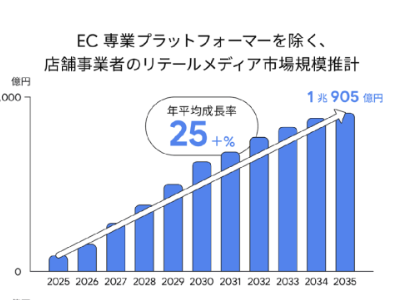会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

杉原 剛(スギハラ ゴウ)
アタラ株式会社 代表取締役CEO
ノバセル株式会社 エグゼクティブディレクターKDDI、インテルを経て、オーバーチュア(現Yahoo!検索広告)、Google日本法人で広告営業戦略を担当。2009年にマーケティングのコンサルティングサービスやツールを提供するアタラを創業。プラットフォーム広告、リテールメディアなどの最新情報を発信する、日本では数少ないプラットフォームビジネスアナリストでもある。「プラットフォームの思考回路」チャンネ...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア