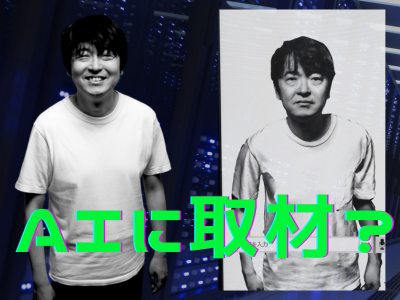DXとは、Digital Transformationの略語であり、直訳すれば「デジタルによる変容」を意味します。ビジネスの分野においては、デジタル技術によって新たな価値を創出し、競争優位性を確立するための重要なテーマでもあります。
今回はDXの基本的な定義や意味を確認したうえで、具体的な重要性や推進にあたって生まれる課題などを解説します。そのうえで、DX推進に取り組んでいる企業の事例も詳しく見ていきましょう。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DXについて正しく理解するためには、基本的な定義をおさえるとともに、似ている用語との区別も明確にしておく必要があります。
ここでは、デジタル化やIT化、CX、UXとの違いなども踏まえながら、DXの意味について確認しておきましょう。
DXの定義
DX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)とは、AIやIoT、ビッグデータなどのデジタル技術を用いて、業務フローの改善や新たなビジネスモデルの創出だけでなく、企業風土そのものまで変えることを指します。
DXはもともと、2004年にスウェーデンのウメオ大学に所属するエリック・ストルターマン教授らによって提唱された概念です。論文内では、DXを「ITの浸透によって人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること」と定義しています。
その後、ビジネスの分野においても単なる技術革新ではなく、「豊かなビジネスモデルの創出」といった目的を持つ言葉に発展していきました。
DXを推進することで、企業は変化の激しい市場に対応し、競争優位性を維持できるようになっていきます。
DXとデジタル化(デジタイゼーション/デジタライゼーション)の違い
DXに似ている言葉として、「デジタル化」を意味する「デジタイゼーション(Digitization)」や「デジタライゼーション(Digitalization)」という用語があります。
デジタイゼーションは、ある工程で効率化のためにデジタルツールを導入するような「部分的なデジタル化」を指す言葉です。具体的には、紙などの物質的なデータをデジタル形式へ変換することを指します。
一方のデジタライゼーションは、自社および外部の環境やビジネス戦略面も含めて、長期的な視野で「プロセス全体をデジタル化」していく取り組みのことです。
デジタイゼーションは局所的な変革、デジタライゼーションは全域的な変革と、それぞれ対象の範囲は異なりますが、いずれも社内に視点を向けた概念であることは違いありません。
それに対して、「デジタルトランスフォーメーション」は、一企業の取り組みを超えた社会全体までにリーチするものです。
たとえば、カメラの変化を例に挙げると、デジタイゼーションはフィルムカメラからデジタルカメラへの変革、デジタライゼーションは写真現像から写真データの送受信への変革と表現できます。
一方、DXはオンライン上で世界中の写真データがシェアされるような、よりダイナミックで根源的な変革を示す概念です。
DXとIT化の違い
IT化もDXと混同されやすい用語の一つですが、こちらは業務の効率化や生産性の向上を図るために、「既存の業務プロセスのまま」デジタル化を推進していくことを指します。たとえば、電話中心で商談や社内連絡を行っていた企業が、Eメールやチャットツールでコミュニケーションを図るといったイメージです。
それに対して、DXは組織やビジネスモデルそのものを変革していく取り組みであり、単なるIT化とは異なる概念を指しています。ただし、両者がまったくの無関係であるというわけではありません。
IT化を進めることで人的リソースにゆとりが生まれ、新たなビジネスモデルを構築していくというケースも多いため、IT化はDX推進実現のための手段やプロセスといえます。
DXとCX・UXの違い
CX(Customer Experience)は「顧客体験」という意味で、一般的には、顧客が企業や製品、サービスに触れる際に経験する快適さや新鮮さ、発見、感動などのプラスの価値を意味する用語として用いられています。
一方のUX(User Experience)は「ユーザー体験」という意味であり、商品やサービスの使いやすさなどを指す言葉です。
両者とも体験を指す概念ですが、一般的にUXはWebサイトやアプリなどのデジタル領域での体験における価値を、CXは店舗利用やアフターケアなどのリアルな顧客体験における価値を意味しているといえるでしょう。
DXが注目されている理由は?「2025年の崖」問題

DXが注目されているおもな理由として、2018年に経済産業省が公表した「DXレポート」内で指摘されている「2025年の崖」問題が挙げられます。
同レポートでは、多くの企業が抱える「基幹システムの老朽化」「担い手の高齢化」「先端IT人材の不足」などの課題を解消できない場合(=DXを実現できなかった場合)、毎年約12兆円の経済的な損失が生じる可能性があるとされています。
さらに、DXが行えなかった企業については、「データ活用機会の損失」「多大な技術的負債」「データ滅失リスクの増大」などにより、デジタル競争の敗者になってしまうといった内容の記述もあります。
これらの予測を受け、国内の企業全体としてDXに向けた取り組みを急加速させているのです。
DXの現状と企業が抱える課題

前述のとおり、DXの重要性は着実に浸透している一方、実際の現場では思うように推進が進まないというケースも少なくありません。
ここでは、DXを取り巻く現状と、企業が抱えがちな課題について見ていきましょう。
DX推進の現状
IPA(情報処理推進機構)が2022年8月に公表した「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート」(2021年版)によれば、2020年以前と比較すると、日本企業全体としてDX推進に向けた取り組みが加速している傾向が明らかにされています。
一方で、多くの企業が「DX人材の育成・確保が進まない」「ITシステムの全社最適や廃棄につまずきがある」などの課題を抱えていることも浮き彫りになっています。
DXを推進するうえで企業が抱えている課題
DX推進に向けて、企業は実際にどのような課題を抱えているのでしょうか。ここでは、多くの企業が直面する問題について解説します。
DXを推進する人材の不足
DXを推進するプロジェクトを担うDX人材の不足は、多くの企業にとって最重要課題です。
DXを推進するためには、デジタル領域に精通し、事業を率先して変革できるスキルを持った人材が求められます。具体的には、UXデザイナーやデータサイエンティスト、AIエンジニア、ITアーキテクトなどの多様な人的リソースを要しますが、これら領域を担う人材の絶対数が不足していることが国内企業共通の課題となっています。
また、DX人材の適切な評価を行うために、社内制度を見直すことも重要な課題です。
老朽化したシステムに人手を割かれてしまう
DX推進が進まないおもな要因の一つとして、「既存システムの老朽化」が挙げられます。経済産業省の「DXレポート」によれば、約8割の企業が老朽化したシステムを抱えているという結果が出ており、約7割の企業がそれをDXの足かせと感じていると回答していることが明らかになっています。
特に事業年数が長く、規模が大きな企業では、どうしても既存システムに依存する度合いが高くなってしまう傾向があります。そうした状況下で先端的な技術を学んだIT人材を確保できたとしても、老朽化したシステムの運用・保守にあてることになり、人的リソースを適切に活用できないといった結果になりがちです。
人材を効果的に活用できていない状況は離職につながりやすいため、DX人材の確保がますます困難になるというジレンマを抱える企業も少なくはありません。
経営層のコミットが得られず、全社的な取り組みが行えない
前述のとおり、DXは単なるIT化とは異なり、全社的な取り組みが求められます。デジタル技術を用いて新たな業務フローやビジネスモデルへの移行を図るためには、特定の業務や部門に限定して進めることはできないため、経営層のコミットや社内の共通理解にもとづいた各部署の連携や協力が必要不可欠です。
しかし、経営層の正しい理解が得られず、そもそもDXのスタート段階でつまずいてしまうといったケースも決して少なくありません。
DX推進に取り組んでいる企業の事例

ここまで見てきたように、DXは社内の根源的なビジネスモデルの変革を示す概念であり、とても幅広い分野や業務に関連するテーマです。それだけに、推進を進めた先のゴールが曖昧になりやすく、目的意識の共有が難しい面もあります。
DXを推進するうえでは、すてに積極的な取り組みを行っている企業の事例を参考にしてみるのもよいでしょう。ここでは、5つの企業のDX推進事例を紹介します。
阪急百貨店
阪急百貨店では、顧客の生活スタイルや購買行動の変化を踏まえ、実店舗とECサイトとともに「デジタルを用いた接点を増やしていく」という目的で「OMO(Online Merges with Offiline)」やDXの推進をスタートしました。
OMOとは、ネットとリアルデータの統合活用のことであり、DXとも大きく重なる部分のある概念です。
OMOとDX推進の取り組みとして、具体的には実店舗とECの顧客データ、売上データ、サイト訪問データを統合活用し、より顧客に寄り添ったサービスの提供を行うためにマーケティングオートメーションツール(MAツール)やデータ統合ツールの活用をスタートしました。そこで導入されたのが、データマーケティングツールの「b→dash」です。
b→dashは、データ集計・統合・分析・Web接客・レコメンド・SNSやメールの配信といった複数の機能をまとめて使えるオールインワン型のツールです。データのつなぎ込みが不要であり、外注していた作業も内製化できたことから、施策を担う土台として採用されました。
b→dashの活用により、特にステップメール(顧客ごとにシナリオを設定して段階的に送付するメール施策)の成果が大きく表れ、MA経由でのCV数は約4倍、店舗からオンラインストアへの送客率は約3.5倍に増加しました。
また、大容量のデータ統合によって分析が効率的になり、有効な施策を実行しやすくなっている点も変革によって得られた大きな財産です。
アシックス
競技用シューズやアパレル用品などを製造・販売する株式会社アシックスでは、2018年から全社を挙げてDXの推進に取り組んでいます。
具体的には、デジタルビジネスとデジタルマーケティングの第一歩として、「一般ランナーとの接点」を意識したカスタマージャーニーを設定しました。顧客がトレーニングからレース出場に挑んだり、リカバリーを経て再びレースにチャレンジしたりする経緯などを踏まえ、最適なタイミングで必要な製品やサービスを提供していくという流れです。そして、この一連の取り組みを支える仕組みとして、「ランニングエコシステム」を構築しました。
これは、同社の会員プログラムである「OneASICS」と、日々の走行距離を測定・記録できるアプリ「ASICS Runkeeper」、4,000以上のマラソン大会に参加登録が行えるデジタルプラットフォーム「Race Roster」、オーストラリアでシェアナンバーワンを誇るレース登録サービス「Register Now」の4つの柱によるサービスの輪のことです。日常的な健康維持から本格的な競技出場まで、ユーザーの多様な目的に対応し、最適なタイミングでフォローアップできる画期的な仕組みとなっています。
しかし、こうした取り組みのなかでは、DX推進時に起こりがちな課題にもぶつかりました。特に、OneASICSの取り組みについては、おもに実店舗部門から目的に対する疑問の声が上がったとされています。実店舗からすれば、「Webでの集客に売上が奪われてしまう」といった危機意識もあり、メリットを実感しづらい面があったのです。
そこで、店舗のKPIを整備したり、実店舗にもたらされる具体的なメリットを説明したりしながら、丁寧に理解を得ていくプロセスが必要となりました。
社内理解の形成にも力を入れながら取り組みを続けた結果、OneASICSの会員数は500万人、各種サービスの年間利用者は合計1,000万人以上と、「一般ランナーとの接点」を大幅に増やすことに成功しています。
フェリシモ
自社商品をはじめ、独自にセレクトした国内外の製品やサービスを取り扱う大手通信販売会社の株式会社フェリシモでは、DX推進の一環として「クラスター&トライブ戦略」を構築・実行しています。
クラスター&トライブ戦略とは、「ニッチではあるものの確実にファンである顧客」に寄り添うことで、より細分化されたマーケティング施策を実行することを目的とした戦略です。
同戦略のおもな特徴としては、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)「Rtoaster(アールトースター)」を使い、「ECコンテンツとメールDM」のパーソナライズに活用した点が挙げられます。ECサイトについては、商品データや顧客データ、購入ステータスなどを組み合わせ、おすすめ商品の差し込みやカタログ紹介に活かしています。
また、メールにおいてはRtoasterによる業務の内製化に成功し、制作費用を抑えつつ効率的な運用を実現させました。さらに、RPA「Brain Robo(ブレインロボ)」の導入により、部署を越えた連携などもスムーズに行えるようになり、結果として年間数千時間の業務時間を削減に成功しています。
大幅な効率化によって生まれた余剰リソースは、顧客に合わせたきめ細かなアプローチや、オンラインストアのリニューアルといったさまざまな業務に活かされています。
中外製薬
大手医薬品メーカーの中外製薬株式会社は、経済産業省と東京証券取引所が選定した「DX銘柄2020」にもラインアップされるなど、国内のDX推進をリードする企業の一つとして注目されています。
同社では社会を変えるヘルスケアソリューションの提供を目指す「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を発表し、DXを部門横断的に推進する「デジタル戦略推進部」を発足しました。
まずは職能を見極めたキャリア採用と、新たに立ち上げた人材育成プラン「Chugai Digital Academy」により、DXを推進する人材の足場作りに注力しました。
そのうえで、AIの活用によってさまざまな業務を効率化させたことで、特に創薬プロセスの大幅な改善に成功しています。具体的には、デジタル技術の活用によって可能性の高い化合物を初期段階で効率的に絞り込み、新薬開発の成功確率を高めるといった具合です。
また、7000日を要していた効果の評価プロセスをデジタル技術の活用により数時間にまで短縮した例もあります。
霧島酒造
大正5年の創業以来、「黒霧島」や「白霧島」といった本格焼酎を製造・販売する霧島酒造株式会社では、DXによる大きな飛躍を目標に掲げ、製販プロセスの変革を目指す「あじわいDX」、顧客体験の向上を目指す「くつろぎDX」、従業員体験の向上を目指す「ひとづくりDX」といったDXの3本柱を設定しました。
あじわいDXとは、原料であるさつまいもの調達、製造管理、物流、販売までのプロセスを見直し、効率的かつより高品質な製品提供が行える環境の構築を目指す領域です。
リソースを効率的に活用することで、本来持っていた発酵技術を活かし、甘酒やクラフトコーラといった新たな製品の販売にも成功しています。
くつろぎDXでは、顧客を卸店や小売店を対象としたBtoB領域と、実際に商品を購入するユーザーを対象としたBtoC領域に分け、それぞれに対してマーケティング施策を実践しました。
BtoB領域ではSFA(セールス・フォース・オートメーション/営業支援システム)の導入に取り組みながら、消費者の嗜好データにもとづいた販促活動と、卸売業や小売業との密な連携体制の構築に取り組んでいます。
また、BtoC領域については、CDPの導入によって、オンライン・オフラインのあらゆるチャネルの顧客データを統合し、より高度なデータ収集と分析を進めています。
SFAの導入により、特に大きな変化が表れたのは顧客とのつながりです。従来の体制では、キャンペーンを実施しても、応募者との接点はその1度限りであり、継続的な関係性は構築できていませんでした。
顧客データとしても、「過去に〇〇キャンペーンに応募した」という情報しか把握できていなかったため、その後の施策に活かすことができなかったのです。しかし、オートメーションツールの導入によって顧客ごとにきめ細かなアプローチが行えるようになり、強固な関係性を育てることに成功しています。
さらに、ひとづくりDXではAIソリューションやロボットによる作業の効率化を促進し、人にしかできない仕事に集中できるような環境設定に取り組んでいます。トップダウンとボトムアップの双方向によるコミュニケーションを推進力にして、現場社員の積極的な参加を促す工夫が凝らされている点が特徴です。
まとめ
DXは単なるIT化やデジタライゼーションとは異なり、デジタル技術の活用によって企業のビジネスモデルや風土、社会との関係性までを対象としたダイナミックな革新を指す用語です。経済産業省によって「2025年の崖」として警鐘が鳴らされたように、企業にとってDXは今後の成長を大きく左右する重要なテーマでもあります。
一方で、既存システムとのコンフリクトやDX人材の不足など、DXの推進においては多くの企業が共通して抱える課題も存在します。また、そもそもDXが持つ概念の幅広さから、社内で共通認識を構築したり、経営層と現場の足並みをそろえたりするのに苦労してしまうケースも少なくありません。
DXの推進に積極的に取り組む企業の事例も参考にしながら、自社が目指すべき方向性を探り、具体的な施策へと落とし込むことが大切です。