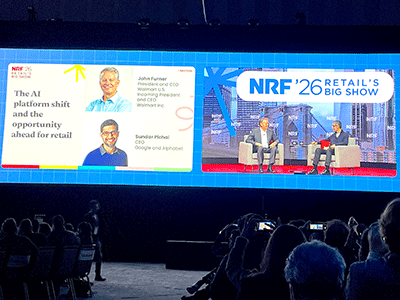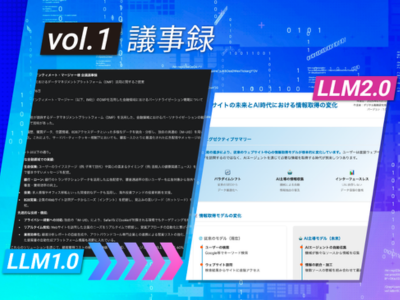今、注目されている「OMO」
デジタル技術が発展し、オンライン上の顧客接点が重要になった現代で注目されているのが「OMO」のマーケティング手法です。OMOを実施すれば、データを起点としたアプローチが可能になり、ユーザーごとにパーソナライズされた体験を届けられます。
今回の記事では、OMOの概要やメリット、事例を紹介します。自社で取り組みを検討されている方は、ぜひお役立てください。
OMO(Online Merges with Offline)とは何か?

OMOとは「Online Merges with Offline(オンライン マージズ ウィズ オフライン)」の略で「オンラインとオフラインの統合」を意味します。実店舗とデジタルをつなげるテクノロジーを活用し、ユーザーの利便性を高め、体験価値の最大化やデータ活用を図るマーケティング手法です。
オフラインとオンラインの区別
OMOでは、オンラインとオフラインは区別されていません。ユーザー視点で見れば、普段からオンラインとオフラインを行き来はしていますが、その境目は曖昧で、特別意識はしていないはずです。同じ企業のサービスを受けた場合、オンラインもオフラインも関係なく“単一の体験”として認識することでしょう。
そこに着目したのがOMOのマーケティング手法です。OMOはデジタルツールが発達し、ユーザーの日常生活でオンラインサービスが当たり前のものになった昨今においては、ユーザーの満足度を向上するために重要度の高い取り組みといえるでしょう。
OMOは中国で盛んに実施されている
OMOに先進国に取り組んでいる企業は中国であるといわれています。そもそもOMOという言葉を提唱したのは、中国ベンチャーキャピタルである「シノベーション・ベンチャーズ」の創業者、李 開復(リ・カイフ)氏です。同氏が提唱した新たなマーケティングの概念は、2017年12月に『ザ・エコノミスト』誌で発表され、認知が広まりました。
中国では店舗に設置されたQRコードを読み取って、ユーザーがスマートフォンで商品情報などをチェックできるシステムもあり、オンラインとオフラインの融合が進んでいます。
OMOとオムニチャネル・O2Oはどう違う?

OMOと混同されがちな概念として挙げられるのが「オムニチャネル」「O2O」です。ここからはOMOとオムニチャネル・O2Oの違いについて解説します。
OMOとオムニチャネルの違い
オムニチャネルとは、ECサイトやアプリ、SNSなど各チャネルを活用した包括的なアプローチを行うマーケティング手法 です。
OMOが顧客の「体験価値の向上」を図る施策であるのに対し、オムニチャネルの最終ゴールは「購買行動の促進」にあります。
OMOとO2Oの違い
O2Oとは「Online to Offline」の略で、ECサイトやアプリなどのオンライン上のサービスから、実店舗へユーザーを送客するマーケティング手法です。
具体例としては「ECサイトのアプリで、実店舗用のクーポンを配信する」などが挙げられます。 OMOは「オンラインとオフラインの境目をなくす」取り組みを実施するのに対して、O2Oは「オンラインとオフラインを区別したうえでの相互送客」を行うことが相違点です。
OMOをマーケティングに取り入れるメリット

企業がOMOに取り組むメリットとして、大きくは以下の2点が挙げられます。
- 購買データの収集ができる
- 機会損失の防止によりLTV(顧客生涯価値)もアップする
次項より、それぞれの概要を解説します。
購買データの収集ができる
OMOにおいて、オンラインとオフラインのデータを管理することは必須です。逆を言えば、様々なチャネルで取得したユーザーの購買・行動データを一元管理でき、ユーザーニーズをより正確に把握できるということです。これにより、ユーザーごとのニーズに応じたレコメンドやクーポンの配布などを行い、売り上げを最大化できます。
これまで実店舗でパーソナライズされた顧客体験を届けようとすると、販売スタッフがユーザーとの関係性を築く必要がありました。しかし、デジタルを活用したOMOなら、アナログな関係構築をせずとも実店舗において良質な顧客体験の提供が期待できます。
あらゆる市場でコモディティ化が進む現代では、企業は競争優位性を築きづらくなっています。OMOは、そのような状況下でオフラインでの提供価値を最大化させる、意義深い取り組みなのです。
機会損失の防止によりLTV(顧客生涯価値)もアップする
OMOを導入すれば、オンラインのみを活用する場合に比べ、より良質な顧客体験を届けられると考えられます。オンライン・オフラインが連携した接客を行えば、ユーザーの離脱リスクの低減にもつながるでしょう。
結果として、各ユーザーの「LTV(顧客生涯価値)」の最大化も図れます。良質な体験価値を届け、「どこで買っても同じ」ではなく「ここで買いたい」と思ってもらえるようになれば、そのユーザーは長期的に自社を利用してくれるでしょう。
OMOを活かしたマーケティング施策の例

OMOを使ったマーケティング施策の例を挙げると、次のような取り組みが代表的です。
- チャットボットによるユーザー対応
- モバイルオーダーによる遠隔注文・決済
- ポイントプログラムを用いたロイヤリティ向上
- デジタルサイネージを利用した広報活動
次項より個別に解説しますので、自社でOMOを実施する際の参考にしてください。
チャットボットによるユーザー対応
チャットボットとは、ECサイトやアプリなどの画面上にチャット欄を設け、ユーザーが質問を入力することで、ロボットが回答するシステム です。自社視点でみれば、ユーザーへの個別対応の手間を省けるほか、返答までのリードタイムも短縮できます。
さらに、チャットボットは初期こそ複雑な回答はできませんが、データを収集し学習することで、より複雑な質問や抽象度の高い問い合わせにも対応できるようになっていきます。
近年はOMOでの活用事例も増えており、実店舗でも導入されるようになりました。たとえば、ユーザーは専用アプリを実店舗で使い、チャットボット経由で在庫検索やおすすめ商品などの情報を知れます。店員が接客中のケースだけでなく、声をかけられることが苦手な顧客にとっても、快適なシステムといえるでしょう。
モバイルオーダーによる遠隔注文・決済
モバイルオーダーとは、スマートフォンの専用アプリ経由で事前注文・決済をしておくと、飲食店に来店した際には実店舗で商品を受け取れる形式のサービスです。日本では、スターバックスなどが代表的でしょう。
決済は注文時にキャッシュレスで行われるため、ユーザーにとっては簡便なシステムです。店舗側にとっても、レジ対応の手間を削減できるため、業務効率化につながります。
さらに、一般的にモバイルオーダーでは専用アプリを利用しますので、ユーザーに対して「割引クーポン」「新商品のセールス」を行うことで、再来店率の向上やアップセル・クロスセルに貢献します。
ポイントプログラムを用いたロイヤリティ向上
ポイントプログラムとは、店舗への来店・商品購入に応じたポイントが付与されるサービスです。以前からポイントカード形式で活用されていたマーケティング手法ですが、デジタル技術の登場により、使い勝手は大幅に向上しています。
ユーザーは付与されたポイント残高をスマートフォンで一括管理できるため「使い忘れ」の低減につながり、店舗としては有効期限がある場合はレコメンドすれば実店舗への再来訪を促せます。
運営視点でみれば、ポイントの付与・使用はシステム面で完結するため、スタッフ教育の手間を削減できる点がメリットでしょう。オンライン・オフラインのどちらでもポイントを利用可能にすることで、自社全体の売り上げをさらに促進する余地があります。
デジタルサイネージを利用した広報活動
デジタルサイネージとは、映像や音を自由に切り替えられる電子掲示板で、置き看板からビルの屋上に取り付ける大型サイズまで、さまざまな大きさのものがあります。通常のポスターや看板に比べると一度に流せる情報量が多く、動画プラットフォームのような使い方が可能です。
近年では、AIカメラがユーザーの年齢・性別を判別して、表示内容を切り替えるというテクノロジーも登場しています。さらに、デジタルサイネージでおすすめ商品を紹介したのち、QRコードを表示することでWebサイトに送客するといったアプローチも可能です。
ただし、アナログ媒体の看板であるため費用対効果を測定しづらく、自社設置のデジタルサイネージでない限り、場所が限られ他社の広告との切り替わり制になることが懸念点です。
OMOを取り入れたマーケティングの成功ポイント

OMOを取り入れたマーケティング施策は有意義なものですが、成功のためには次のようなポイントを意識する必要があります。
- マルチチャネルで幅広い接点構築を行う
- 自社でデータ活用の運用体制を構築する
- ノウハウのある人材のアサイン
それぞれについて、具体的に解説します。
マルチチャネルで幅広い接点構築を行う
オンライン・実店舗における顧客体験の融合を図るOMOを成功させるためには、ユーザーとのタッチポイントを幅広いマルチチャネルで設計する必要があります。
デジタル技術の発展により、企業とユーザーとの接点は多岐に渡るようになりました。近年は、「実店舗では商品を確認するだけで購入はECサイト」「商品の細かな疑問まで、スタッフに直接確認したい」のように、ユーザー側のニーズも多様化しています。
こうした細かなニーズを拾っていけるように、OMOでは実店舗やECサイトだけでなく、SNSやLINE公式など、幅広いチャネルによる接点構築が推奨されるのです。結果的に、さまざまなニーズを持ったユーザーのデータを収集分析にもつながりますので、自社サービスのブラッシュアップにも貢献するでしょう。
自社でデータ活用の運用体制を構築する
OMOでのユーザー接点は多岐にわたり、日々さまざまなデータが蓄積されるにつれ、適切なデータの運用の体制構築も求められます。そのためOMOを成功させるためには、各チャネルで収集したデータを一元管理するデータベースシステムなどのシステムも必要になります。
さらに一元管理化したデータをもとに、ユーザーへのアプローチを効率化するため、CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)などのツールの活用も推奨されます。
ノウハウのある人材のアサイン
OMOの取り組みを自社で推進させ、成功に導くためには、さまざまな販売チャネル事情に精通した人材が求められます。実店舗における営業ノウハウに加え、ECサイト・アプリ経由での売り上げを最大化するために必要な知見を備えた担当者です。
OMOでは「オンライン⇆オフライン」の相互送客も行うことになりますので、各チャネルで発生する課題やユーザーニーズについて、データを基に粒度の高い分析をできる能力が求められるのです。さらには、部門間をまたいだ連携も必要になるため、社内調整・交渉に長けた人物がOMO施策を統括するのが望ましいでしょう。
OMOへの取り組みの成功事例

ここからは、実際にOMOに取り組んでいる企業例を紹介します。国内外の例をピックアップしましたので、各事例についてみていきましょう。
【日本】西武・そごう
百貨店事業を展開する西武・そごう渋谷店は、2021年9月に衣類・雑貨などを販売するOMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA(チューズベース シブヤ)」をオープンしました。ストアでは、ユーザーは店内用のWebカタログを見れば商品情報がわかるようになっており、スマートフォンを使った商品購入も可能です。
店舗と同時に立ち上げられたECサイトは、一部を除き実店舗と在庫状況が連動しているため、ECで購入した商品をそのまま店舗で受け取る「BOPIS(Buy Online Pick-up In Store)」サービスにもつながっています。
店舗スタッフの接客を受けなくても実店舗にいながらオンラインで商品詳細を検討できる同社の事例は、OMOの取り組みとしては学ぶべき点があるといえるでしょう。
【アメリカ】Amazon GO
ECモール型のマーケットプレイスとして世界最大手のAmazonも、OMOへの取り組を行なっており、その代表例が米国シアトルでスタートした「Amazon GO」です。
Amazon GOは、Amazonが世界ではじめて立ち上げた実店舗であり、無人レジが導入された「ウォークスルー型」の採用が当時話題になりました。Amazon GOでは、通常の実店舗で発生する商品の会計作業が一切不要で、ユーザーは棚から商品を取った後、出入り口のゲートを通過するだけで決済が完了する仕組みです。
Amazon GOがこのような決済方式をとっているのは、何も人件費削減のためだけではありません。ウォークスルー型会計を行うためにはAmzon GOの専用アプリが必要なのですが、このアプリ経由でAmazon側はユーザーの実店舗における購買・行動データを収集し、サービス改善に役立てられるのです。
日本でも、ユニクロや無印良品が専用アプリによる決済を採り入れていることを踏まえると、今後各社でAmzon GOのようなOMOの取り組みが加速するかもしれません。
【中国】Tencent(テンセント)
中国IT系企業のTencentは、同国で利用頻度の高いコミュニケーションアプリ「WeChat」を活用したOMO施策を展開しています。
2017年にWeChatは「ミニプログラム(小程序:シャオチェンシュ)」をスタートしました。これはWeChat内のミニアプリで、複数のアプリを端末にダウンロードする必要がないという点がポイントです。たとえばこの機能を使って駅でQRコードを読み込めば、新たなアプリは不要で各線の発着時刻を調べられます。
移動など様々な日常生活(オフライン)における手間暇を、オンライン経由で削減できるOMOの取り組みといえます。
まとめ
オンラインとオフラインをつなぐOMOのマーケティング手法は、ユーザーのニーズが多様化し、市場もコモディティ化している現代においては、取り組む意義のある施策といえます。OMOの企画・実行・舵取りは、複雑かつ煩雑であるものの、ユーザーの体験価値を最大化できれば、今後も自社を存続させるだけの競争優位性を築けます。
デジタルに関する知見がない場合は外部専門家の意見も取り入れつつ、包括的な施策を実行しましょう。