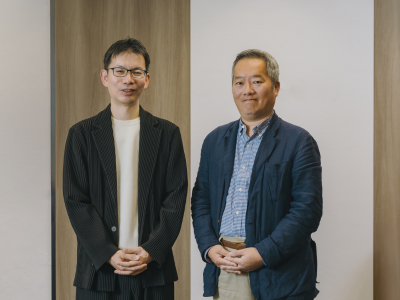「ビール回帰」の流れを受けて新ブランドを開発
はじめに、玉手氏は最近のビール市場の変化に触れた。
「若年層のビール離れ」などによって縮小を続けていたビール市場だが、最近では市場を取り巻く環境が変化し、「ビール回帰」の流れが加速している。
変化の中でも大きかったのは、2020年に行われた酒税の改正だ。ビールの酒税が下がり、『第3のビール』と呼ばれる新ジャンルの酒税が上がり、ビール市場が拡大した。「ビールが減税になってから、多くのお客様がビールカテゴリーを飲用するようになった」と玉手氏が話すように、その影響は大きなものだった。

そして、2023年10月には2回目の酒税改正が行われ、新ジャンルが増税により発泡酒と税額が統一された。さらに2026年には、ビール類酒税が一本化されるため、これによりビールへの注目が一層高まることが期待されている。
この変化をチャンスととらえたアサヒビールが新たに開発したブランドが「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」(以下、ドライクリスタル)だった。
なぜ3.5%のビール?4つの開発背景
玉手氏は、ドライクリスタルが生まれた背景には次の4点があったと説明した。
1.お客様を取り巻く環境の変化
2. グローバル市場のトレンド
3. 日本における度数別構成比
4. 国内のお客様の声
1.お客様を取り巻く環境の変化
1つ目は「お客様を取り巻く環境の変化」。人生100年時代と言われる現代において、勉強して良い学校に通って就職し、60歳を超えたあたりで定年を迎えるといった「教育⇒仕事⇒引退」と画一的な人生ではなく、ロールモデルのない非常に多様な人生が歩める状況になっている。
玉手氏は「お客様の人生が大きく変化しているのに、ビールとお客様との関係性がずっと同じとは考えにくい」という気づきからドライクリスタルの開発をスタートしたという。
2.グローバル市場のトレンド
2つ目の「グローバル市場のトレンド」は、日本のみならず、世界各国で緩やかにアルコール消費低下の傾向が見られている。その一方で、アルコール度数0~3.5%の販売容量が2022年に過去最高値を記録し、需要を伸ばしていた。
3.5%前後の度数の商品を、アサヒビールは「ミドルレンジアルコール帯」と位置付けて需要が高まっている背景を探った。その結果、ミドルレンジが海外市場で台頭しつつある理由として、3つのトレンドが挙がってきた。
【ミドルレンジアルコールをめぐるトレンド】
・「スマートな消費行動」:酔うためだけにお酒を飲むのではなく、日々の充実のために飲むといった賢い飲酒習慣を指す。
・「選択肢の拡充」:顧客自身が、シーンや気分によって飲むものを使い分けられるよう、アルコール度数や味を含め選択肢を増やす動きが増えている。
・「新しいライフスタイル」:無理のないビールライフを送る人が増えている。各国のミドルレンジアルコール商品を見ると、いずれもスマートで暮らしに馴染むデザインを採用している。
3.日本における度数別構成比
こうしたグローバルのトレンドに対して日本の現状をあらわしたのが、商品開発の背景3つ目の「日本における度数別構成比」。世界ではミドルレンジ商品が増えているのに対し、国内市場では4~6%の度数帯が97.8%で、ほとんどを占めていると指摘。中でもアルコール度数5%台の主力のレギュラービールが約7割と大きな構成を取っていて、3%台に関しては1.7%と雀の涙ほどしかない。
「お客様が『今日はアルコール度数が低いものを飲みたい』と思っても、そもそも手に取れる選択肢がありませんでした。これはビールメーカーとして反省するポイントですが、ミドルレンジ商品に可能性があるのではとも考えました」(玉手氏)
4.国内のお客様の声
その仮定の裏付けになったのが、開発背景の4つ目となる「国内のお客様の声」だった。
実際にミドルレンジ商品を販売したときに受け入れられるのかを探るため、プロトタイプを作成し多くのお客様の声を調査したところ、「体への負担が軽くなりそう」「長い時間、心地よく楽しく飲めそう」「翌日のことを考えずに飲めそう」といった良い反応が沢山得られたのだ。