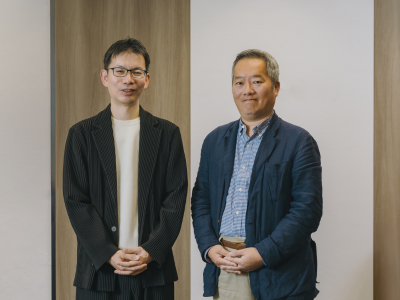DevSecOpsを日本に浸透させるために
GitLabはFortune 100の50%の企業が導入し、全世界で3,000万人以上に利用される「DevSecOpsプラットフォーム」を提供するソフトウェア企業だ。同社のサービスを利用することで、ソフトウェア開発ライフサイクルにおけるプロセスの可視化や改善、情報やデータの一元管理が可能となり、開発効率化だけでなく、セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス強化、ディベロッパーエクスペリエンスの向上が期待できる。

「北米に比べると、日本の開発環境は6年ほど遅れていると言われています。『DX白書2023』(IPA:独立行政法人情報処理推進機構)によると、開発手法としてDevSecOpsを『全社的に活用している、事業部で活用している』と回答した企業は日本では9.1%、米国の52.9%と比べると大きな開きがあります。日本ではGitLabの訴求はもちろん、DevOpsやそれを進化させたDevSecOpsという概念の浸透もこれからです」
そう語るのは、日本におけるフィールドマーケティング全般を担う川口氏だ。

GitLabでは、顧客のステージを認知・検討・購買・拡大に分け、各段階でのマーケティングの目的を下記のように設定している。
- 認知:マーケットアウェアネスの獲得
- 検討:ソートリーダーシップの獲得
- 購買、拡大:パイプラインの創出
全社戦略として認知~検討は基本的に米国本社のチームが行なう。川口氏は購買・拡大のフェーズを司るフィールドマーケティング部門に属し、日本におけるデマンドジェネレーションの仕組み作りや、営業に対するパイプライン供給の勝ち筋の模索を続けている。
主なターゲットは、IT関連部門ないしビジネス関連部門のミドルマネジメント以上。DevSecOpsへのニーズが顕在化されているケースは非常に少ないため、どの部門のどの役職の方が導入のキーパーソンになるかがわからない。従って現状では広めにターゲットを設定しているという。
イベントの役割は自社/他社、オン/オフで切り分ける
2020年にGitLabへジョインした川口氏がまず行ったことは、オウンドイベントのパフォーマンス改善だ。BOFU (Bottom of Funnel)のパフォーマンス改善を先に着手することで、TOFU(Top of the Funnel、ここでは協賛するサードパーティイベント)から流入する大量リードのパイプライン化率を向上させることが狙いだ。
コロナ禍中だったこともあり、基本的にイベントはオンラインに限られたが小規模のウェビナー、オンラインワークショップ、大規模配信イベントの改善に取り組んできた。結果が見えてきたところで、サードパーティイベントの最適化に着手した。
川口氏はオウンドイベントの主目的をパイプライン創出、サードパーティイベントの目的を新規リード獲得とし、それぞれ使い分けているという。
「サードパーティイベントについてはCPL(Cost Per Leads)、ターゲット含有率、パイプライン化率などの指標をイベントごとに計測しながら、最適化に取り組んでいます。私の職責上そうしたデマンドジェネレーション関連の指標に着目せざるを得ないのですが、一定の認知向上も期待しています」(川口氏)
さらに、リアルイベントへの回帰も見られる中で、オフラインとオンラインの役割の違いも明確に意識していると川口氏は言う。
「オフラインイベントの強みは、直接お会いできること、ある程度長いお時間を確保いただけること、導入に対するモチベーションを醸成しやすいことにあります。第三者同士のつながりが生まれるのもメリットと言えます。一方のオンラインイベントの強みは、参加のハードルが低く、参加人数の制限もないため多くの対象に情報提供できることにあります。またデータ化しやすく、比較的少ない工数・コストで実現できます。どちらが効果的といった画一的な話ではなく、イベントの目的やお伝えしたい情報によって使いわけることが重要だと思います」(川口氏)

EnterpriseZine Dayは意欲的なオーディエンスにアプローチできる場
このようなマーケティングの一環として、GitLabはサードパーティかつオンラインイベントである「EnterpriseZine Day 2023 Summer」に協賛。登壇を通して、成果を得ているという。
「GitLabが定めるターゲットの含有率が、通常のサードパーティイベントでは40%前後が平均のところ、EnterpriseZine Day 2023 Summerでは60%を超えました」(川口氏)
また、リード獲得を目的としていたものの、一部パイプラインも生まれているという。加えて登壇内容を記事化するオプションにより、自社の考えを営業先などでシェアできるようにもなった。
EnterpriseZine Dayとは、26万人以上の会員数を抱える専門領域特化型のエンタープライズ向け会員制Webメディア「EnterpriseZine」が2014年より開催しているオンライン形式のイベントだ。

川口氏が同イベントへの協賛を決めた理由は、大企業という明確なターゲット層かつ、情報を集めることに積極的なオーディエンスが集まるという理由からだったという。
「GitLabにおいて大企業と中小企業では導入のアプローチが大きく異なります。つまりオーディエンスの企業規模によって、求める情報が大きく変わるのです。EnterpriseZine Dayは『大企業向け』と明言しているイベントなので、より大企業向けのコンテンツを作成しました。明確なイベントテーマも相まってオーディエンスの期待値を想定しやすいイベントだと感じました」(川口氏)
また、イベント来場者の情報収集意欲の高さも重要だ。そうしたイベントにおいては参加者が求める情報を想定し、協賛者側がそれに寄り添うことが、イベントを活用した案件創出の近道だと川口氏は語る。
「私は前職から翔泳社さんと10年近くお付き合いしていますが、広告主におもねることなく、きちんとした見解を持てメディアを運営していると感じます。イベントに関してもメディアが設定したテーマに賛同する企業が協賛し、それに沿った情報を提供するようコンテンツレビューを徹底されています。それが支持され、情報収集意欲の高い方の参加につながっているのだとと感じます」(川口氏)
登壇を決めるより前に翔泳社が運営する複数のメディアで自社イベントの告知を実施。EnterpriseZine経由のユーザー層とGitLabが定めたターゲット像との親和性の高さを確認できていた点も大きかったという。
堅実な情報提供で日本での認知・導入を広げていく
川口氏に今後の展望を尋ねると、「まずは基本的なBtoBのマーケティングの施策を実施します」と考えを示す。
「情報収集の主導権は既にお客様が持っています。我々マーケターは『お客様の意思決定をサポートする』くらいの謙虚かつ誠実な姿勢であるべきだと思います。そのためには、今回のEnterprise ZineDayでも実践したように、我々がお伝えしたい情報だけではなく、お客様が知りたい情報をしっかり定義し、その2つの中間を模索し続けてくことが重要だと思います。またお客様の情報収集チャネルは年々増加・多様化しており、そこに寄り添っていくことも重要だと思います。あらゆるチャネルでの情報提供を手堅く実現していくことで、各チャネルのデータを手に入れ、データを基にコストやリソースの最適配分を導き出し、改善を続け成長していきたいと思います」(川口氏)
EnterpriseZineもチャネルの一角として、GitLabおよびDevOps/DevSecOpsの情報提供を続けていく。
EnterpriseZine(エンタープライズジン)について詳しく知る
川口氏も活用するEnterpriseZineの読者層や広告メニューをまとめた資料のご請求、お問い合わせは広告掲載お問い合わせフォームよりご連絡ください。
★翔泳社の他の媒体について知りたい方は、広告掲載ご案内ページをご覧ください。