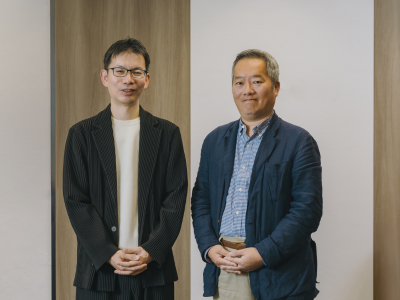会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 今どきシニアの消費行動大解剖連載記事一覧
-
- 年間支出11万円超、平均推し歴14年!「シニア市場」の解像度を上げる“推し活”のインサイト
- 終活にかかる総額は平均約503万円!シニア世代の嗜み「終活」市場の可能性を読み解く
- シニア女性に響くアプローチとは?「メディア三層構造」と「実用→感情→習慣」の視聴サイクルが...
- この記事の著者
-

梅津 順江(ウメヅ ユキエ)
ハルメク 生きかた上手研究所 所長
2016年3月から現職。主に年間約900人のシニアを対象にインタビューや取材、ワークショップを行い、誌面づくり・商品開発・広告制作の糧になるインサイトをつかんでいる。時代や世代も捉えて、半歩先の未来も予測している。著書に「消費の主役は60代 シニア市場最前線」(同文舘出版)な...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア