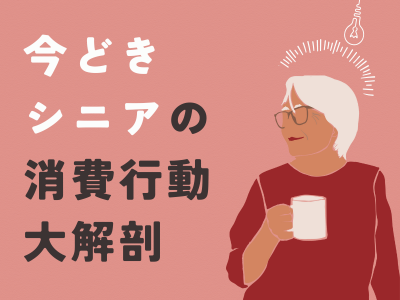ANA、現場からのボトムアップでDMP導入へ
安成:では、それぞれのDMP活用の進捗状況と導入の目的について、うかがっていきたいと思います。
西村:ANAでは、施策に迷ったときに立ち返るポイントとして社内で共有しているのが、「Right Person・Right Time・Right Channel・Right Contents」というワードです。適切な人に対して、良いタイミングで、良い媒体を使って、正しい情報を提供しましょうということですね。
安成:これはマーケティング施策に限らず、現場でも浸透しているのでしょうか。
西村:そうですね。空港のカウンターでグランドスタッフがお客様にニコッとお話しながら、ストレスなくお客様の座席を決めてチケットをお渡しする。空港で行われているこの当たり前のサービスを全ての顧客接点で実現したいというのが、ANAのシンプルな考え方です。

安成:社内で軸が共有されているというのが大切なんですね。
西村:はい。DMPを導入する前は、どうしてもチャネルごとのマーケティングに偏っていたんですよね。データを統合するのも大変でしたし。でも、よくよく見ると、複数のチャネルに渡ってタッチしている一人のお客様の姿が浮かび上がってきた。どのチャネルからお客様がタッチしてきても、ちゃんとお客様に寄り添ったマーケティングをしないといけないと気がついたんです。テクノロジーの進化に伴い、それを実現する外部環境が整ってきたタイミングで、チャネルごとの縦のマーケティングから、お客様ごとの横のマーケティングへシフトしていきたいと思い、DMPを導入する取り組みを進めていきました。

安成:ちなみにDMP導入に向けて動き出したのは、いつ頃のことですか?
西村:去年の前半かな。
安成:検討期間から導入までは、どれくらいの期間がかかりましたか?また様々なベンダーがDMPを提供していますが、どのように検討されたのでしょうか。
西村:導入が決まったのは去年の秋くらいなので、半年くらいはかかりましたね。安くない買い物なので、製品比較もしました。ただ弊社はデータ解析において2007年からAdobe社の製品を使っており、すでに導入している他のマーケティングツールとの連携がしやすかったこともあり、Adobe社のDMPを採用しました。ANAの場合、広告よりもオウンドメディアの強化を一番に考えていたので、これが一番フィットしているのではないかと判断しました。
安成:DMPの導入には、情報システム部をはじめとした様々な部署の協力が必要になってくると思いますが、社内をどのように説得されたのでしょうか。
西村:“今までできなかった不可能が、可能になるんです”と。DMPを導入して、データを蓄積・活用することで、具体的にどんなことができるようになるのかをブレイクダウンして、定量化・定性化していきました。当時向き合っていた課題を挙げてみると、DMPを活用することで解決できることがわかったので、「DMPを入れることでお客様もHAPPYになるし、会社的にも増収が見込めてHAPPYだし、我々現場もやりたいことが実現できて作業も楽になってHAPPYになる。三方良しでしょ」と説明しましたね。
安成:DMPを導入することによる増収見込みの数字はどうやって出されたのですか?
西村:既存施策の実績を参考値として、すでにDMPを導入して運用している海外企業を実際に訪問し、担当者に教えを請いながら、数字を組み立てていきました。
安成:マーケティング部門でシステムの導入をする際は、情報システム部門との軋轢がしばしば議論にあがりますが、特に反発などはなかったのでしょうか。
西村:実現したいことをしっかり丁寧に説明すれば、理解してもらえましたね。他部署の理解を得る際に、うやむやにして進めてしまうと、後々いろんな障壁が出てくるので、時には後戻りしながら、丁寧に、丁寧に、と心がけて話を進めていったので、さほど大きなハードルはありませんでした。