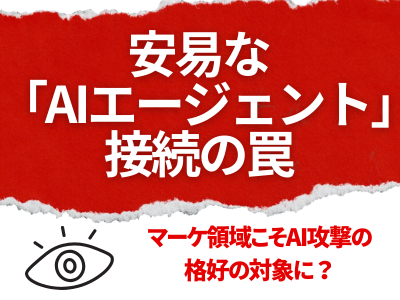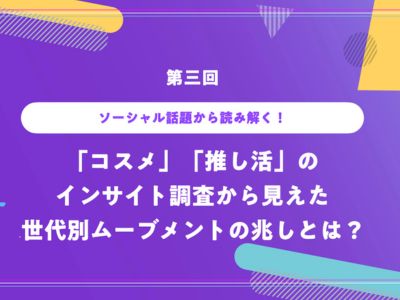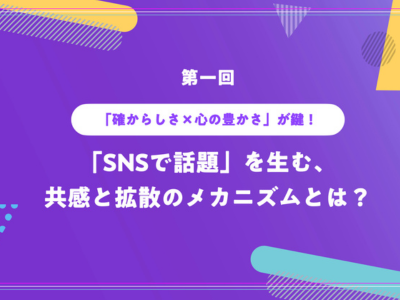データを読み解く分析者側の感覚の磨き方
古川:「ビッグデータ」には、調査範囲があまりにも広すぎるという課題があります。本の中で「マーケッターとしての嗅覚」というフレーズがありましたが、広大なビッグデータから最適なデータをいかに見つけるか、というのは、ある意味で職人技ですよね。
酒井:おっしゃる通りですね。どこに目をつけるのかはまさに職人技であり、実に泥臭い部分だったりします。ビッグデータがあまりにも多様であるからこそ、ある種の大喜利というか、分析者のセンスやアイデアが問われるという。
古川:その意味でも、本に書いてある「生活者に寄り添う」という考え方は大事ですよね。データからは様々な仮説を導き出すことができますが、毎日の生活を起点に発想の幅を広げていくとおもしろい話がどんどん出てくる気がします。
上原:2つタイプがあると思います。1つは、幅広い視点を持って自分たちを相対化するデータの使い方。もう1つは、自分たちの商品やブランドのファンと向き合うための使い方です。「ファン」という存在は知れば知るほど特徴があるはずですし、その特徴を認識するためには、自社以外の商品やサービス、ブランドを使っている人のことも知る必要があります。
言い換えれば、視点を広げる使い方と、どこまでも深く掘っていく使い方です。こういった点を意識せずに「ビッグデータ」と一言で括ってしまうと、どう使っていいかわからない、という事態が起きてしまいます。今、自分がどちらの目的のためにデータに触れているのかを意識しながら使うことが大事なのかなと思います。
データを分析する目的が問われている
酒井:「内海データ、外海データ」といった言い方をするのですが、自分たちが保有している膨大な顧客情報や、自分たちのサイト内にあるログデータも立派なビッグデータです。その“内海”のデータから既存ユーザーの属性をさらに深めて分析するのか。それとも“外海”にいる別の人たちを分析し、自分たちのユーザーとの違いを見つけるのか。
最近、私が取り組んでいることの1つに「ないのに検索」という考え方があります。たとえば、あるインテリア小売企業の検索データを調べると、その企業では取り扱いのない「電気毛布」というワードが異様に検索されていることがわかりました。
上原:消費者が期待しているからそのキーワードで検索しているのに、実際にはないと。その企業にとっては機会損失になっているわけですね。
これまで「データをどう分析するのか」というのは、統計の専門家やデータサイエンティストの独占的な仕事領域でした。しかし、データ分析がこれだけ大衆化してユーザーインターフェイスも整ってくると、「何を得るためにやっているのか?」「なんのために調べているのか?」という目的意識が問われるようになる。いわば、データの切り口ですよね。その意味で「ないのに検索」はすごくおもしろい切り口ですね。
基準を持ちながら違和感を探る
酒井:上原先生が普段指導される際、または論文を作る際には、どういうところから着想を得るのでしょうか?
上原:私はミーハーなところがあるので、いろいろな分野を見るのが好きなんです。そうすると、普段から「あの業種だけちょっと違うぞ」といった気づきを得られやすいのが1つ。あとは、「普通ならこういう数値になるはず」という基準を持ちながら世の中を見渡してみたときに「あれ、ここが違うぞ。じゃあ調べてみよう」と。
このことは学生への指導にも当てはまります。いざ卒論を書こうとしても、学生はどの業種のことも詳しく知りません。彼らが知っているのは大学で勉強した教科書的な理解だけ。でも、世の中は教科書から外れることがたくさん起きているので、何をテーマにすべきか、それを探すところから始まる状況です。
酒井:学生からするとかなり難しいお題ですね。どのようにアドバイスされていますか?
上原:たとえば、彼らが「韓国コンテンツの研究をしたい」となったとき、「今の韓国のブームだけではなく、過去の第一次・第二次の流行が起きたときの違いを調べてみましょう」と伝えます。今の学生にとって、韓国のコンテンツが他分野で市民権を得ているのは物心付いたときから変わらない、とても自然なこと。でも、かつては韓流といえば中高年女性がテレビで見るドラマのことでした。この違いは何が原因なのか、どんな変化があったのか、学生はあれこれ調べていますね。