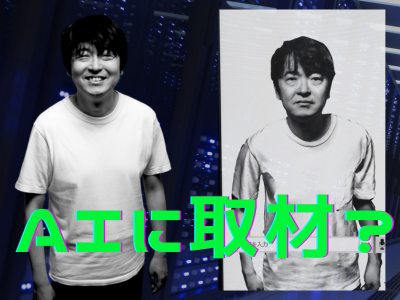キャンペーン応募が急増、その理由とは?
2021年1月、アサヒビールのキャンペーンが話題となった。
アサヒビールの対象商品についているシリアルコードを6個ためて応募すると、抽選で白石麻衣さん・西野七瀬さんのWebCM撮影イベントの現場に招待されるなど、複数のコースが用意されたプレゼントキャンペーンだ。
アサヒビールがこの応募チャネルに採用したのが、LINEだ。同社マーケティング本部の玉手健志氏は、「このキャンペーンは、昨年まではハガキで行っていたのですが、今年からLINEで応募形式に切り替えました」と説明する。

玉手氏は、ハガキを古くからある王道の手段と認めつつも、現在のアクティブな利用という観点でいえば、LINEに軍配が上がるという見方を示す。今回、応募数が従来に比べ数倍に増えた背景には、LINEのアクティブなユーザー数も関係していると玉手氏は語る。
実際、LINEが提供するキャンペーンプラットフォームについての調査(LINE調べ、2021年4月実施、n=1,054、15~59歳)では、「普段参加するキャンペーン形式」にLINEを選んだユーザーの割合は59.5%と群を抜いて高い。「ハガキ」は24.7%、「Webサイト」は17.2%、他SNSでも26.3%なので、LINEはキャンペーン応募のチャネルとして圧倒的に支持されているわけだ。
「LINEで応募」は、ユーザー・企業双方にとって大きなメリットがあるとLINE OMO販促事業推進室の江田達哉氏は説明する。
「LINEで応募できるので、キャンペーン参加のために専用アプリをダウンロードする手間がなく、また従来のWEBキャンペーンのようにIDやパスワード入力を新たに設定することも不要です。ユーザーは、商品に貼付してあるシールのQRコードをLINEで読み込むだけで参加できますし、企業側はLINEを通じて購買者を把握し、1to1のメッセージを送ることができます」(江田氏)

この点について玉手氏も、「当社のようなBtoBtoC事業で、実際のお客様について把握できるという点は非常に大きいです」と同意する。
今が「LINEを活用した販促構想」の実行フェーズ
アサヒビールの公式LINEアカウント開設は、他の飲料メーカーに比べむしろ後発組であったと玉手氏は語る。だが、導入後はLINE活用の幅が急速に広がっている。
同社の場合、LINE公式アカウントを開設したのは2017年2月だったが、同年8月には酒類としては初となるコンビニでのLINE サンプリング(※現在は提供中止)を実施。また、2018年にはハガキと併用した種々の応募キャンペーンを開始し、その後もビーコンによる位置情報を活用した販促施策の実施。2020年にはアサヒビール社初となるLINEプロモーションスタンプの配布などを進めてきた。
「当社ではLINE導入前から『LINEで何をしていくのか』について議論を重ねてきました」と玉手氏。そのため、サンプリングやキャンペーンで手応えを得ると、2018年には早々に「デジタルマーケティングの中心にLINEのユーザーIDを置く」と判断したという。
そこで、あらゆる接点にLINEの入り口を作りユーザー行動をログ化することに着手した。たとえばキャンペーンの一部を「LINEで応募」に切り替えることで、普段は見えにくい購買者の情報や行動を把握・分析してきた。2020年以降は、取り組みも高度化・立体化してきており、LINEのセグメント配信にAIを活用するなどしている。
「こうして、当社の最大ブランドである『アサヒスーパードライ』のキャンペーンをLINEで展開することにも着手しました」(玉手氏)
玉手氏によると、「デジタルマーケティングの中心にLINEのユーザーIDを置く」という戦略には2つの理由がある。1つは、自社会員IDやその他のプラットフォームのIDに比べ、圧倒的に規模が大きい点。もう1つは、IDの堅牢性だ。無制限に登録できるIDではなく、1つの携帯端末に1つのIDが付与されるため個別に丁寧なコミュニケーションができる点がLINEのユーザーIDの特長だという。
デジタル販促の幅も広い。店外にいるユーザーに対しては、LINE広告やLINE公式アカウント、またはLINEチラシなどを通じて商品を告知し、店内に入ってきたユーザーにはLINE POP Media(トライアル)で、購買直前のユーザーに商品やキャンペーンを訴求する。そして購買を後押しする手段として「LINEで応募」を展開し、購買後にはLINE公式アカウントで再購買を促す。

その一連のプロセスを、LINEのユーザーIDに集約することで、より高度なコミュニケーションが実現する。
こうしたLINEのデジタル販促構想について、LINEの江田氏は玉手氏と長年話し合ってきたという。「ようやく実現でき、アサヒビールさんの戦略とも合致しており、非常にうれしく思います」(江田氏)
施策を描くから実行に移すための「ABC」とは
複数のチャネルを通じて集まるさまざまな情報を1つのユーザーIDに集約し、コミュニケーションの質を上げてマーケティングに生かす——パートナー企業との打ち合わせや資料などでよく見られる概念ではあるが、それを実際に推進している企業は、現状ではほとんどないといえるだろう。
この構想を進めていくに当たり重要だった、次の3つのポイントを玉手氏は挙げる。
第1に「抽象論ではなく本当にやる」ということ。第2に「ありたき姿を定義して山頂を目指す」こと。第3に「当たり前のことを馬鹿にせずに、ちゃんとやる」ということだ。この「当たり前(Atarimae)のことを馬鹿にせずに(Baka)、ちゃんとやる(Chanto)」を同社では昔から「ABC」と呼んでおり、この姿勢がLINEの活用術に表れているという。
1つの施策を実行することは容易ではない。たとえば、商品にQRコードのシールを貼付するコストはどれくらいなのか、コンビニの協力が必要な場合、誰がどうやって何を交渉するのか、LINE Beaconを使った位置情報マーケティングを行う際、誰がLINE Beaconを設置するのか。デジタルマーケティング部隊が頭で考えたことを「本当に」実行するには、実はさまざまなハードルがある。
そのハードルを乗り越えるには、「山頂」つまり目指すべき姿を社内で共有し、部門を超えて協力し合うことが肝要だ。玉手氏は「部署が異なっても、ベクトルは同じ方向に向けるはずです。明確なビジョンを伝えれば合意は得られます」と語る。
そのうえで情報を日々蓄積し、その情報をもとに顧客と最適なコミュニケーションを取るという。当たり前なことを、愚直なまでにやっていくのが、アサヒビールが考えるLINE活用のポイントだという。
キャンペーンは開始1日目からPDCAが回り始める
では、冒頭で紹介した2021年1月から5月下旬まで実施された「LINEで応募」キャンペーンを受けて、どのようなインサイトが蓄積されてきたのだろうか。
ハガキでの応募からLINEに切り替えたことで、キャンペーン開始後1日目からレポーティングを実施。キャンペーン前に立てていた仮説と、応募者から寄せられた属性データや、応募状況などを付き合わせ、その結果をブランド担当者と共有していったという。
「これまでは応募ハガキが到着しきってからしか集計できなかったのですが、LINEは1日目からデータをもとに仮説検証ができたので、細かい調整を重ねてキャンペーンを盛り上げていきました」(玉手氏)
このキャンペーンでは、応募者の詳細を把握したいという目的から、応募にあたり性別や年代等のアンケート回答を取ることにしていた。この回答を、社内のカスタマーデータプラットフォーム(以下、CDP)に蓄積し、閲覧・分析を進めていった。
その結果から展開したコミュニケーションは、玉手氏が繰り返し語るように「愚直なまでにストレート」なものだった。
たとえば応募がスパイクする日を見ると、「土日」もしくは「配信が行われた後」ということが判明。これにより、金曜日もしくは土曜日の朝にキャンペーンについて告知をすると、それに応じて応募数が跳ね上がることがわかった。
また、応募者のなかでも層が厚いと想定されるタレントのファンに向け、応募最終日直前に「締め切り告知」をプッシュ配信することで、ファンの応募を促すといった取り組みも実施。
「小さなことですが、こうしたコミュニケーションは、大々的な広告を1つ打つよりもずっと効果的です」と玉手氏は話す。
クリエイティブの差し替えも積極的に行われた。蓄積されたインサイトを見ると、CM撮影の参加に応募した層と、タンブラーに応募した層は、ほとんど別のペルソナのユーザー群であることが早いうちにわかったので、それぞれの層に合ったクリエイティブの出し分けを行ったという。
「お客様に不要な情報、興味のない情報を配信するのではなく、より好ましい情報を提供することがこれからの時代は求められると考えており、クリエイティブ変更を柔軟に行うことも必要だと思います」(玉手氏)
マーケターがセグメントを切る時代ではない? AIの活用がカギ
LINEの江田氏は「この話を聞くと、販促施策も、デイリーでPDCAを回して調整していく運用型の時代になってきていると感じます」と率直な感想を述べる。
そんな時代だからこそ、今後積極的に活用していきたいのがAIだ。アサヒビールでは、CDPに蓄積されたデータをAIで解析し配信の高度化・効率化を図っている。
たとえば、キャンペーンへの応募参加可能性を割り出したところ、AIが「参加する確率が高い」とはじき出した高スコアユーザーほど参加率が高いことがわかったという。逆に低スコアユーザーの場合、やはり応募は少なかった。
玉手氏はもともとデータ分析が好きで、数字を見続けたり、セグメント軸を策定したりすることは苦もなくこなしていくタイプだという。経験に裏打ちされたターゲティング設定には自信があったが、AIの予測の速さや正確さには「脱帽しました」とのことで、「マーケターが職人技のようにセグメントを切る時代ではなくなっていると思いました」と語る。
LINEのコミュニケーションでセグメント分けが求められるのは、当然ながら配信効率を上げるためだ。AIの活用について、玉手氏は次のように考えを述べる。
「LINEの友だち数が増えていくと、どうしても一人ひとりの顔は見えにくくなっていきます。『誰に送るか』ではなく、むしろ『誰に送らないか』という視点でコミュニケーションを最適化することが重要。人の感覚だけに頼らず、時にAIを活用することが大切だと思います」(玉手氏)
「お得」だけではなく「ブランド体験」へ、デジタル販促の未来
アサヒビールは今後、LINEのデジタル販促をどのように進化させていくのだろうか。
販促プロモーションといえば、購買を促進するため、最初はどうしても“お得感”を前面に打ち出す傾向がある。実際にアサヒビールもLINEでキャンペーンを始めた時は、キャッシュバックやポイント還元、サンプリングなど、購買者にお得を感じてもらうキャンペーンが主流だった。
一方、大きなブランドを持つ企業のマーケターとしては、「ずっとお得だけで良いのか」という葛藤が絶えずあったという。
「購買者にキャッシュバックやポイントなどの具体的な経済価値を提供することは、ビジネス上確かに大切ですが、それだけではないと考えています。そこは我々も議論を進めているのですが、ブランド体験や、パーパスに基づくメッセージも含め、様々なコミュニケーションをすることで、ブランドや商品、企業姿勢への理解を深めていただくことも重要だと考えています」(玉手氏)
これを受け、江田氏も、「LINEはブランド体験まで含めたフェーズをカバーするようなプラットフォームでありたいと思っています」と返す。企業にとってLINEを使うことで、より高付加価値なブランド体験を提供できるようにしつつ、購買者がキャンペーンへ応募しやすくなるように、LINEの販促体験そのものをより洗練化していくことを視野に入れているという。
たとえば応募方法については、シリアル付きシールや、レシート撮影、電子決済との連携といったように、さまざまな手段がある。これについて、リテール企業とLINEが連携することで、応募手段を拡充させていく予定だ。

「今後は『リテールパートナープログラム』という形で、リテール企業の方に特別なソリューションをLINEが提案し、メーカーと購買者にもメリットを還元していくプログラムを考えています」(江田氏)
「これにより、商品を提供するメーカーから、リテール、購買者に至るまでのエコシステムの体験価値を上げ、企業はLINE活用によるマーケティング成果をより向上できれば」と江田氏は意欲を見せる。LINEを活用した販促施策はこれからも進化していくようだ。