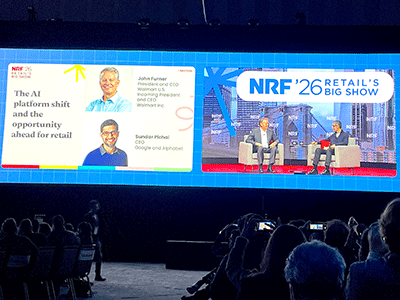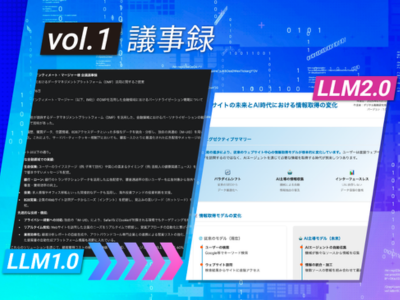本記事は『ビジネスを成功に導くデータ活用実践ガイド 顧客体験価値を創造し、向上させるためのデザイン』の「1.1 データ活用、その前に」と「1.2 存在価値をデザインする」から抜粋したものです。掲載にあたって一部を編集しています。
共通のWHY、言えますか?
DXという言葉は、流行り言葉からビジネス上の必須課題となり、今日ではその言葉を見ない日はありません。多くの企業がDXを中長期経営戦略の中心に据え、DX推進の専門部署を作り、今この瞬間にもプロジェクトが進んでいることでしょう。データ活用はDXという企業変革における一つの重要テーマに位置付けられている場合が多いかと思います。
本書を手に取られた皆さんも、データ活用を推進しつつ、DX推進プロジェクトに何らかの形で携わっている方だと思います。ここで、皆さんに質問があります。
なぜDXを推進し、データを活用する必要があるのでしょうか?
回答として、「競合他社がデータ活用を始めて、シェアを奪っているから」といったビジネスの全体課題を挙げる方もいれば、「今アプローチできていない顧客をとらえるため」といった、業務上の課題を挙げる方もいるでしょう。しかしながら、この問いに対する明確な答えを、関係者全員の共通認識として持った上で推進しているプロジェクトはどれくらいあるのでしょうか。
インキュデータが2022年6月に行った独自調査によると、およそ60%の企業が、DXを通じた企業変革の新しいビジョン策定や社内外へのマーケティング戦略策定の取り組みを検討していました。
この調査と並行して2021年4月から2022年3月の間に、DX推進を検討する41社の経営層や事業責任者と面談しました。うち11社は「DXを推進する必要性」や「DXを通じて目指すゴール」について、社内の共通認識を持った上で議論を行うことができました。裏を返せば残りの30社、つまり73%もの企業は「明確な答えを持っていない」「全員の共通認識を取れていない」という結果になりました。
DX推進は、企業の戦略上非常に重要な要素です。一定の成果を得るまでにはITシステムの刷新といった金額的な投資のほか、社員のリスキリングや専門人材への投資も必要です。他社もDXを推進しているから、といった外部環境に合わせた方策としてとらえるのは得策ではありません。
こうしたとらえ方は、「面倒なことが増えた」「新しいことを覚えなくてはならない」といったネガティブな考えがプロジェクトに蔓延する原因になりかねません。また、社内の業務効率化だけに注力すると、社外へ向けるべき考えがおろそかになってしまい、お客さまにとって不都合な顧客体験や価値を提供することになり収益が下がるといった、本末転倒な事態を招くリスクがあります。
目的を定めた上でDXを推進する
DX推進は、目的を達成するための手段です。目的を定めずにDXを推進することはできません。
まずは企業として目指すゴール(=目的)を明確にした上で、目標と現状の指標を比較する必要があります。既存のビジネスモデルで目標が達成できるのであれば、既存の業務プロセスの改善や最適化が最も早く目的を達成する方法になるでしょう。一方で、既存のビジネスモデルでは目標を達成できない場合は、価値の見直しやビジネスモデルの転換が方針になるかもしれません(図1)。

このように、DX推進は企業にとって重要な取り組みであり、ただ単に取り組めばなんとかなるものではありません。その理由や目的を明確にし、共通認識を持って取り組むことが必要です。顧客や従業員にとっても理解しやすい明確な理由があることで、DX推進による成果がより大きくなります。そのためには、DX推進の目的を明確にした上で、達成するための具体的な方法を検討していくことが重要です。
まずは先の「なぜその取り組みを推進するのか?」という質問、すなわち、自社の取り組みにWHYと問いかけて、共通の目的が明確に定まっているのかを確認してみてください。
HOW・WHAT思考の落とし穴
DX推進やデータ活用のWHYが明確になっていないにもかかわらず、HOWやWHATだけが明確に決まっているケースが散見されます。
具体的な例で説明しましょう。ある企業は顧客体験価値の向上を目的に、現在提供しているサービスを全て統合したスーパーアプリを作りたいと考えていました。我々への依頼は、スーパーアプリ作成のためにサイロ化されたデータベースをSaaSのデータ基盤で統合したいというものでした。
一見すると、問題がない方針のように思われます。しかし、「なぜスーパーアプリが必要なのですか?」と質問すると、「競合企業が提供しているからです」という答えが返ってきました。さらに掘り下げて聞くと、その企業がスーパーアプリを開発する独自の理由(WHY)が存在しないまま、SaaS基盤でデータを統合すること(HOW)と、スーパーアプリを開発・提供すること(WHAT)だけが決まっていたことが分かりました(図2)。

WHYを定めた上で、HOW・WHATを議論する
そこで、この企業が求めているスーパーアプリのニーズが実際にあるのか、確認してみました。既存の顧客がこの企業のメインサービスを利用する一番の理由は、シンプルに予約ができることでした。既存顧客は、この企業が提供する他サービスとの連動というニーズを持っていなかったのです。
顧客がシンプルな体験を望んでいるにもかかわらず、複数のサービスを統合した複雑な体験を提供してしまっては、本末転倒です。顧客体験価値の向上を目的にするのであれば、顧客視点でニーズを満たすための共通認識=WHYを持ち、その上で初めてHOWとWHATを議論することができます。
なぜやるのかが決まっていない状態、つまりWHYが決まっていないのにHOWとWHATが決まっているケースは、残念ながら多くの企業で見受けられます。結果、本来の目的を見失い、顧客目線の施策ではなく企業目線の施策になり、顧客体験価値の向上も収益の向上も実現できないといったことが起こり得ます。こうした状況を防ぐためにも、WHYの共通認識を形成することを強く意識しましょう。
企業やブランドとしての「パーパス」の定義
DXやデータ活用を手段とした顧客体験向上を学ぶために本書を手に取られた方からすると、「なぜデータ活用の本でパーパスを説明するのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
Purpose(パーパス)は日本語では目的や意図を意味しますが、ビジネス上のパーパスには社会的存在意義という意味があります。これまでの、良いものであれば売れるという時代から、人々の共感を得られる、社会的意義のあるプロダクトやサービスでないと使われない、売れない時代に変化しています。社会の中で企業がどのような責任を果たすのか、何のために存在するのかというパーパスを定義した上で次の手を打つことが重要になります。
ここで、DXやデータ活用について考えてみましょう。次のように、DXやデータ活用はIT戦略に限ったものではなく、企業経営の根本に関わるものです。
- DXやデータ活用は企業全体の存続に関わる極めて重要な戦略・投資であること
- DXやデータ活用は手段であり、目的ではないこと
一見すると、パーパスとDXおよびデータ活用には何の関係もないように思えるかもしれません。しかし、企業の社会的存在価値であるパーパスをゴールとし、そこに向かうための手段としてDXやデータ活用があるのです(図3、図4)。


登る山はどれか ― パーパスを実現する提供価値
企業の社会に対しての存在意義、つまりパーパスさえ定義できれば、企業は目指す世界の実現に向けて動き出せるのかというと、そうではありません。パーパス実現のためには、サービス・プロダクトを含む提供価値を定義する必要があります。ここでは、登山ツアーの企画に例えて考えてみましょう。
登山ツアーに参加するお客さまは、例えば、ツアー会社が掲げる、登頂して「最も美しい景色を見る」というツアーの目的に共感して参加します。一例として、初日の出を見るツアーを考えてみます。
注意する必要があるのは、「最も美しい」といってもその定義は人によってさまざまで、「最も美しい初日の出」に対するニーズもさまざまだということです。眼下に雲海を見下ろしながら太平洋から昇る初日の出を「最も美しい初日の出」とする方なら、富士山山頂への登山が一つの正解でしょう。富士山山頂と太陽が重なるダイヤモンド富士の初日の出を「最も美しい初日の出」とする方なら、別の山へガイドすることが適切です。
このように、お客さまのニーズを理解した上で、どの山へ登り、どのような景色を見せるかを企画しないと、ツアーには参加してもらえませんし、ツアー会社としてどのようなガイドをすべきかが定まりません(図5)。

ツアー会社は参加者が共感する美しい景色(パーパス)を見せるために、どの山に登るツアーを企画するか(提供価値の定義)を適切に設定する必要があります。
登るべき山が不変とは限らない ― 提供価値は変えられる
お客さまが共感する景色を見せるため、ツアー会社は登る山やルートを決めることが必要ですが、登るべき山はいつの時代も不変とは限りません。お客さまが求めるニーズが時代とともに大きく変化し、会社の元々の提供価値と大きく乖離が生まれた際に、登る山は変えずにルートを再整備したり、登る山自体を変更したりすることも検討すべき戦略の一つです。
ここでは、まずユニリーバの事例を紹介します。ユニリーバは「サステナビリティを暮らしの“あたりまえ”に」 を、その目的・存在意義と定義しています。
1880年代のイギリスでは衛生的な生活習慣が根づいておらず、多くの人々が命を落としていました。そのような状況の中、「清潔さを暮らしの“あたりまえ”に」という想いをこめて石鹸を販売したことが同社のルーツです。
その後、140年ほどが経過し、人々の生活環境やニーズは絶えず変化していますが、同社はホームケア用品のみならずヘアケア、男性用化粧品を含むパーソナルケア用品、食品など、その存在意義に沿った事業を展開しています。これは、時代の変化とともに、ルートを再整備していったケースと考えられます。
次に、「地球上で最もお客様を大切にする企業」であることを使命としている、Amazonの事例を紹介します。同社はその存在意義を達成するため、常に顧客の満足度を高めるために、事業活動を行っているように思えます。
書籍のインターネット販売業者として事業を開始しましたが、続いて小売業者がAmazonで出店できるマーケットプレイスをローンチ。その後、時代のニーズに応えるように、有料会員プログラムAmazon Prime や電子書籍のKindle、無人店舗Amazon Go といった独創的なサービスを生み出し続けてきました。
これらのイノベーションを起こした同社は、見せる景色(=「地球上で最もお客様を大切にする」)は創業時から変わらないものの、世の中のニーズや技術進歩とともに登る山を次々と変化させていったケースといえるでしょう。
登る山を決定できる組織づくり
企業が掲げるパーパスによっては提供価値が不変の場合もありますが、提供価値を変えたり、創造したりすることもあります。現状把握や未来を予測し、このような意思決定をする上でデータ活用は有益な味方となります。
ただし、ニーズがあるからといって付け焼き刃の価値を提供したり、企業にとって都合の良いデータやニーズだけをもとにした経営判断を行ったりすると、結果として自社のパーパス実現の妨げになるケースがあります。
データを一つの手段として利用しながら、顧客のニーズを理解し、意思決定ができる組織を構築していくことが、本当の意味でのデータ活用なのです。
フォアキャスティングとバックキャスティング
目指す世界(=パーパス)と登る山(=企業の提供価値)が決まったら、次に実施すべきは現在地の把握です。ゴールとそれに至るまでの経由地が決まっても、どこからスタートするかによって、道のりの長さや過程が違ってきます。
フォアキャスティングアプローチは現状からの積み上げ
一般的なプロジェクトでは、現在地の把握から始めます。現時点での達成項目と課題項目を分析して重要な論点を精査し、何を、どのような順序で進めていくかを決め、建設的にタスクを実行していくことが多いと思います。これは、フォアキャスティングアプローチと呼ばれる手法です。皆さんの日々の業務の多くは、このフォアキャスティングアプローチで進めているのではないでしょうか。
フォアキャスティングアプローチには欠点があります。現行の事業から逸脱したアイデアは生まれにくいという点です。フォアキャスティングアプローチは現時点での強みや課題解決を積み上げて成長を試みる手法のため、視野が狭くなりやすいという特徴があります。さらに、人間の性質として数値が悪い部分の改善やすぐに着手できる項目にフォーカスしてしまうことが多いため、革新的な成長プランが描きにくいといった傾向が見られます。
結果、比較的取り組みやすく、自社内でコントロールしやすい業務の効率化や業務プロセス改善に注視してしまい、中長期経営計画などで掲げられた社会に対しての価値の向上という目的から逸脱した取り組みを推進してしまうケースが見られます。
バックキャスティングアプローチは未来からの逆算
現在のように流動的で不確定な社会において持続可能な企業戦略を描く上での主流な手法は、あるべき未来を初めに描き、そこから現時点に向けて逆算し、実行すべき事柄を決定するバックキャスティングアプローチです。
バックキャスティングアプローチでは、企業の本来の目的=パーパスの実現に向けて、既存の事業に囚われることなく、本質的に必要な要素を定義できます。そのため手段が目的化してしまうことがなく、WHYに沿った事業や体験をDXによって実現する戦略が策定可能です。
それぞれのアプローチの特徴を生かす
ここで注意していただきたいのは、「フォアキャスティングアプローチが悪、バックキャスティングアプローチが善」ではないということです。プロジェクトの粒度によっては、既存事業から逸脱したアイデアは必要なく、目の前の課題を解決すれば事業の成長に事足りるケースもあるからです。
DXに取り組むにあたり問題となるのは手法ではなく、現在の業務改善のみに着目してしまうというマインドセットの部分です。企業にとって重要な成長戦略の一つであるDXは、先に述べた通り、金銭的投資や時間的投資に加えて人的投資も必要な、企業の一大プロジェクトです。
そのような会社の未来に関わるプロジェクトであるにもかかわらず、既存事業の課題解決のみにフォーカスしていては期待した成果が得られず、DXそのものへの懐疑的な見方が広がってしまう、といったことにもつながりかねません。
データ活用にも同様のことがいえます。ここでは、現状、デジタルマーケティング以外にデータを取得できていない企業のケースを考えてみましょう。この企業は多様な消費者の価値観の変化に伴い、商材チャネルやコミュニケーションのタッチポイントを変化させ、お客さまの幸せにコミットするという目的を持っています。
この場合、企業が目指す世界における理想の顧客体験をバックキャスティングアプローチで描くことが適切でしょう。また、それに合わせてデータを活用するために、どのように最適なデータアーキテクチャ(ビジネスのニーズに合わせてデータを適切に収集・保持・活用するための設計)を整備すべきかをあらかじめ検討しておく必要があります。
仮にこれを怠ってしまうと、新たなデータ活用のニーズが出てくるたびに、必要なデータの収集や統合、既存のプログラム改修を場当たり的に対応せざるを得なくなってしまいます。結果的に、顧客が望んでいる体験を提供できないといった、よくある失敗に陥る危険性があります。
こういった失敗に陥らず、本質的な目的を達成するためにはそれぞれのアプローチを適切に用いる必要があります。
フォアキャスティングとバックキャスティングの併用
我々は、データ活用を通じたDX戦略や事業のデザインに取り組む際に、フォアキャスティングアプローチとバックキャスティングアプローチの両方を採用しています。多くのプロジェクトで、フォアキャスティングとバックキャスティングの各アプローチにおいて導き出されるアウトプットのギャップをクライアントの経営層も含めて共有し、認識してもらいます(図6)。

フォアキャスティングアプローチとバックキャスティングアプローチを並行して行うことで、会社の中長期的な経営戦略と短期的な改善施策のギャップが明らかになります。また、事業部門の現場や経営層などの異なるレイヤーごとの視点とそれぞれの視点から導き出される戦略ごとのアクションに対する認識を統一できます。これにより、企業が本来目指すべきではない施策を実施したり、既存顧客のニーズにフォーカスし過ぎたりするような、本末転倒なアクションを防ぐことができます。