カスタマーが購入してはじめて儲けが発生
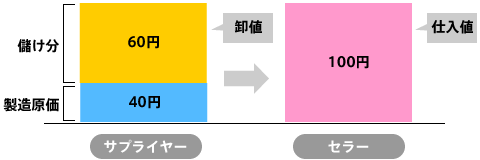
さて、その仮想仕入れなのですが、図解をしてみると上記のようになります。サプライヤーの卸値は100円…ということは、セラーの仮想仕入れ値も100円になります。先ほど、セラーは「仮想仕入れ」をするといったのですが、これはあくまでもセラーの立場にたってみた場合の表現であり、実はサプライヤーからみると、商品の「仮想卸」であるともいうことができます。上図の卸値と仮想仕入値が同一なので気づいていた方もいたのではないでしょうか。
さて、セラーは仮想的に商品を仕入れて、販売の準備を整えたわけですが、実際にカスタマー(顧客)に販売する場合にはどうするのかというと…、100円で販売はしませんよね? なぜなら、仮想仕入れ価格である100円で販売をしてしまっては、セラーの儲けが0円になってしまうからです。在庫処分でない限り、そんな出血大サービスはありませんよね。
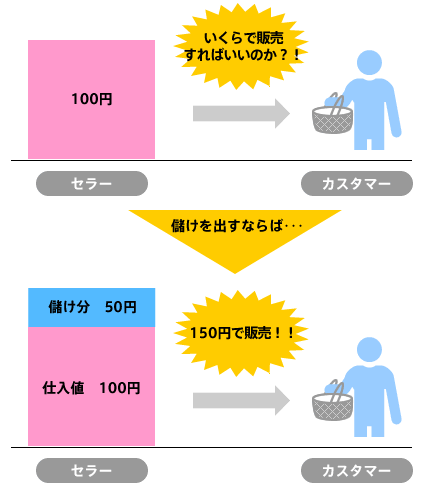
となると、サプライヤーがセラーに仮想卸をする際に製造原価にプラスして上乗せしたように、セラーは価格決定権を利用して利益を取りたい分を100円に乗せて販売することになります(ここではわかりやすいように、50円の儲けを得るために150円で販売するものとします)。
ここまでをみても、サプライヤーが仮想的に商品を卸してセラーが仮想的に仕入れただけなので、まだ、お金の動きはありません。となると、いつ儲けが発生してくるのか? ということになります。まぁ、もうお気づきの方も多いとは思いますが、最後のプレイヤーであるカスタマーがキモなんです。
もちろん、カスタマーは顧客というだけあって、セラーのお客様です。ですから、商品を購入…、つまり、購入に際して150円の決済(代金の支払い)をすることになります。ここでやっと「お金」というものが発生することになるんですね。
さて、この決済されたお金「150円」なのですが、いったいサプライヤーにいくらで、セラーにいくら入ってくる形になるのでしょうか。セラーが商品を実際に売ったら、サプライヤーはセラーに報奨金を還元すべきですが、ドロップシッピングでは、アフィリエイトのように「決済額の○%を還元する」という取り決めはありませんでした。
しかしながら、セラーが手にするべき金額というものは、実は既に決まっているのです。わかりやすくするために、先に金額を言ってしまいましょう。実は、セラーが手にすることができる儲けは「50円」です。どうでしょうか? いままでの流れをもう一度見返してみてください。50円、50円・・・ありますね。そうなんです!この50円という金額はセラーが価格決定権を行使して、サプライヤーの仮想卸値に対して上乗せをした金額ですよね。つまり、セラーの儲けというものは、サプライヤーの仮想卸値に対して、自分自身で値段をつけた分というものが利益になる仕組みなのです。
となると、サプライヤーの儲けも気になるところではないでしょうか。では、サプライヤーの儲けはどのくらいになるのかというと「100円」・・・つまりは、「製造原価+製造原価に上乗せした金額」(仮想卸値)になるんですね。

































