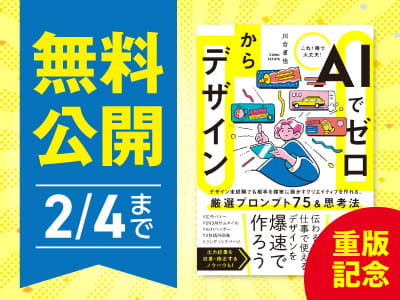重要なのは自社の顧客・カテゴリ・独自性を言語化し、認識を揃えること
――両社は創業初期から“インテントセールス”のカテゴリ創出を目指し協業していたと伺っています。その背景について教えてください。
小笠原:susworkの田岡さんと初めてお会いしたのは2022年ごろでした。弊社がシード期を終えシリーズAに差し掛かるタイミングで、さらなる成長を目指すための戦略を考えていたところに、知人から田岡さんを紹介いただきました。
田岡さんへ私たちの抱えていた課題をお話ししたところ、マーケティング戦略のワークショップを実施してくださり、WHO/WHAT/HOWを整理することができました。
お会いした際に「チーム全体でマーケティング戦略、WHO/WHATに対する認識を揃え、言語化することが最も重要」と話していただいたのですが、実際にワークショップを通じてマーケティング戦略の目線を合わせることができました。そこから田岡さんには、Sales Markerのマーケティング戦略について外部顧問をお願いしています。

田岡:小笠原さんに初めてSales Markerのお話を伺った時は、画期的なサービスだと感じました。ただ、メッセージングに改善の余地があり、お客様にその魅力を最大限理解してもらいきれていないと感じました。
そのため「Sales Markerとは一言でいうと何か?」というカテゴリと独自性を的確に表現すれば、市場を変えていくようなサービスになれるだろうという予感がしました。
そこでマーケティング戦略ワークショップを行い、その後の伴走を通じてカテゴリ戦略を描いていきました。
「値決めと価値が定まる」スタートアップにカテゴリ戦略が必要な理由
――スタートアップ企業にとって、カテゴリ戦略を描くことがなぜ必要なのでしょうか。

田岡:カテゴリを定義・創出することは急成長するスタートアップの命題と言えるくらい重要です。スタートアップがステークホルダーから望まれているのは、社会の課題を解決しながら高い成長率でグロースしていくことであり、そのためには社会や経済の環境変化から生まれてくる新しいマーケットを捉え、カテゴリを再定義・創出して圧倒的なシェアを獲得することが求められます。
カテゴリを創出するためはWHOとWHAT、つまり「誰に何を売るか」を定義する必要があり、そこが決まると必然的にプライシングも固まります。「値決めは経営」と言われるくらい、プライシングは企業のビジネス規模や可能性を大きく変えるためとても重要です。
スタートアップ初期では、多くの場合、イノベーターと呼ばれる新たな価値に敏感なユーザーがメイン顧客となってきます。彼らは詳細を説明しなくともプロダクトを見て、その便益を読み取り、サービスの導入を決定できます。
しかしイノベーター以外の多くの顧客にとって、新たなサービスはなかなか理解しにくいものです。
そのためスタートアップは、自社が何の課題を解決するサービスを、誰に向けて売っているのか、見失ってしまうことが多くあります。これでは高い成長率でサービスをグロースできません。
そうならないために創業時からWHOとWHATを定義し続け、カテゴリの勝ち筋を見つけていくことが重要となってくるのです。
インテントセールスのカテゴリをどのように創出した?
――“インテントセールス”のカテゴリ創出に向けて、どのように戦略を描いていったのでしょうか。
田岡:まず「自分たちの顧客は誰なのか?」というWHOを皆さんと一緒に定義するところから始めました。既存顧客はどのような企業が多いのか、そして企業のどういった課題を解決しているのか。今後はどのような顧客候補がいるのかといった内容を議論し、自分たちがサービスを提供したいターゲットを定めました。
その次に、ターゲットの中でも市場浸透を進め、成長していくために注力したいコアターゲットを定めていきました。コアターゲットを決めることは、リソースの限られているスタートアップにとって非常に重要です。
小笠原:コアターゲットの設定では、イノベーターからラガードまで5つの層に分けて市場の普及を捉えるイノベーター理論も意識しながら顧客の属性を整理していきました。
我々が提供する新しいサービスを利用してくださるイノベーターは、私たちと同じようにスタートアップである可能性が高い。一方で商談数の増加をビジネスにしている営業代行会社にもニーズがあり、それらへの導入はかなり進んでいる段階でした。
あらゆる観点から整理した結果、コアターゲットの候補として挙がってきたのが上場を目指しているシリーズC以降のスタートアップです。また、新たなカテゴリとして、顧客インテントを起点としたセールス活動として“インテントセールス”と定義しました。
ワークショップを通じてコアターゲットの仮説が導き出せたことで、顧客への提案もスムーズに進み、導入にも着実につながっていきました。

カテゴリ戦略が定まったことで、施策に確かな手ごたえ
――カテゴリ戦略をもとにどのような戦術を仕掛けたのか教えてください。
田岡:立案した戦略はあくまで仮説であり、検証することが重要でした。そのため様々な施策を行い、カテゴリがフィットしているか検証していきました。
その中で、特に反響があったのはビジネス映像メディア“PIVOT”へ出演するタイアップ企画です。登壇者の方と一緒に“インテントセールス”の啓蒙を行ったことで反響を得られ、小笠原さんと立案したWHO/WHATおよびカテゴリ戦略の仮説への確信を持っていただくこともできました。
小笠原:“PIVOT”への出演以外にも、イベントやウェビナーの開催などを行いました。“インテントセールス”に特化したイベント“世界初インテントセールスカンファレンス”の開催は業界にも大きなインパクトを与えることができました。
このカンファレンスでは、すでに弊社のサービスを利用し“インテントセールス”を実践してくださっている方を招き、まだ“インテントセールス”を実践していない方、これから実践する方へお話をしていただきました。多くのユーザーを巻き込み、カテゴリを盛り上げられた施策でした。
さらにWebサイト、広告、コンテンツなどあらゆる施策で“インテントセールス”というキーワード、説明を統一していくといった地道な施策も行っていきました。
こうした我々自身の一連の戦術の実行、検証は「インテントセールスでは、インテントシグナルを持つユーザーにマルチチャネル・マルチメッセージでアプローチすると、その施策が新たなインテントを生み出し、検索行動をはじめとしたシグナルを喚起する。顧客インテントを中心にあらゆるセールス・マーケティング活動が循環する」という気づきにつながりました。
この概念は“インテントホイール”という名称で、顧客起点の持続可能な事業成長モデルとして、現在提供しているサービスの根幹に据えながら、さらなるカテゴリ啓蒙に活用しています。
5日で3ヵ月分の問い合わせを獲得、カテゴリ戦略の成果
――カテゴリ戦略を通して、どういった成果が得られたのでしょうか?

小笠原:たとえば “PIVOT”で行ったタイアップ企画では、出演後5日ほどで300件ほどの問い合わせをいただくことができました。
当時、1ヵ月でいただくお問い合わせの数は100件程度でしたので、5日間で3ヵ月分の問い合わせをいただいたことになります。多くの受注につながり、ROIは10倍という数字を記録しました。
加えて良かったのが動画を見た方から「インテントセールス、おもしろい」という感想を数多くいただいたことです。
それまでは「顧客のニーズがわかるSaaS」という紹介をしており、強烈な印象を残すことができていませんでした。“インテントセールス”という単語を覚えていただくことができたというのは、私たちにとって大きな収穫となりました。
――仮説検証がうまくいったということでしたが、成功要因はどこにあったのでしょう?
田岡:カテゴリの浸透において、浸透フェーズにあった取り組みをすることは極めて重要です。
たとえば、インテントセールスカンファレンスを通して、イノベーターのユーザーの方々の成功した姿を伝えたり、世界初と冠を付けて内容を広く啓蒙したりすることは大きな効果があったと思っています。
また“インテントホイール”として、カテゴリを浸透させる中で思想やフレームワークをさらに言語化し啓蒙したことも重要な施策であると考えます。
ビジネスにおけるカテゴリは思想と共に啓蒙することで浸透しやすいと考えており、フレームワークがセットで広まることも多くあります。インテントホイールは、インテントセールスをより正確に理解いただくとともにカテゴリの浸透を進める上で重要なフレームワークだと考えています。
“インテントホイール”を中心にステークホルダーや周辺企業とともにカテゴリを盛り上げエコシステムを創出し始めることで、インテントセールスの検索数も継続的に増えており、第一想起を得ることができました。
「組織のインテントホイール」「スタートアップのグロース戦略伴走」両社の展望
――最後に今後の展開を教えてください。
小笠原:今回の取り組みを経て、スタートアップとしてプロダクトを市場に受け入れてもらうためには、プロダクトマーケットフィットだけでなく、カテゴリを創出し、マーケットと対話し続け、カテゴリも受け入れていただくことも重要だと思うようになりました。これを私はカテゴリマーケットフィットと呼んでいます。
現在は、ターゲットセグメントを拡大しており、たとえば “インテントジェネレーション”としてマーケティング分野での活用や、世界をリードする数万人規模の大企業の開拓も進んでいます。
また現在は、“インテントホイール”の考え方を事業だけでなく、組織にも活用できるのではないかと考えているところです。
これからも成長を続け、パーパスに掲げている「すべての人と企業が、 既存の枠を越えて 挑戦できる世界を創る。」 を実現するべく、活動していきたいと思っています。
田岡:“インテントセールス”の事例は、新しいカテゴリを創出しそのフェーズに合わせて勝ち筋を発掘することを突き詰めている事例です。

田岡:カテゴリの定義・創出は、多くのスタートアップにとって最重要課題であり、これまでは再現性のないものだと思われてきました。しかし、我々は既存顧客、市場、検索の分析などから、WHO/WHATの戦略仮説を立て、仮説検証することで、十分再現性を持たせることができると考えています。
susworkでは、スタートアップや新規事業の方々に、戦略ワークショップを通じたマーケティング戦略立案から中長期での戦略伴走を一気通貫で行っています。

田岡:新しいサービスの浸透に悩んでいたり、既存サービスの事業成長に課題を感じていたりする企業様は、ぜひ私たちにお声がけいただければと思います。
マーケティング戦略の無料相談・壁打ちできます!
本記事をお読みのスタートアップや新規事業で、マーケティング戦略やグロース戦略に課題をお持ちの方は、無料で壁打ち相談を実施しています。お気軽にsuswork公式サイトからお問い合わせください。