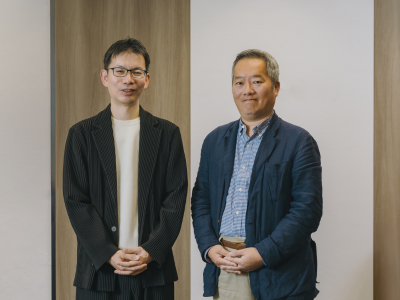※本記事は、2025年4月刊行の『MarkeZine』(雑誌)112号に掲載したものです
【特集】いま選ばれる「ブランド」の作り方
─ ブランドに求められる「善」と「余白」/これからのブランディングに必要な6つの視点
─ クボタが推進するK-ESG経営とコミュニケーション戦略、「選ばれるブランド」になるために
─ 大躍進のアシックス スポーツから“日常”へ「ブランドの新たな柱」をどのように作り上げたのか?
─ 明確に言い切るブランドが選ばれる 属人性を恐れないGREEN SPOONの戦い方
─ 「CXといえばプレイド」がブレない理由とは?規模拡大とともに変えたこと、変えていないこと(本記事)
初期はブランディングではなく、プロダクト作りに集中
──CXプラットフォーム「KARTE」リリース直後から現在まで、ブランド作りとして、ビジネス成長(規模拡大)のどのようなフェーズで、どのようなことをされてきましたか?
倉橋:ブランディングのために直接的に活動することはほぼありませんでした。私たちのようなSaaSスタートアップやソフトウェア関連企業は、初期ではプロダクトを作ることと、それに興味を持ってくださる方々に知ってもらうこと、そして仲間を集めていかなければなりません。すべてを同時に行うのは難しいものです。
そのため、私たちは初期的なマーケティングやブランディングはプロダクト作りに内包されていると捉えていました。プロダクト作りにフォーカスすることで、結果的にマーケティングやブランディングも始まるという流れです。旗(コンセプトやビジョン)を立てることで人が集まってくるようなイメージですね。
仲間集めに関しては、エージェントなどを通じた採用活動の比率も低かったです。社員数が100人程度になった時点でのおおよその採用構成を見ると、半数がリファラル採用で、残りの25%がエージェント経由、そして25%が転職メディア経由でした。立てた旗の力で人材が集まってきた証拠と言えるでしょう。

2011年10月に株式会社プレイドを創業。2015年、企業のカスタマーデータ活用を支援するクラウドソフトウェア「KARTE」を提供開始。顧客戦略またはDX戦略の推進基盤として、EC、金融、不動産、人材他、幅広い業界で導入されている。2020年12月東証マザーズに上場し、同年のIPO of the Yearを受賞。
2018年、ウェブ接客からCXへ
倉橋:展示会への出展など、より積極的なマーケティング活動を始めたのは2017年頃からです。イベントの参加者の方々からの反応をもとに2018年の春、ウェブ接客から新たな旗として位置づけたのが、CX(顧客体験)です。
背景には、ブランドや製品のコンセプト作りなど上流ではお客様のことを考えているのに、実際にお客様とコミュニケーションするタイミングになると、急に人を意識していないと感じる瞬間が多くなっていたことがあります。様々な企業が同様に苦しんでいました。解決されるべき課題がそこにあり、それを端的にどう捉えるかというと、やはりCXや顧客中心、顧客理解だろうと。
そういったものにチャレンジできる会社が輝く時代になっていくだろうと感じていたので、CXを選びました。旗を立てるのは難しいことで、具体的であればあるほど人々は乗りやすいものの、本質的な変化を捉えにくくなってしまいます。逆に遠すぎると「そうだよね」と皆が同意しても、「でも具体的にどうすればいいの?」という話になってしまいがちです。CXは、当時は少し遠い概念だったかもしれません。しかし、間違いなく今は市場が追いついていると感じます。
その「遠さ」があるからこそ旗として機能し、より魅力的な目標になりやすい側面もあるのだと思います。お客様や社員が集まるパワーというのは、ある程度野心的だったり理想的だったりする旗に生まれるものだと思います。そういう意味では、旗を下ろさずに続けてきたことが、今のところは正しい選択だったと思います。
──確かに売上が大きくなってくると、KPIの達成が優先され、顧客が見えづらくなる傾向があると思います。そこをCXに置き換えたのですね。御社では、オウンドメディアにおける事例紹介でも、単に成果を紹介するだけでなく、顧客体験を重視して発信していると感じます。
川久保:そうですね。KARTEのオウンドメディア自体は2015年にスタートしていますが、当初から数字をコミュニケーション手段の中心に据えないようにしていました。
2018年3月にはオンラインメディア「XD(クロスディー)」を、CXに特化したメディアとしてスタートしました。当時はCXに関する情報はほとんどなく、私たち自身もCXが何であり、何が良いのかということがわかっていなかったので、実際に取り組んでいる人たちに話を聞かせていただこうと考えました。それを世の中に学びとして出そうと2018年と2019年には「CX DIVE」というイベントも開催。CXに興味がある人や考えている人が集まり、意見を出し合いました。これはKARTEではなくCX軸で始めた活動です。
KARTE軸としては、たとえば2019年春に動画CMを制作。地上波やトレインチャンネル、駅のサイネージなどで展開しています。マスではないものの、オンラインだけに限らない形の露出には2019年から取り組んでいます。いずれも一貫して、顧客体験にフォーカスしてコミュニケーションを続けてきました。2024年にはプレイド顧客体験研究所(CX研)を設立、過去にメディアやイベントを通じて得たCXに関する知見をまとめるとともに、その知見の発信とさらなる探求を行っています。
また、デジタルを活用したCX変革が多くの企業に求められている中で、CXについて学びたい、CXを推進できる人材を育成したいという企業のニーズも増しています。今後、そのようなお声にも対応していきたいと考えています。

博報堂を経て、2015年よりプレイドに参画。「KARTE」ローンチ時よ りコミュニケーション領域を担当し、現在はCommunication Director/編集者として、コミュニティ、動画、イベント、メディアなどに関わる。日常の価値を問い直すビジネス・カルチャーマガジン『XD MAGAZINE』編集長を務め、2024年12月にVOL.8特集「掘る」を発行。
──これまでの取り組みに対し、社内の反応はいかがですか?
倉橋:仲間が集まってくるときも、KARTEが実現したいことや、実現したいことに対しての共感が強いため、社内でも「こういう方向がいいね」という会話が自然に生まれます。
もちろんこれらはブランディングを意識して行っていることではありません。私はブランディングの専門家ではないですが、冒頭でお話ししたようにスタートアップは何もない状態から始まります。人・モノ・金、何もないのです。成長と共に集まっていくのですが、そのときにどこか1つの側面に対してのブランディングだけではいけない。そこに集まってきている理由のようなものが、あらゆるアセットクラスの中で合致しないと事業はうまくいかないと思っています。
プロダクトや価値、世界観、どのようなことを成し遂げたいのかということを突き詰めると、結果的に特にアーリーフェーズでは人・モノ・金など重要な資本が合致するのです。私たちはこのようなことをただただ愚直にやってきたに過ぎません。
川久保:ロゴなど見た目を変えることだけがブランディングではなく、そのコアをちゃんと固める、コアとなる部分がどこから切り取っても同じように見えるということが大切です。だからこそ「KARTEとプレイドはブレていないよね」と言っていただけるのだと思います。
──コアとなる部分(ビジョン)を社内全体に共有するために、取り組んでいることはありますか?
倉橋:決定事項として社内に話すことはほとんどないですね。「多分こうだと思うんだよね」の時点、要は形作っていく段階には既にオープンになっており、皆で考えていく時間を大切にしています。
もちろん会社の規模も大きくなっているため、人によって多少は幅があるかもしれませんが、価値が作られていく過程に必ず何かしら関わる機会があります。現在は複数のグループ企業がありますが、グループ全体の統一感を生み出すことがブランド構築において重要と考え、どの要素をどこまで共通にすべきかを考えています。
──先ほどコアが固まっていて、どこから切り取っても同じものが見えるようにと話していただいたのですが、社名を変える選択肢もあったかと思います。あえてKARTEとプレイドを別にした理由はあるのでしょうか?
倉橋:お客様からも「KARTEさん」と呼ばれることもあり、営業効率が悪いから変えたほうがいいのではないかという声もありました。しかし結局将来どういうことをやりたいのか、どういう世界に行きたいのか、根源的にどういうことを考えているのかというのが会社だと考え、「効率が悪くても、変えない」という意思決定をしました。