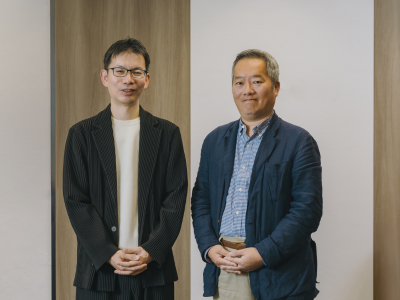データが示す市場の変容――「死への備え」から「生への投資」へ
エンディングノートや遺言書、相続対策、墓の準備など、死に備える行為を推奨する言葉として生まれた「終活」は、2009年に『週刊朝日』の連載から生まれ、2010年に「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされ、広く認知されていきました。日本の総人口の約3分の1が60歳以上となった社会構造の変化を背景に、今や誰もが知る言葉として定着しました。
しかし現在、その意味合いは当初の“死に備える行為”というイメージから大きく変化しつつあり、これからの“生きかたを再設計する行為”として捉えられるようになっています。その結果、「終活」はもはや人の心構えや家庭内の課題にとどまらず、一大市場として存在感を増しているのです。
終活にかかる総額は平均約503万円、その内訳は?
生きかた上手研究所が2025年2月に実施した「終活に関する意識と実態調査」では、終活にかかる総額は、平均約503万円にのぼりました。この内訳は、葬儀や墓石といった従来型の支出だけでなく、家のリフォーム、不動産処分、資産運用の開始など、生活そのものを再設計する消費が大きな割合を占めました。

※クリックすると拡大します
かつて終活と言えば、「エンディングノートを書く」「遺言を残す」「お墓を用意する」といった、死に備える行為が中心でした。その動機となるのは、「遺された家族に迷惑をかけたくない」という意識でした。
ところが近年は、「資産形成を始める」「家のバリアフリーに改修する」「健康習慣を見直す」といった、むしろ“これからの人生を良くするための行動”が終活に含まれるようになっています。
これは、「遺された家族のために整える」から「自分の人生を充実させる」へのパラダイムシフトと言えるでしょう。終活は消極的な整理ではなく、積極的な生活投資へと変容しています。そう捉えると、終活関連のビジネスはエンディング領域だけではなく、健康、金融、住まい、趣味など幅広い業種が参入できるテーマであることが見えてきます。