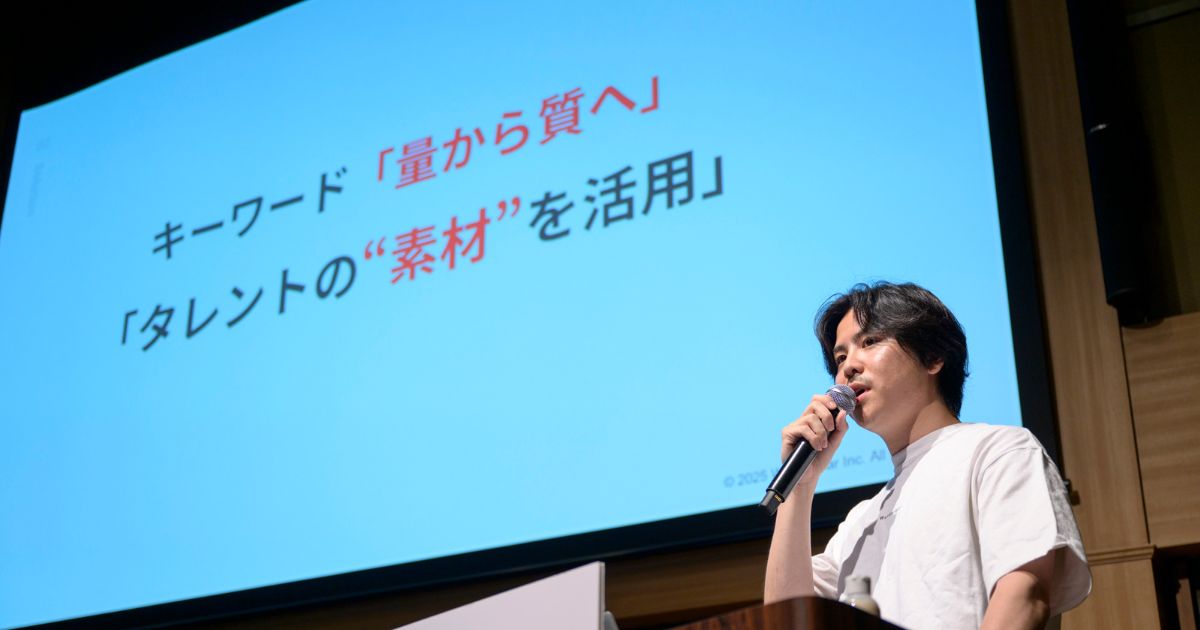予算、リソース、ブランド……行き詰まる広告業界
どんなに最適化を尽くしても、広告が“効かなくなる日”がやってくる――。セッション冒頭、Wunderbar代表の長尾氏は、現在の広告業界が直面する課題を整理した。
「マーケティングの4P(Product・Price・Place・Promotion)のうちプロモーション、特に広告の効果が鈍化しているのではないかと懸念を持つ方も多いのではないでしょうか」(長尾氏)
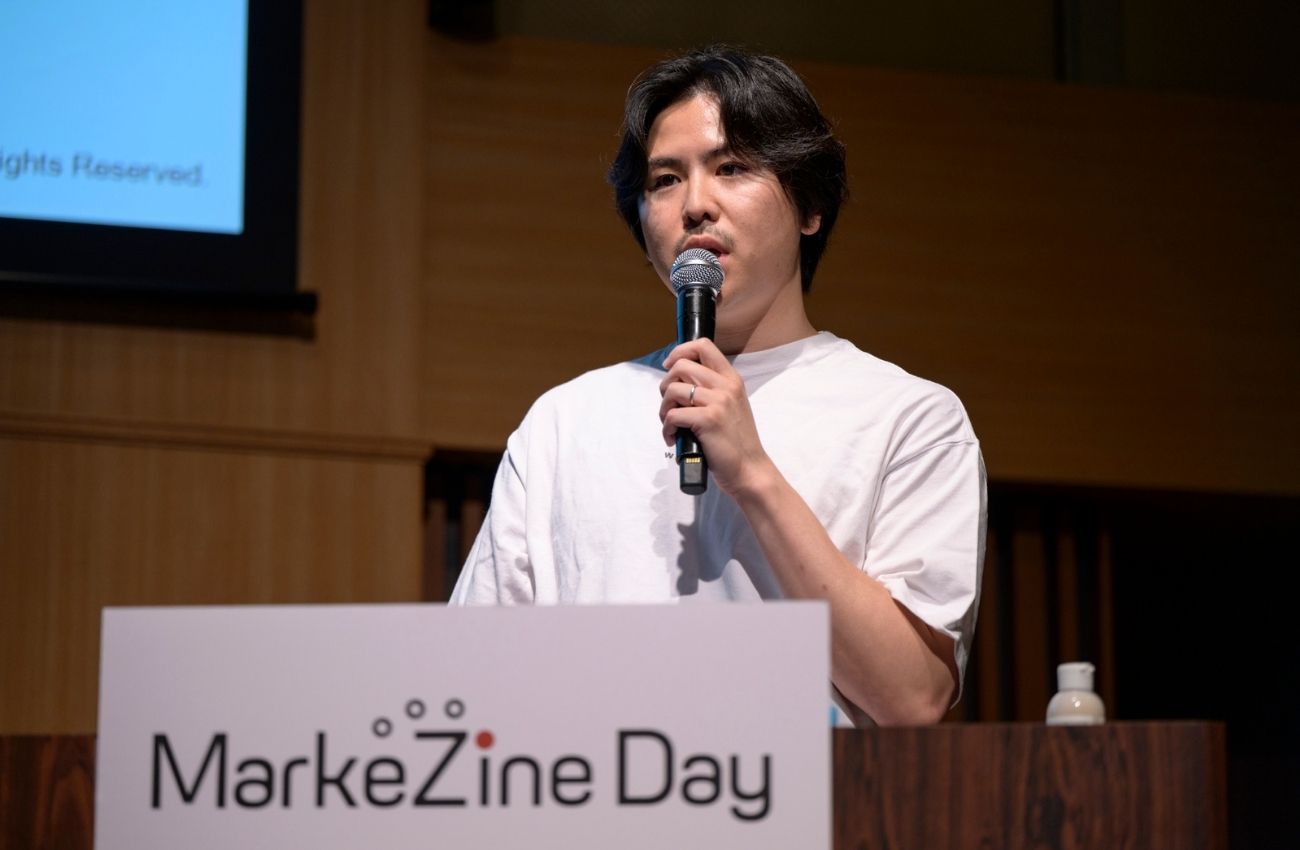
まず課題になるのが「予算」だ。大手企業の事業部単位では、一定の予算があっても大量投下に頼った手法で費用対効果が頭打ちになり、クリエイティブの質的改善が課題となっている。一方、中小企業では限られた予算内で最大効果を出す必要があり、広告量ではどうしても勝負できない状況だ。
次に「リソース」の課題がある。大手企業は承認や社内調整に時間がかかり、スピード感のある施策が打ちにくい。逆に、中小企業では専任人材や制作体制が不足し、質の高いクリエイティブを継続的に生み出すことが難しい。
さらに「ブランド・認知」の課題も深刻だ。大手企業はブランドガイドラインの縛りで「無難な広告」になりやすく、差別化が困難となる。中小企業はそもそも知名度が低いため、広告を出しても見てもらえない、または信頼されにくい問題を抱えている。
これらの課題に対する打ち手として、従来は広告の量や、その中での効率改善に偏りがちだった。しかし、スピード、差別化、信頼性といった質の観点では既に限界に達していると長尾氏は指摘した。
解消の一手は、タレントを“起用”ではなく“活用”すること
そこで課題解決のキーワードとして長尾氏が掲げるのは「量から質へ」の転換だ。その実現手段として、「タレントの素材活用」を提示する。
長尾氏は、タレントの価値を2つの要素で定義している。1つ目は「アテンション」で、一瞬で目を引く力(信頼・知名度)によりCTRを改善する効果。2つ目は「ストーリー」で、タレント独自の思想や生き方(人間性)によりCVRを向上させる効果だ。
しかしこれまで、タレント起用は「金額が高い」「時間がかかる」「レギュレーションが厳しい」などの課題があった。特にデジタル広告はPDCAを回して改善を繰り返す運用がベースとなるため、従来のような撮影を行う形でのタレント活用は非現実的な選択肢となっていた。
この課題を解決するためにWunderbarが開発したのが、IPマーケティングプラットフォーム「Skettt(スケット)」だ。タレントの素材をあらかじめデジタルデータ化することで、最短1ヵ月、10万円から利用可能なIP契約サービスである。

「Skettt」ではタレントの画像だけでなく、音声や動画素材も提供しており、SNS広告や縦型ショート動画制作まで対応可能だ。参画タレント数は300名以上、素材数は10万点以上。膨大なデータの提供から、効果測定・分析・フィードバックまで可能な仕組みとなる。
「タレントの素材も、事前に撮影した素材を使用しているのか、その商品のために新たに撮影したのか、見分けが付かないレベルまで合成技術が向上しています。私たちの掲げる『検証型のIP活用』を通して、タレントは起用から“活用”の時代になっていくと考えています」(長尾氏)
CVRが200%向上!タレント素材の活用事例を解説
ここから長尾氏は、実際にタレント活用を行った事例を紹介した。中年向けキャリアスクールを運営するライフシフトラボでは、中長期的に顧客獲得単価を下げていきたいという課題があった。
この課題に対応すべく、同社が起用したのは女優の菊川怜氏。東京大学出身で知的なイメージを持ち、同社のターゲットと同世代である点、そして「今よりベターな自分になれる」というブランドイメージと合致する点が決め手となった。
「菊川怜さんの知的なイメージとキャリアは、サービスコンセプトとストーリーがマッチしていました。また、交通広告への活用も全面的にOKとなっていたため、素材の使いやすさの面でもメリットがありました」(長尾氏)

結果として、3ヵ月後にCVRが200%向上、採用応募数も120%増加という大幅な広告効果の改善を実現。短期での検証効果が認められたことで、長期契約やテレビCM放映へ発展したという。
長尾氏は「最も重要なのはタレントの“ストーリー”を借りること」とし、「AIクリエイティブとIPクリエイティブにはそれぞれ良し悪しがありますが、ユーザーの心をつかんで購入まで導けるかどうかは、タレントのストーリー性が大きく影響します」と解説した。
ユーザーインサイトに沿ったタレント活用でCPA50%削減を実現
続いては、滋養強壮製剤を扱う京福堂の事例を紹介。同社では、LPやクリエイティブの改善を行うものの、商材訴求も難しく、CPAを下げる手段を模索している状況だったという。
そこで、「より渋くてかっこいい、ユーザーが目指したい男性像」に合致した俳優・西岡德馬氏の素材を選定。過去に別タレントでの起用効果が出なかった経験を踏まえ、ユーザー調査をもとに再チャレンジした中での選択だった。

西岡氏の素材を3ヵ月活用した結果、CPAが50%削減という大幅な改善を達成し、さらに成果を受けて長期アンバサダー契約へと発展した。また、この素材活用を機に西岡氏本人が商品を愛用してくれるように。従来の価格より大幅にコストを抑えての継続的な活用が可能となった。
低コストだからこそ、複数のタレント起用も可能に
ワイン製造・販売を行うメルシャンの事例においては、ブランドイメージ向上につながるプロモーションを模索していたものの、ロングテール型のワインでは、まとまったマーケティング費用を投入するのが難しい状況であった。キリングループでのタレント起用効果を把握していた中で、どうしたらタレント起用できるかと考え辿り着いた先が「Skettt」だった。
そこで、2名のタレント素材を活用する戦略を取った。1人目は優木まおみ氏で、「カジュアルかつナチュラルにくつろぎながら楽しめる」という商品イメージとの合致と、SNSフォロワーの多さが選定理由だ。また2人目の押切もえ氏はワインエキスパートを取得しており、世間のワイン好きなイメージと合致していること、結婚・出産経験というターゲットに適した背景を持っていることが決め手となった。

「このような複数名の起用が可能なのは、費用が安価だからこそ。同時に複数のタレントで検証することで、時期や商品といった様々な変数の中で、何が効果的で何が課題だったのかを明確に把握できるのです」(長尾氏)
結果として、優木氏をきっかけとする購入が30%にのぼるなどの成果を実現。これを受け、素材だけでなくオリジナルの撮影や別ブランドへのタレント追加など、より深い取り組みへと発展している。
キャラクターも、インフルエンサーも。IP活用をよりライトに
長尾氏は現状の「Skettt」の業界内の立ち位置について、以下のように表現した。
「単なる素材のパーツ売りではなく、IPの活用のソリューションを包括的に提供しています」(長尾氏)
さらにWunderbarは今後の展開として、タレント以外のIPカテゴリーへの拡張を進めている。2025年8月からは「Skettt Influencer」の提供を開始し、30万フォロワー以上のインフルエンサーの素材活用が可能になった。
「インフルエンサー素材へのお問い合わせは、日用品やアパレル、美容関連の案件を多くいただいています。特に『Skettt Influencer』では、これまでタレント起用をしたことがない中小企業様からの問い合わせが3~4割を占めており、従来の相場よりも格安で素材活用できることを評価いただいています」(長尾氏)
最終的な目標として長尾氏が掲げるのは、「IP活用を科学する」こと。膨大なデータを活用し、誰を・どのタイミングで・どのような企画で活用すべきかを、AIで提案する仕組みの構築を進めている。目指すのは、広告代理店に相談する前に、担当者レベルで「Skettt」のAIとコミュニケーションを取りながら最適な企画にたどりつける世界観だ。
最後に長尾氏は、改めてIP活用の魅力と「Skettt」としての意気込みを語り、セッションを締めくくった。
「広告領域でIP活用がライトにできるようになるだけで、今までとまったく違う検証が可能となります。お客様の広告運用を成功に導くために、プラットフォームをより磨き上げていきたいです」(長尾氏)