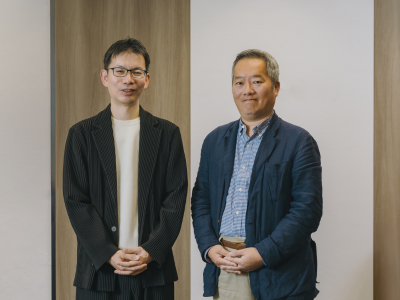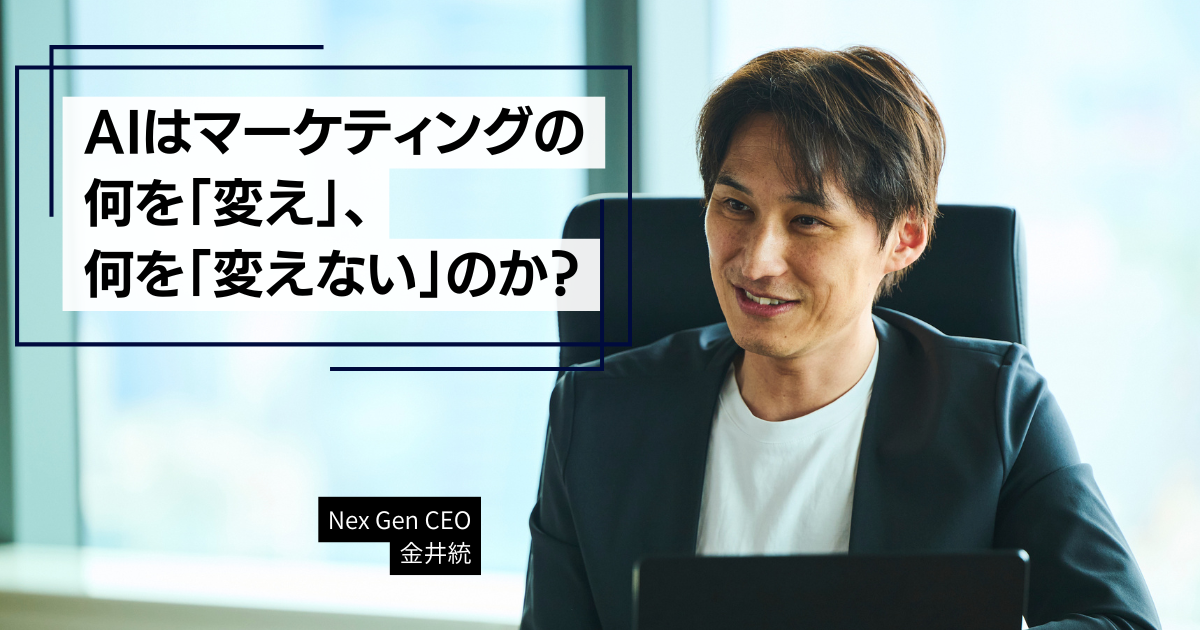AI時代の前提──何が変わり、何が変わらないのか
今回は、今後の「強みにフォーカスするマーケティング思考」の前提となる将来の社会環境について、皆様と一緒に考えていきたいと思います。AIによって何もかもが変わる──そんな言説が飛び交う中、世界中で大規模な投資競争が巻き起こり、AIはこの瞬間にも進化を続けています。「AIが人の職業を奪う」といった悲観的な未来予想もありますが、圧倒的な利便性には人間は抗えない、というのもまた事実です。
そうなると、ここで伝えていくマーケティング思考も、AIの普及によって変わるのではないかという疑問も浮かびます。だからこそ、具体的な思考の型に入る前に、AIによる変化にまずは触れておきたいと思います。
今年の3月、私はサンノゼで開催されたAIカンファレンス「NVIDIA GTC」に足を運びました。AI活用の最前線を自分の目で確かめたいと思ったからです。会場では、AIとロボティクスが融合し、身体を持ったAIがその場で思考・判断し、様々なタスクをこなす様子を目の当たりにしました。エッジコンピューティングによりリアルタイムで処理を行うAIロボットは、もはや“脳”だけでなく“身体”も持ち合わせた存在に進化していることを実感しました。その姿に、人間の代替として機能する未来が目の前に迫っているという興奮と、進化のスピードへの恐怖を覚えました。
ただ同時に、「それでも変わらないものはなんだろうか」という問いが残りました。本連載では、マーケティングにフォーカスし、「AIによって変わること」と「変わらないこと」の両側面を丁寧に考えていきたいと思います。
私は長らくインターネット業界で仕事をしてきましたが、今やっと「次のスマートフォン」と呼べるほどの大きな変化が訪れています。このタイミングで株式会社NexGenを創業できたことは本当に幸運でした。大きな変化のタイミングには、多くの成長の機会が生まれるからです。だからこそ、この連載を読んでくださっている皆様が、新たなチャレンジをしてみようと思っていただけたら、心から嬉しく思います。
マーケティングとAIの相性──「届ける」ことはAIの得意領域
第1回の連載で、私はマーケティングを次のように定義しました。
「人が創り出すマーケットのニーズに、限りなくリアルタイムに、価値を届けるために適応し、利益を生み出すこと」
この中で特に「リアルタイムに価値を届けるための適応」という部分は、AIとの相性が極めて良いと考えています。
実際に、既にオンライン上の情報マッチングにはAIが広く使われています。Googleが2015年に導入したAI検索アルゴリズム「RankBrain」や、TikTokのサイコグラフィックモデル(ユーザーの心情を読み取るアルゴリズム)などがその代表例です。AIはユーザーの行動や文脈を解析し、最適な情報をリアルタイムで届けることを可能にしています。
このように、マーケティングにおける「デリバリー=価値を届ける作業」はAIの得意領域であり、効率化・最適化は今この瞬間にも進んでいます。インターネット上に膨大なトラフィックが生まれ、データを活用して効率的に届けることができるようになり、工程の自動化が進みました。それが今では、AIによってデリバリー業務全体が自律的に改善される未来が見えています。
加えて、広告の伝達効率を担うクリエイティブ制作にもAI活用は常態化しつつあります。デジタルはもちろん、テレビや映画などの制作プロセスでも導入が進んでいます。現時点では工程の効率化が主ですが、タレントの代替としてAIで生成した人物を使うケースも出始めており、デリバリー領域は急速に代替が進むでしょう。
少し前までは「人がデータの活用方法を考え、機械がそのデータをもとに運用する」という役割分担を想定していました。しかし、急速な進化によりAI自らがデータの活用方法を考え、改善を繰り返す時代が訪れています。AIが自律的に思考して駆動する未来を前提にすると、デリバリーはAIに代替させたほうが効率的です。他方、「人が創り出すマーケットのニーズ」をAIが本当に掴めるのか。私は、マーケティングを担う人がこの点に集中すべきだと考えています。理由は、人は日常で必ずしも合理的に意思決定をしていないからです。従って、AI時代のマーケティングを担う人は「誰に、何を」という本質的な価値設計に集中していくことが重要になるでしょう。