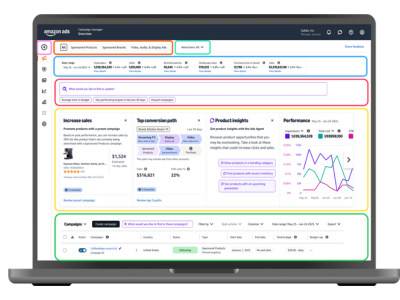会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 関連リンク
- ブランディングと購買行動の関係を探る【短期連載】連載記事一覧
-
- 【第2回】ブランドの記憶資産と売上の関係とは?「利益を創る」優れたブランドマネジメントの視...
- 【第1回】ブランディング投資はなぜ重要なのか?消費者の記憶と意思決定のメカニズムを紐解く
- この記事の著者
-

安野 将央(ヤスノ マサヒロ)
株式会社マクロミル
シニアマネージャー/マーケティングサイエンティスト
大学卒業後、D2C企業にてデータベースマーケティングに従事。新規顧客の獲得からリピート顧客育成まで、LTV(顧客生涯価値)をベースとした顧客分析でPDCAマネジメントを担当。マクロミル入社後は、...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア