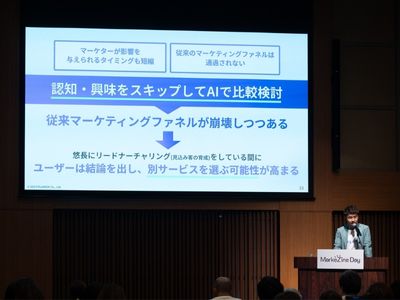実際にリスティング広告の改善案の立案・施策の実施をそれぞれの要素でどのように行うかの例を紹介しよう。
- キーワード
キーワード別に効果測定することによって、思うほど効果が出ていないキーワードがわかる。それらのキーワードは、単純に効果が悪く、出稿停止すべきキーワードと、改善の余地があるキーワードに分けることができる。改善の余地があるキーワードとは、広告主にとって関連性が高いキーワードであるにも関わらず、広告文等他の要素によって効果が悪くなっている(と考えられる)キーワードのことである。改善の余地があるキーワードが判明したら、それぞれのキーワードのインプレッション数・クリック数・入札単価を調べ、インパクトの大きいものから優先順位をつけて改善施策を行っていく。 - 広告文
広告文の改善案を立案するに当たり、効果を上げる指標はクリック率かコンバージョン率になる。クリック率を上げるということは、いかにクリック数を増やすかという目標になるし、コンバージョン率を上げるということは、いかに無駄クリックを減らすか(コンバージョンするユーザを効率的に誘導できるか)という目標になる。それらの目標を受けて具体的に何を行うかというと、広告文の訴求ポイント(例えば安さ、高機能等)を明確にし、興味を持っているユーザのみが広告をクリックするような施策が例としてあげられる。訴求ポイントを分けた別々の広告文を複数テストし、最もユーザに響く訴求ポイントを発見し、それをブラッシュアップしていきクリック率を上げていくという流れだ。 - リンク先URL
リンク先URLについては、何が達成できれば成果が上がったかというと、コンバージョン率の上昇か、コンバージョン後(オフライン)で引き上げた割合が上がることだろう。施策案としては、単純にリンク先を変更することや、LPOを実施している際にはランディングページのデザイン変更・訴求ポイントの変更・キャッチコピーの変更などがあげられる。また、Web解析ツールを使用していれば、サイト内の導線分析を行えるので、お申込フォームのどのステップで離脱しているか、コンバージョンをするユーザはどのようなページを見る傾向があるかなどを分析し、サイトへフィードバックしていくことによってサイト自体のコンバージョン率を上げることも可能だ。
施策実行時の注意点
改善施策を立案し、実行する際に注意すべき点がいくつかあるので以下に述べる。
- 改善施策が狙い通りの成果をあげられない可能性
当たり前のことかもしれないが、念のために確認しておくと、何か変更を行った際に効果が上がることもあれば下がることもある。施策を実行する前に、その施策を行うことでどの程度のリスク(究極はコンバージョン数がゼロになること)があるかを事前に考慮した上で実施する必要がある。 - 時期要因の考慮
例えば2つの施策(施策A、施策Bとする)を実施する際に、時期をずらして実施する方法と同時に実施する方法がある。前者の方法の場合、月初から中旬に「施策A」を、中旬から月末に「施策B」を実施することになる。リスティング広告を運用していて、お気づきの方もいらっしゃると思うが、下旬になればコンバージョン率が下がるであるとか、コンバージョン率の高い月・曜日等があるので、時期をずらして施策を実施した場合、その施策の成果なのか時期要因によるものなのかが判断しづらい。この点を考慮に入れないと、本来であれば効果が上がる施策なのに、時期要因のせいで効果が下がったと誤解してしまう恐れがある。
同時に実施する方法であれば、時期要因による影響を排除できるので、できればこの方法で実施することをお勧めする。参考までに述べておくと、Overture 新スポンサードサーチとGoogle アドワーズにおいては、ひとつのキーワードに対して複数の広告文・リンク先URLを設定することが可能である。この方法での懸念点は、施策の実施期間が広告を単体で運用する場合よりも長くなってしまうことにある。これは、複数の広告を均等配信した場合にインプレッション数が配信する広告の分だけ等分されてしまうからであり、この方法を使用するキーワードはある程度のインプレッション数を持っていたほうが良い。
テストを繰り返して効果を上げよう
以上に、効果測定の方法から改善施策への流れを述べた。再度、あなたの管理しているアカウントのデータを見直していただくと、完全な状態ではないことがお分かりになると思う。また、改善施策を実施して、ある程度の成果を得られるようになるには、1回テストを行うだけでは不十分で、何回もテストを繰り返す必要があるので、すぐにでも効果測定の仕組みを導入し、改善施策をテストされることをお勧めする。