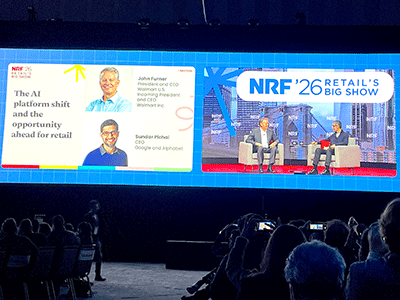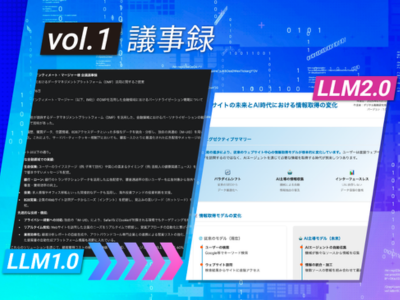「なぜファンが大事なのか」を知りたい人に読んでほしい
――“さとなおさん”こと佐藤尚之さんの『ファンベース』(筑摩書房)、高橋遼さんの『熱狂顧客戦略』(翔泳社)が2月に発売となりました。まず、佐藤さんはこれまで広告やコミュニケーションの領域で重要な書籍を出版してこられましたが、今回はどのようなねらいで執筆されたのでしょうか。
佐藤:『明日の広告』(アスキー)は、これからはトップダウンの妨害型の広告では通用しなくなり、相手の気持ちを考えたコミュニケーションが重要になると書きました。『明日のコミュニケーション』(アスキー・メディアワークス)では、SNSが普及してくる時代に関与する生活者の中に入っていって愛されることの重要性について書いています。『明日のプランニング』(講談社)では、ネットやSNSが当たり前になると予測された社会が、実はそうではなく二極化してしまったことを受けて、マスベースとファンベースに分けてプランニングする重要性について書きました。

ファンベース ──支持され、愛され、長く売れ続けるために(ちくま新書)
佐藤尚之著
その流れを踏まえ、『ファンベース』(筑摩書房)ではファンベースに特化して、ファンをベース(土台・支持母体)に、中長期にコミュニケーションを構築していく方法を提案したんです。
その提案の根本には、人口急減やウルトラ高齢社会、成熟市場などで新規顧客の獲得がとても難しくなっているという時代的・社会的な流れもありますが、日本の情報環境がデジタルの施策が効く人とマスの施策が効く人に二極化してしまい、従来のキャンペーンなどがとても効きにくくなったという部分も大きな要素となっています。
大都会で仕事をしていると認識しづらいかもしれませんが、スマホやネットを駆使している人は、日本全体で見ると実はマイノリティと言っていい。たぶん2~3割しかいないと思います。大半の人は、ネットは利用してても使うのはメールとLINEとソーシャルゲームくらいで、日常的に検索すら使わない人がたくさんいます。
ヤフーから47都道府県別の検索数調査が出てますが、検索を使っているのってダントツに東京だけ。東京は別の国なんです。その外側にはネットのつながりよりリアルなつながりを大切にするライフスタイルの人が大勢いて、実は日本の大半はそういう人たちなのです。そういう人たちにはまだまだテレビが強力な影響力を持っています。
この二極化した人たちのどちらにも届き、態度変容まで促せるのは、友人のオススメです。なぜなら友人とは価値観の近い人だからです。価値観が近い人が愛用しているモノ、大好きなコトなどは、自分も好きになる確率が高い。この情報も商品も過多な時代、友人の言葉ほど信用でき共感するものはありません。で、その友人がある商品の熱量高いファンであったなら、それは熱量高くその友人たちに伝わっていきます。ファンが友人に商品を勧めてくれることほど効くものはないんですね。
ちょっと前までは広告キャンペーンが効いたので、そちらのほうが効率的でした。でもこんなに効きにくくなった時代において、相対的にファンが友人に伝えてくれることがとても大切になってきます。しかも日本は毎年100万人都市が一つずつ減る勢いで人口が減少し、物理的に新規顧客を増やすのが難しくなっていく。高齢化も進み、新しいものや知らないものに手が出にくくなる人も増えていくでしょう。
そうした状況を踏まえると、すでに知ってくれていたり熱心に買ってくれたりしているファンこそ大事にしないといけません。しかも、多くの商品ジャンルでたった2割のファンが8割の売上を支えているんです。本のタイトルを「ファンベース」としましたが、大切なのは「ベース」の部分。ファンを土台にして売上をきちんと確保しつつ、ファンに新規顧客を増やしてもらうというのがファンベースの基本の考え方です。

左:佐藤尚之さん(ツナグ 代表、4th 代表)
右:高橋 遼さん(トライバルメディアハウス チーフコミュニケーションデザイナー)
――高橋さんが『熱狂顧客戦略』を執筆するきっかけになったのは?
高橋:僕が所属するトライバルメディアハウスは、TwitterやFacebookが日本に上陸して以来、企業のソーシャルメディア戦略をサポートしてきました。当初、われわれがご支援していた企業の「ファン」や「フォロワー」と呼ばれる方々は数千、数万人の規模でしたが、年を経るごとにソーシャルメディアのユーザーが増えてきて、企業のSNSアカウントのファンやフォロワーはここ数年で一気に数十万、数百万単位にまで増加していきました。
そのような中で、一口に「企業のファン」と言っても、その濃度は人によってばらばらだと感じ始めたんです。ブランドのコアなファンから、キャンペーンでSNSアカウントに「いいね!」を押しただけの人までを一括りに「ファン」と呼んで、その人たちに同じようなコミュニケーションをしていくのは妥当ではなく、ファンの熱量に応じてどのようにコミュニケーションを分けていくかが企業の課題になってきていました。
その中でも特にブランドへの熱量が高い人たちは企業にとって重要ですし、その人たち自身も一括りにされたくない。ライトなファンとは別のことを求めているんですね。その微妙な「熱量」の違いに着目して顧客とどうコミュニケーションしていけばいいのかをまとめたのが『熱狂顧客戦略』です。

熱狂顧客戦略 ――「いいね」の先にある熱が伝わるマーケティング・コミュニケーション
(MarkeZine BOOKS)
高橋 遼著
――おふたりは、それぞれの本を読んでどんな印象を持ちましたか?
高橋:顧客との関係性、つまり、お客様は神様ではなく友達だという考えはさとなおさんの『ファンベース』と共通しているところかなと思いました。特に、ブランドそのものよりも企業やブランドが発信する価値に共感してもらうことが大事だというところは、僕も大いに賛成ですし、とても重要なポイントだと思っています。
僕は熱狂的なファンとどうやって向き合い、一緒にどんな価値を作っていくのかを考えながら、現場の目線で本を書きました。一方で、佐藤さんの『ファンベース』は現場に挑む前のプロセスや、マーケティング全体の中でファンとの付き合い方をどう描いていくかを整理されていたと思います。
佐藤:『ファンベース』は、高橋さんの本に比べるともっと基本を書いた本だと思っています。キャンペーンなどで新規顧客を増やす、という従来の考え方から抜け出られない人が多いので、そのマインドセットにかなり枚数を割いている感じですね。この本は僕が書いた原稿を「さとなおオープンラボ」の人たち200人くらいに読んでもらい、分からないところを指摘してもらったんです。そうしたら「そこから説明しないとダメ?」みたいなことが山ほど出てきた。なので、そこを大事にしました。
また、本書では「共感、愛着、信頼」とそのアップグレードである「熱狂、無二、応援」という言葉で具体的にファンベースの考え方を整理しました。「ファン」に関してあまり理解や知識のない上司などを説得するための役割を意図しているので、なぜファンが大事なのか、そこから理解したい方に読んでもらえればと思います。
社員が共感していなかったらばれます
――両書とも、まず始めるべきこととして「社員がファンになること」が大事だと書かれています。当たり前とはいえ、意外と難しいことのようにも思いました。
高橋:いままでは経営層が決めたことが現場に降りてきて、現場からは社員の意向よりも決まったことを伝えるための統一されたメッセージが発信されてきました。それを「コミュニケーション」と呼んでいたんですね。
ですが、日々お客さんと接するのは現場の社員やスタッフです。つまり、社員がお客さんをファンにする直接的なエンジンとなるわけです。だとすれば、社員が自社やブランド、商品に熱狂してファンになっていないと、メッセージは伝わらない。経営層は社員に権限委譲したり、ファンをおもてなしした社員を評価する仕組みを作ったりして、社員に熱心なファンになってもらう必要があると思います。
佐藤:どんなに戦略を練って実行したとしても、社員が商品に共感していなかったり、不満を感じていたりすれば絶対お客さんにばれますよね。SNSでは特にそうです。

佐藤尚之(さとう・なおゆき)
1961年東京都生まれ。(株)電通にてマス広告、ネット広告、コミュニケーションデザインなどに携わったあと、
2011年に独立。現在は、コミュニケーション・ディレクターとして、(株)ツナグ代表。
コミュニティ主宰・運営として、(株)4th代表。
著書に『明日の広告』、『明日のコミュニケーション』(ともにアスキー新書)、
『明日のプランニング』(講談社現代新書)、『ファンベース(ちくま新書)』等多数。
ただ、社員がファンになることから始めるべきではあるのですが、これは社内改革に近いのでその話を持ち出してもなかなか前に進まない。だから、本書はそこは軽くまとめただけにしました(詳しく知りたい人は『明日のプランニング』を参照)。でも「内面を磨かないとばれる」ということは意識しておいてもらいたいです。創業者がリスペクトされている企業が強いのは、やはり社員に自社への共感があるからでしょう。
高橋:社員間の共感も大事ですよね。たとえば、ワークショップでお互いに「なぜこの会社に入ったのか」といったことを共有すると、そこから共感が生まれていきます。いつも一緒に仕事していても、そういうことを意外と知らない方が多いように感じます。現場ではむしろ、そうしたところから始めてもいいのかもしれません。
大事なのはNPSよりも「きっかけ」
――企業にとってファンが重要とされる理由のひとつに、ファンが家族や友達などに商品を勧めてくれるという部分があると思います。NPS(Net Promoter Score、商品推奨意向)に注目が集まっている理由もそこにあるわけですが。
佐藤:NPSを測って短期的に安心しちゃう人がいますけど、たとえNPSが高くても、人ってむやみやたらと誰かに商品を勧めることはないんですよ。何の文脈もなく急に勧めてきたら怖いじゃないですか。人はもっといろんな文脈を持って友人にお勧めするものです。
さらに、日本人は世界的に見てもトップクラスに自分に自信がない国民なんです。だから「この商品を人に勧めていいものかどうか」の自信が持てないんです。自信がないとどんなに好きでも人に言いません。本書では『レタスクラブ』の例を挙げていますが、他のファンが「最近のレタスクラブ、好き」「この数号、とても面白い」と言い出して初めて「みんなもそう言ってるし、自分も言っていいんだ!」と思えるようになるんです。言ってもいいと自信を持ってもらえる、好きだと言えるきっかけを作る。そういう施策を意識してやらないと熱狂してても他人には勧めないんです。
高橋:これまでの経験から、たとえ熱狂的なファンでも、自分がなぜそれを好きなのか、うまく言語化できていないケースはとても多いです。ファン同士で話すことで自分が好きな理由に気づくことがある。以前行ったインタビュー調査では、「誰かに話すたびに好きになっていく」という方もいました。
また、お勧めするというのは能動的な行動ではなく、どちらかといえば受動的で、訊かれたときに答えるものだと思います。カメラに詳しい先輩にお勧めを訊いたことがあるんですが、質問すればいくらでも教えてくれる。けれど、僕がカメラについて関心があるそぶりを見せていないのに、いきなり「カメラはこのメーカーがお勧め」なんて言ってこないですよ(笑)。

高橋 遼(たかはし・りょう)
1983年鳥取県生まれ。トライバルメディアハウス チーフコミュニケーションデザイナー。
2007年、慶應義塾大学総合政策学部卒業。広告会社を経て、2010年にトライバルメディアハウスへ参画。
企業のマーケティング戦略構築およびプロモーションプランニングおよび実行に従事。
これまでに大手航空会社、ファッションブランド、スポーツブランド、化粧品ブランド、飲料メーカーなどを担当。
佐藤:だから「きっかけ」が大事なんですよね。そう考えると、言いやすくなる状況を作るのにテレビCMやキャンペーンは有効なんですね。「テレビCMが効かない」「広告は見られない」と言われるけれど、全然そんなことはない。ファンは喜んでいるんです。そして自信を持つ。そういうことがないと、人はよほどのことがないと能動的にはお勧めしないです。本当に親しい友人だったら、会っていきなり「あの商品、買った?」とか言うかもしれないけど(笑)。
企業のコンテンツはファンのために
――「ファンベース」や「熱狂顧客戦略」に関連するものとして「CRM」や「コンテンツマーケティング」があると思いますが、これらはどのような位置づけになるのでしょうか。
高橋:CRMは購入量と顧客の感情をどう切り分けるかということがポイントだと思います。「買ってくれた人はすべてファン」と考えがちですが、そうではないんです。購入量と愛情を混同せずに、まず愛情を高めて、そのあとで買ってもらうプロセスをどう作っていくかを考えます。
佐藤:「コンテンツ」はそんなに簡単には見てもらえないという認識がまず必要だと思います。YouTubeだけでも毎分400時間分の動画がアップロードされていて、1日分を観るとしたら65年かかるらしいです。そういう状況下において、企業に都合のいいことを一方的に伝えるようなコンテンツが勝てると思うほうがおめでたいと思います。
ただ、そんな中でもコンテンツを見に来てくれる人はいます。それがファンです。ファンは興味もあるし関心もある。喜んで見に来てくれます。にもかかわらず、企業のサイトは新規顧客向けに作られていることがほとんどなんですよ。この時代、わざわざ見に来る新規顧客なんかほとんどいないと僕は思っています(笑)。ファンか、もしくはリピーターがかろうじて見に来てくれる。サイトやコンテンツを作るならそういう人たち向けに、そういう人たちが喜ぶものにすべきですね。
――最後に、あらためて本についてのコメントをいただければと思います。
高橋:僕は、佐藤さんが最初の本『明日の広告』を出版した年(2008年)に社会人になりました。その約10年後、今回初めて本を書いてみて、最初はなんとなく不特定多数を対象に書いていたんですが、それだとかえって伝わらないと思い直し、改めて「熱狂顧客戦略」というコンセプトを一緒に作り上げてきた、社内のスタッフやこれまでにプロジェクトをご一緒したお客様をイメージしながら書くようにしました。
本当にその価値を伝えたい、知ってほしい相手はみなさんの目の前にいるにも関わらず、企業の皆様は意外と自社のブランドのファンに会った経験をお持ちの方が少ないように感じます。ぜひみなさんのブランドの熱狂的なファンに会って、直接その声を聞くところから活動を始めてみることがますます重要になってくると思います。
佐藤:僕は時代や社会がこうも難しくなり始めてから、不特定多数に対するコミュニケーションは半分以上諦めてきています。もうマスは存在しない。それよりも、たとえ小さくても、熱心なファン・トライブやコミュニティにしっかり伝えることが大事だと思います。そこには確実に伝えられる。そのうえで、ファン・トライブやコミュニティの人たちが周りに少しずつでも伝えてくれれば、それが最強だと思っています。
本書は書店に並びますし、広く売ることが前提ですが、特定少数に伝わればいいと思って、具体的に伝えたい人の顔を思い浮かべて書きました。本書に限らず、まずは特定少数、伝えたい人を絞ることが大事だなと思います。