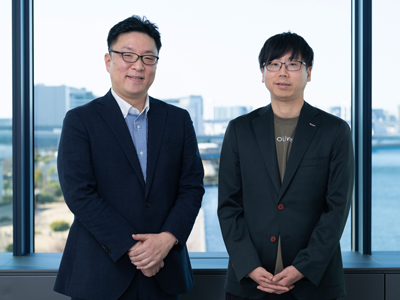まだ多くの企業は真のDXにたどり着いていない
今回紹介する書籍は、『マーケティング視点のDX』(日経BP)。著者は、江端浩人事務所代表/エバーパークLLC代表でiU情報経営イノベーション専門職大学教授の江端浩人氏です。
江端浩人(著)日経BP 2,200円+税
江端氏は伊藤忠商事、ITベンチャーの創業を経て、日本コカ・コーラ、日本マイクロソフト、アイ・エム・ジェイ、ディー・エヌ・エーなどでマーケティングの要職を歴任。現在はエバーパークLLC、iU情報経営イノベーション専門職大学教授および江端浩人事務所代表として、各種企業のデジタルトランスフォーメーションやCDOシェアリング、次世代デジタル人材の育成に尽力しています。
ニューノーマル時代に突入し「自社のビジネスのDXを加速したい」という会社が増えてきました。しかし、江端氏は真のDXとなりえる動きをしている企業が少ないと語ります。真のDXとは一体何なのでしょうか?
「デジタル化」と「DX」の違いは何なのか
これまでも、「IT革命」「デジタル化の推進」といった言葉が企業から出てくることはありましたが、DXとは一体何が違うのでしょうか? これに対し江端氏は、「ただデジタル化したことを『DXに取り組んだ』と捉えると、システム導入や業務効率化にとどまり、新たな価値を生み出すところまでたどり着かなくなる」と指摘しています。
たとえば新聞の場合「〇〇新聞」に乗っている記事が「〇〇オンライン」という電子版で読めるようになった――。これは紙からネットへの置き換えで、デジタル化です。知りたい事柄を手軽で検索できたり、興味のある記事をクリップしておけたりと、紙より電子のほうが使い勝手は高まりますが、これだけではDXとは言えません。
こういった場合は、読者としては、類似ジャンルのメディアが連携してワンストップで読めるほうがありがたいでしょう。また、読者Aさんの閲覧記事をAIが分析して、他読者の傾向もふまえてAさんが関心を持ちそうな記事を、個別に関連記事欄やメルマガで薦めてくれる……これは顧客起点でデータを基に個別に最適化するという点でDX的と言えます。
DXの取り組みにはマーケティング視点が必要だと江端氏は語ります。
「従来のように『ITの人』だけが技術面からアプローチするのではなく、市場の消費者に近く、市場を最も理解しているマーケティング部門の人がDXに積極的に関わる必要があります」(江端氏)
マーケターは顧客のデータにアクセスしやすく、市場がどんな課題を抱えているかを分析できます。また、将来のあるべき姿から逆算して今までにない課題解決方法を提供する視点を持ち合わせています。
「デジタル化」と「DX」の大きな違いは「顧客志向」にあります。マーケティング部門の仕事は顧客のニーズを発掘し、その解決するソリューションを提供することです。その解決方法を実践する過程で、デジタル化によって解決できることが増えてきたためマーケティング視点が必要になったのです。
DXには、専門組織とリーダーが必要
「DXはITの領域」とIT部門にとりあえず投げておく、といった形では真のDXは進みません。デジタル化の壁を超え、DXに導くには、DXの取り組みを「組織面」で変える必要があると江端氏は警鐘を鳴らします。
組織面から変えるポイントは2つあります。1つめはDXを推進する部署やチームを作ることです。役割・成果を明確にし、権限を提供することで社内に伝わりやすくなります。2つめはDX専門の組織にリーダーを配置することです。米国の大手企業ではCDO(Chief Digital OfficerまたはChief Data Officer)などを設置していますが、経営目線で取り組むこともDX推進には求められます。
このコロナ禍は「アナログで十分」という壁を突き破った転機となりました。今まで社会では「そういうもの」と割り切って我慢していたこと、我慢はしていないものの「もっと便利になるのではないか」と気づくきっかけとなりました。
「どうやって変えれば良いか」はIT目線で見えてきます。「何を変えれば良いか」を把握するためにマーケット目線に立って利用者や消費者側から考える必要があるのだと江端氏は書籍の中で指摘しています。
本書では、マーケティングの基本のフレームワーク・事例をベースにDX時代におけるマーケティングの視点が書かれており、またワークシートもあるためDXの本質を知識・体験・豊富な事例を通して理解することができます。
マーケターはもちろん、DXを推進していこうと考えている方や経営者、新規事業を立ち上げようと考えてる方には特にお薦めの書籍です。DXがバズワードになりつつある今こそ、本書を通してDXの本質を理解し、今一度自社のあるべき姿を振り返ってみてはいかがでしょうか。