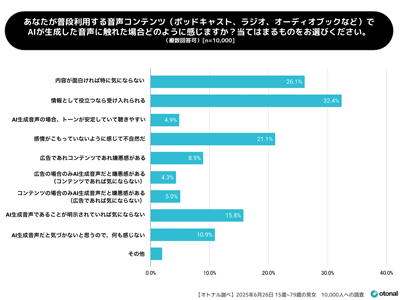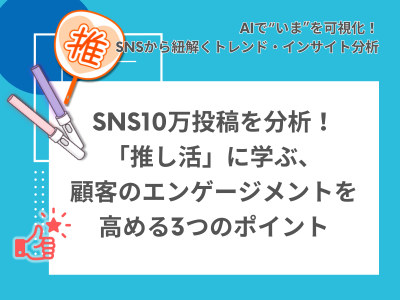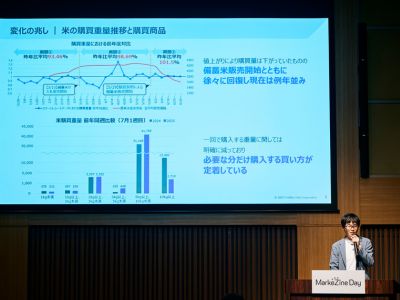変化(2)新たな顧客ニーズの発見
従来の消費が激減する中で、新たな業態にチャレンジする企業もいた。
B社では、お弁当の製造販売やエキナカでのイートイン提供等を行っていたが、人々の勤務形態がテレワークに移行したことにより、法人向けの弁当需要や駅構内での需要が激減した。需要は減ったものの、農家等の生産者には直接の買い付けを行っていたため、新たな販路を開拓する必要があった。新しい販路の開拓は正解のない、長い道のりだったという。
最初に取り組んだのが、個人向けのデリバリーサービスだ。コロナの外出できない状況を狙ったサービスだったが、競合デリバリーサービスも強く、思うように事業は成長しなかった。結局半年以上の期間を経て個人向けの取り組みは撤退を余儀なくされる。
挽回の手として取り組んだのが、法人向けのオンライン飲み会に特化した宅配サービスだ。オンライン飲み会用に食事セットを提供している。こちらも最初は鳴かず飛ばずだったが「リアルの接待・懇親会はなくなったが、接待交際費は使わないといけない」という幹事のリアルな課題にフィット。特定企業内で爆発的に利用されるようになってから、一気に成長軌道に乗った。
元々の弁当作りのノウハウとして、消費期限は長くないもののチルドで届ける仕組みがあったことが成功要因とのことだ。事業の立ち上げにおいては十分な予算もなかったため、BASEやGMOの決済サービスなどの外部サービスを上手く駆使していた点も非常に興味深かった。
今後は宅配サービスのみならず、司会業の派遣や表彰式のセッティングなど付随するサービスでさらなる拡がりも見出せそうとのことで、このトレンドが完全にコロナ禍が終結した後も持続するか注目したいポイントだ。

さらに大きな変化を強いられていたのが酒類を提供している事業者だ。
地ビールを提供しているC社は緊急事態宣言にともない酒類の提供がなくなり、業態変更を余儀なくされた。従来は店舗・イベント・飲食店やホテルへの卸の3つが収益源であったが、コロナによりすべてにおいて発注が止まったという。
現状考えている打ち手は2点。1つはカレーの移動販売である。現在キッチンカーの見積もり中で、金額がまとまり次第クラウドファンディングを行う予定とのことだ。コロナによって商圏が固定されてしまうことがリスクとなり、移動販売へのメリットを感じていた。
もう1つが通販サイトでのビール販売である。商工会の補助金により通販化が可能になり、集客面でもFacebook、Instagram、Twitterを駆使することで集客が徐々に増えてきているとのことだ。
前述のBASEなど気軽にネット通販を開設できるサービスが充実してきており、今まで通販に取り組んでこなかった事業者も、新たな販売チャネルの構築に目を向ける流れができてきている。この領域は様々なビジネスチャンスを生み出しそうである。