ただ売るだけ、はマーケティングではない?
MZ:顧客が価値を見出すから購買が成立する、というのは消費者目線でもわかりやすいです。買ってから「失敗したな」と思うこともありますが、基本的には自分にとって何らかの価値があると感じなければ買わないですよね。
西口:購買という形態でなくとも、たとえば無料のゲームや動画配信サービスに“時間”を費やすことも同じです。多くの場合、その時間内にユーザーに広告を視聴してもらうことで企業は売り上げを確保しているわけです。
顧客と、その顧客が価値を見出すプロダクトが合致して初めて企業に売り上げや利益が生まれ、その積み重ねで継続的な利益が生じます。そこで生まれた利益を、また新しい価値の提案に生かすというのが、先の一連の流れです。
MZ:どうして、このような定義にたどり着いたのですか?
西口:私は「マーケティングとは売ることだ」といった表現に、ずっと違和感がありました。売る仕組みやプロセスは大事ですが、ただ売れば良いのであれば、必要でもないのに「これはあなたにとって必要です、役立ちます」と誤解させて売ることもマーケティングに含まれてしまいます。
価値が“自分ごと”化されているか
MZ:確かにそういう言葉に乗せられて、つい買ってしまうこともあると思います。
西口:売れるようにすることがマーケティングであるならば、極端な例ですが、道端の石ころをさも価値があるように誤解させて売ることもマーケティングになりますよね。
仮に、何らかに使う重しや金槌の代わりになるものを探している人に「この石がちょうど良いですよ」と勧めたら、価値を見出してくれるかもしれません。お金を払ってもらうのは難しいかもしれませんが、感謝はされそうですし、お礼のジュースをもらえるかもしれない。それならば「価値が生じている」といえそうです。
しかし、そのような潜在的なニーズが顧客の側にまったくない状況で、理由をつけて石を売り付けるのは良いこととは思えません。
MZ:売るものや売る部分だけにフォーカスするのではなく、顧客と売るものが合致すること、顧客にとってそのプロダクトが「価値を感じていただけるもの」であることが、マーケティングの最初のステップの前提になるわけですね。
西口:はい。ここで考えるべき重要な観点は、「顧客が価値を“自分ごと”化しているか」です。誰かに強制されるのではなく自分が手にしたいから、所有する価値を能動的に感じているから、購買に至るのが本来のあり方です。
そして価値が成立するかどうかは、顧客とプロダクトの組み合わせによって変わります。自分にとって具体的に欲しい何かを見つけ出す顧客が存在するか、そしてその「何か」を満たすプロダクトを提供できるか、の2点で決まるのです。マーケティングでは、ここから責任を負うべきだというのが私の考えです。


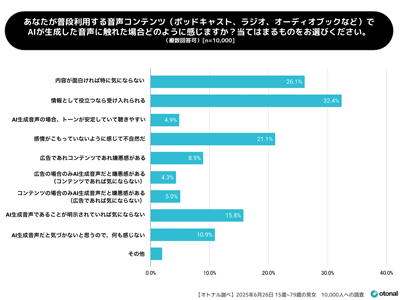














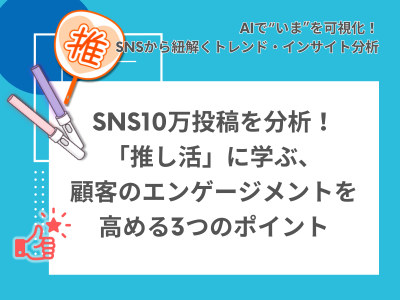




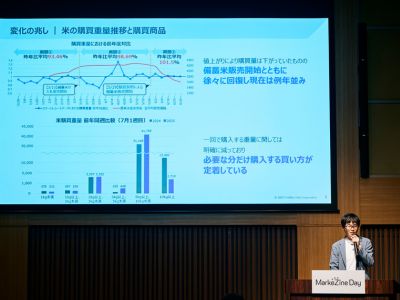











.jpg)
