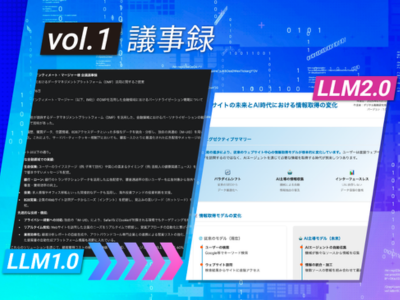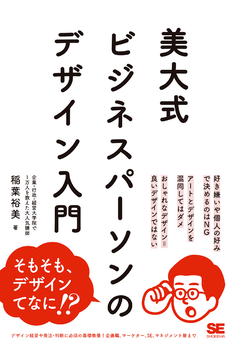本記事は『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』から一部を抜粋したものです。掲載にあたって編集しています。
センスは生まれながらの才能じゃない
仕事に自信満々な人も、センスだけは自信がない
「センスには自信がなくて」
高学歴や大企業勤めで、自信に満ち溢れている社会人も、出世頭でハイパフォーマンスを出すビジネスパーソンも、センスの話になると、とたんに申し訳なさそうな、恥ずかしそうな顔をする。
デザインをお伝えする仕事をしていると、こういった方によく出会います。
なぜ、センスがないというだけで、こんなにも自信を失ってしまうのでしょうか。
そうやって自信を失ってしまう多くの人に共通するのは
「センスって結局才能でしょ」
「センスって生まれつきの天賦の才が関係しているよね」
という考えを持っていることです。
そういった考えを持つ人は、センス=生まれつきの才能だから、それがない自分は、
「生まれながらにして欠陥がある人間だ」
というような認識を、無意識に持ってしまうのです。
他の能力がないと言われた時に比べて、より根本的なことを否定されたような気持ちになってしまう。
そして、まるで、決定的な欠損を抱えた人だと言われているような気さえしてくる。
それが、みなさんが申し訳なさそうな、恥ずかしそうな顔をする大きな理由です。
誰でも今からでもセンスは磨ける
しかし、私がまずお伝えしたいのは、センスは生まれながらの才能ではないということです。これは断言できます。
私は、美術大学で多くの美大生たちと共に学びました。
社会に出てからは、数多くの優秀なクリエイターたちと仕事をしてきました。
そこで気づいたのは、センスがいい人たちは、決して生まれ持った才能で、センスを発揮しているのではない、ということです。
そこには、あきらかに、センスを育む経験と学びがあります。
たとえば、子どもの頃から、美術館によく行っている。
オシャレな服の選び方を、日々の生活の中で、教えてもらう機会があった。
デザインのいい家具を売るお店に、連れて行ってもらったことがある。
家に、美しい絵画が飾ってあった。
茶道や華道を体験したことがある。
DIYでものづくりをすることがよくあった。
いい映画や演劇を観に連れて行ってもらえた。
「センスがいい状態」になるまでには、そのような小さな経験が、幾重にも積み重なっているのです。
そこには、明らかに後天的な学びが存在しています。
つまり、センスがいい人になるために重要なのは、遺伝ではなく、センスを磨く経験や学びがあったかどうか、ということなのです。
センスは生まれながらの才能ではなく、誰でも磨くことができるもの、ということです。
今はセンスに自信がなくても、自分には無理だと諦める必要はありません。
経験と学びを積み重ねれば、センスは誰でも磨くことができるものなのです。
デザインがわかる人になるためのコツ
センスは生まれながらの才能ではなく誰でも磨くことができるもの。
「ヤバい」「すごい」「カワイイ」で終わらせるのはやめなさい
美術館でよく聞く「ヤバい」「すごい」「カワイイ」
「これヤバいね!」
「なんかすごい」
「カワイイ〜」
美術館でこんな会話をよく聞きます。
何かは感じているんだけど、上手く言葉にできない。
だから、簡単な言葉ですませてしまう。
美術館に限らず、いろんなシーンで、こんな言葉ですませている人は、多いかもしれません。
けれど、いつもこういった安易な言葉ばかりでは、デザイン力は伸びません。
日本は色を表す言葉が世界一多い
人間は、言葉と共に世界への認識を深めてきました。
四季の変化が豊かな日本では、色を表す言葉が他の国に比べてとても多い、ということをみなさんはご存知でしょうか?
秋に色づく楓の葉のようなあざやかな赤は「紅葉色」。
萩の花のような紫がかった明るい赤は「萩色」。
春の紅梅の花の色のようなやや青みのある淡い赤は「紅梅色」。
など、赤色にまつわる名称の一部を挙げてみただけでも、深く細やかな世界への認識があることがわかります。
言葉の存在があることで、そこに情緒を感じる心があることが、くっきりと浮かび上がるのです。
他にも、雪が多く降る地域の人は、雪を表す言葉をたくさん知っています。
粉のようにさらさらとした細かい雪は「粉雪」。
ざらめ糖のように粒の粗い積雪は「粗目雪」。
牡丹の花びらのように大きなかたまりとなって降る雪は「牡丹雪」。
雪が降らない地域の人にとっては、ひとくくりに「雪」という名称で認識されてしまうものです。
しかし、言葉があることで、そこに差異があり、それぞれの雪に個別の特徴があることがわかってきます。
雪にも、さまざまな表情があり、情景があることに気づかされるのです。
このように、言葉があることではじめて、それ自体が「存在する」ということがわかるようになる。
語彙と、世界認識は繋がっているのです。
諦めず言葉にしたいと願う
ですから、みなさんにはぜひ、
「もう一歩、具体的な言葉で言い表せないか?」
ということにぜひチャレンジして欲しいのです。
ヤバい、ではなく、たとえば、
「これまで経験したことのない、迫力だったね」
「すごく洗練された美しさだね」
カワイイ、ではなく、たとえば、
「丸みが心地よくて、癒やされるね」
「小さくて、可憐な感じがするね」
というように、もう一歩先まで、言葉にしてみて欲しいのです。
日常で感じた、ちょっとした喜びについてや、旅先での感動についてなど、どんなことでもOKです。
「そんな言葉、すぐに出てくるようにはならないよ」と思うかもしれません。
でも「この感じた気持ちを言葉にしたい」と願い、どういう言葉がフィットするかと、諦めず考え続ければ、その時は思いつかなくても、そのうち何らかの言葉にたどり着くものです。
ふと、音楽の歌詞を聞いた時に、「あ、この言葉はあの時自分が感じた感情だ」と気づいたりする。
友達と話している時に聞いた言葉に「そうか、自分もこう言えばよかったかも」と気づいたりする。
「言えなかったけど、言い表したかったこと」に、こだわる気持ちがあれば、そんな風に、全く別のシーンで、あの時言いたかったけど、出てこなかった言葉に出会うこともあります。
そんなことを繰り返しているうちに、だんだんと使える言葉は増えていくものです。
デザインは、とても解像度の高い、細やかな世界認識に基づいて存在しているものです。
ですから、こんな風に語彙を増やし、世界認識の解像度を上げていくことは、デザインへの解像度を上げていくことに直結します。
「これはどんな感情だろう?」
「これはどんな印象だろう?」
と、日頃から言葉を細やかにし、世界認識を細やかにすることで、デザインの世界観に、一歩、また一歩と確実に近づいていくことができるのです。
デザインがわかる人になるためのコツ
語彙を増やせば、世界への解像度は上がる。
解像度の高さはデザイン力に繋がる。
デザイン判断できるクリエイティブリーダーを目指す
リーダーとしてデザイン判断者になる
最後に、デザインの力を活かすために、ビジネスパーソンのみなさんがどんな役割を担うことができるか?というお話をしたいと思います。
デザインについて聞いてみて、みなさんはどんなことを思ったでしょうか?
「デザインはやはり魅力があってワクワクする」
と感じていただいた方もいるかもしれませんし、
「これを実際に実行するのはなかなか難易度が高いな」
と思った方もいたかもしれません。
しかし、ご安心ください。
当然ですが、これらのデザイン経営の実践を、全て一人で実行する必要はないのです。
デザイン経営は、デザイナーと、それを判断するリーダーの二者が、二人三脚で進めていけば良いのです。
つまり、自分自身が発想したり、実際にアウトプットをつくったりするデザイナーになるのではなく、それらの技術力・発想力をすでに持ったデザイナーとチームを組めば良いということです。
つまり、ビジネスリーダーは、デザインを判断できるレベルの基礎力を身につければ良いということです。
「デザイン判断力」とは何か?
私が、ビジネスパーソンのみなさんに、目指すべき役割として提案したいのは、この二人三脚を進めるための「デザイン判断できるクリエイティブリーダーになる」ことです。
それは、どのような能力を持っている人のことでしょうか?
クリエイティブリーダーに身につけて欲しい能力は、大きくこの3つです。
- どこでデザインを使うかを決める力
- デザイナーに相談し、議論しながらアウトプットを判断する力
- 適切なデザイナーを選ぶ力
まず一つ目の、「どこでデザインを使うかを決める力」。
デザインには「視覚から情報を伝える」「感性的価値をつくる」「人間中心で考える」という、大きく3つの役割があります。
それぞれの現場に合わせて、経営のどのフェーズで、デザインを使うかを検討してみてください。
もちろん、どこでデザインを使うかを決めるところから、経営の視座で相談にのってくれるデザイナーもいますので、そういったデザイナーに相談するのも良いでしょう。
次に、二つ目の、「デザイナーに相談し、議論しながらアウトプットを判断する力」。
これは、デザイナー以外の専門的なメンバーとの付き合い方と、基本的に同じだと考えていただければいいと思います。
ビジネスを実行するチームには通常、企画、製造、マーケティング、営業など、それぞれ専門性を持ったメンバーがいます。
優れたビジネスリーダーは、そういったチームを率いるために、専門性を持つセールスパーソンやマーケターに相談したり、対等に議論したり、そのアウトプットを判断したりすることができるでしょう。
また、そのために必要となる各分野の基礎知識をもっているはずです。
デザイナーとも、同様の関わり方ができるようになればよいということです。
本を読んだり、講座に参加したりして、デザインについても基礎知識を学んでみましょう。本書での学びもその一つとなるでしょう。
基礎知識を得ることで、デザイナーに相談し、議論しながらアウトプットを判断するということも、徐々にできるようになってくるはずです。
そして、三つ目の、「適切なデザイナーを選ぶ力」。
これは、二つ目とおおよそ同じです。
ビジネスをチームで実行するには「誰を採用するか?」が非常に重要です。
プロジェクトに合った優秀なメンバーを選ぶ力が必要です。
デザインにおいても、それができるようになろうということです。
そのためには、まず採用する側が仕事の内容を理解し、どんな人物ならばその仕事をこなせるのかをわかる必要があります。
また、その人物がどのレベルで仕事ができるのか、どんなタイプの仕事が得意なのかを判断する必要もあるでしょう。
そういった判断をするためには、やはりその分野の基礎知識を持っておくことが重要です。
基礎知識を得ることで、良し悪しの基準を身につけましょう。
判断者は希少人材
実は、こういった判断力ある人材は、ビジネスシーンで多数必要であるにもかかわらず、実際にはほとんどいません。
つまり、多く席がある上に、希少価値人材となれる、とても魅力的なポジションだということです。
このポジションには、あらゆる企業で、かなり多くの椅子があります。
たとえば、ウェブサイトやパッケージ、名刺、冊子などのデザイン判断をしなければならない責任者。
デザイナーと協業しながら、ものづくりやサービスづくりをする企画・開発者。
デザイン人材を採用したり、デザイン研修を企画したりしなければならない人事担当者。
戦略やビジョンを打ち出していかなければならないマネジメント層、経営者。
他にも、さまざまなポジションでデザイン判断力は必要です。
それにもかかわらず、この役割を高いレベルでこなせる人は、ほとんどの企業で存在しません。
実質的には、空席になっています。
つまり、ほとんどの企業で、実際にはデザイン判断力が必要なはずのポジションに、現在は判断力がない人が座っているということです。
そのため、多くの企業で、デザイナーとデザイン判断者の二者で回すはずの両輪の片側が欠け、上手く駆動できない状態になっています。
デザインの価値がわからない。
デザインをどこでどう使えばよいかわからない。
デザイナーを起用したいが、どのデザイナーが良いかわからない。
デザイナーと共通言語をもって議論できない。
デザインの良し悪しを判断できない。
そのような状況は、あらゆる企業で課題となっています。
これでは、良いデザイン経営ができるはずがありません。
優れたデザインを組織で実行していくには、デザインを判断できるクリエイティブリーダーの存在が必要不可欠なのです。
このポジションを目指すことは、みなさんのキャリアにとっても、大きなプラスとなるはずです。
スティーブ・ジョブズも優秀な「デザイン判断者」だった
アップルの創業者である、スティーブ・ジョブズも、優れたデザイン判断者の一人でした。
彼の場合は、ビジョンを自らデザインしているという点では、デザイナーでもあります。
一方で、ジョブズは、製品づくりについてはデザイナーを選び、任せ、判断していました。
プロジェクトの方針に合った、最適なデザイナーであるジョナサン・アイブを選ぶ。
アイブに相談しながら、対等に議論し、任せる。
アイブが出すアイデアの良し悪しを判断する。
まさに、優れたクリエイティブリーダーとして機能していたのです。
このようなジョブズのデザイン判断力が、アップルの成功に大きく寄与していたことは間違いありません。
デザインには力があります。
しかし、それはリーダーが活かしてこそ発揮されるものです。
あなたもぜひ、ジョブズのような「デザイン判断できるクリエイティブリーダー」を目指してください。
デザインがわかる人になるためのコツ
デザイン判断できるクリエイティブリーダーがいれば企業のデザイン実践は大きく変わる。