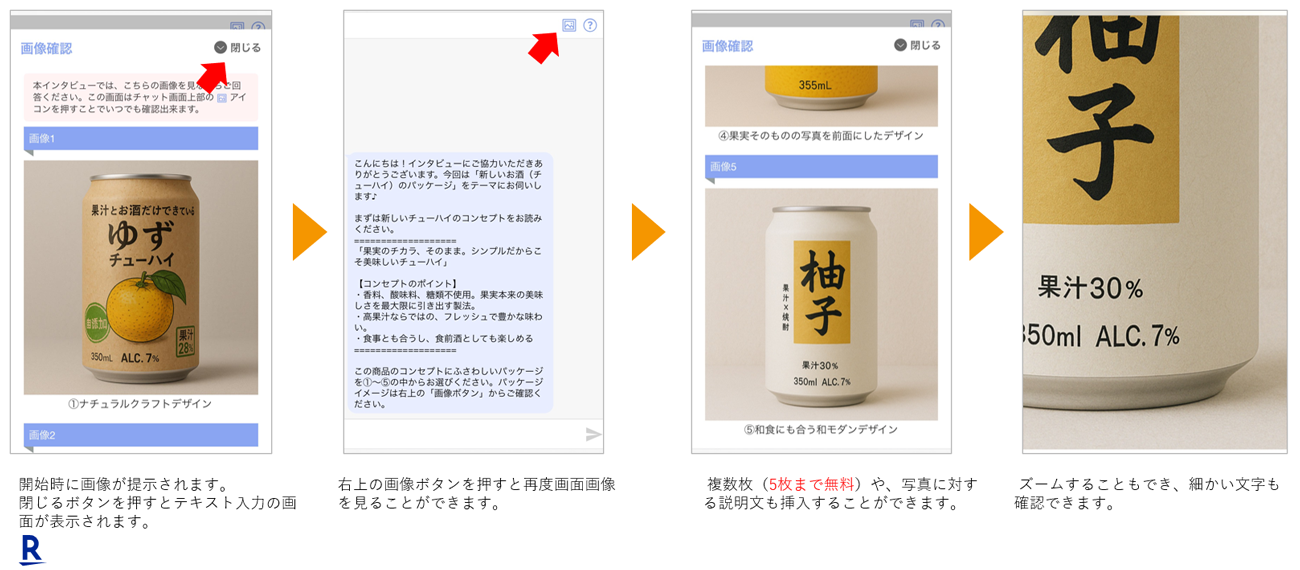「質×量」を両立、リードタイムも2ヵ月から5日に短縮
MarkeZine:では、改めて、AIチャットインタビューの基本的な機能を教えてください。
伊藤:AIチャットインタビューは、従来の定性調査では難しかった「多数の意見収集」と「インサイトの獲得」の両立を実現するソリューションです。通常のインタビュー調査だと数時間かけても話を聞けるのは10人前後ですが、AIがモデレーターを務めることで、一度に多くの調査対象者へチャットインタビューを実施することができます。50~数百人規模の深掘りされた定性データをスピーディーに収集することができるわけです。
また、時間の制限も大きく改善されます。従来の定性調査では1.5〜2ヵ月要していたリードタイムが、最短5営業日まで短縮されるので、マーケティングアクションの大幅なスピードアップに繋がります。
MarkeZine:1.5~2ヵ月が最短5日になるというのは、かなり大きな違いですね。
鈴木:加えて、マーケティングの工数やコスト削減にも寄与します。もちろん、マーケターがインタビューに立ち会う時間を持てるのが理想ですが、現実的にはなかなか難しいことも多いでしょう。その点、AIチャットインタビューでは、マーケターをその場に拘束することがありませんし、インタビュー結果の納品時にAIが解析・要約したサマリーも提供させていただくので重要な部分をクイックに把握できます。マーケターの工数削減という点でもお役に立てるのではないかと考えます。
CEPの抽出でも有用、定性的な意見を定量的に把握できる
MarkeZine: AIチャットインタビューは、どのような使い方が想定されますか?
伊藤:AIチャットインタビューの使い方としては、大きく次の3つがあります。
1つ目はこれまでの定性調査の代替的な用途です。費用やスケジュール面で、本当は定性調査を行いたいが、時間・費用・スケジュールの制約があり実施が難しいといった場合に活用いただけます。
2つ目は、定量調査や定性調査の補完的な使用です。定量調査を行う前の仮説整理として、たとえばAIチャットインタビューで生活者の価値観や意識を把握し、それを選択肢に反映するといった使い方があります。また、定量調査の実施後に、もう少し深掘りしたい部分について追加で調査するパターンもあるでしょう。
3つ目が最近増えている使用方法で、定性的な意見を定量的に収集することを目的にしたケースです。たとえば、消費者が商品やサービスの購入を考える際に、特定のブランドを思い出す「きっかけ」となる状況や目的であるカテゴリーエントリーポイント(CEP)を抽出するための調査では、消費者がブランドを想起するきっかけとなる「状況」を明らかにする必要があります。
このように実態を把握しづらいテーマは調査が難しく、定量調査にしてしまうと選択肢に影響された結果が出てしまいます。とはいえ、定性調査は量的な問題で網羅性が担保できません。AIチャットインタビューなら、そうした抽象度の高いテーマについても、数百人の定性情報を取得した後、量的に変換して分析することが可能です。
鈴木:CEP抽出の調査については、どのような場面・状態で、どのようなニーズが発露するのかを辿っていくような形で、AIチャットインタビューを実施されるケースが多いですね。具体的な出来事を体験した際のエピソード記憶も含めた回答データを多数回収できるため、多くの企業様に満足いただいています。