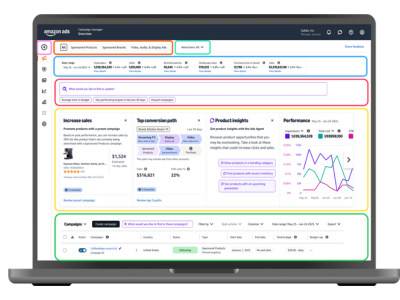CMOから経営者へ、視座はどう変わったか
木村:このセッションでは、Uber Eats Japan代表の中川さん、ポーラ代表の小林さんから、ブランディングおよびマーケティングについて考え方や視座を学んでいければと思います。
お二人はCMOというポジションからCEOになられたわけですが、その過程でマーケティングに対する向き合い方に何か変化がありましたか? まずはそこからお聞きできればと思います。

ユニリーバに2009年に入社。約12年間、ラックスやダヴなどのブランドマーケティングを経験。国内を中心とした360°のプロモーションから、グローバルのブランド戦略や製品開発まで、幅広く従事。ロンドン本社にてダヴを担当し、グローバル全体のブランド戦略設計をリードした後、2020年1月より、ユニリーバ・ジャパンにおけるスキンクレンジングカテゴリーならびにダヴブランドを統括。2021年7月より同ユニリーバ・グループのプレミアムのスキンケアを扱うラフラ・ジャパン株式会社の代表取締役に就任。また、2021年より株式会社Brandismを創業し、ToBからToCまで、幅広くマーケティングのサポートを行なっている。
ブランディングの対象は「消費者」よりもっと広い
中川:マーケティングという専門職に対する向き合い方は、特に変わっていません。私は「マーケティング=対象者の知覚管理をすること」と考えており、そうした本質的な部分の考え方はずっと一貫しています。
カントリーマネージャーや日本代表という立場になって変わったのは、やはり実務面が大きく、具体的には仕事の領域が変わりました。その時々で会社に一番必要な領域に入っていくので、極端に言えば、毎日やっている仕事が違います。そうしてより広い領域を見るようになり、ブランディングやマーケティングが影響を与える対象は必ずしも消費者だけではない、ということを強く実感するようになりました。

P&Gでブランドマネジメント担当としてキャリアをスタートさせた後、事業再生支援会社を経て、2009年にユニリーバ・ジャパンに入社。ヘアケア商品のマーケティング責任者を経て、2016年からは同社ホーム&パーソナルケア部門のディレクターとしてマーケティングを統括。2021年1月の Uber 入社後、モビリティとデリバリーの両事業におけるマーケティング活動を統括し、2022年9月にUber Eats Japanの暫定代表に就任。日本におけるUber Eatsの事業責任者として、Uber Eats プラットフォームの運営全体を統括。2023年2月に Uber Eats Japan 合同会社のゼネラルマネジャーに正式に就任。
たとえば、弊社のビジネスはまだ社会で新しいサービスであり働き方であるため、国の法律やルールの整備から必要になります。ですので、時には政治家の方々と話すこともあります。私が代表に就任した最初の頃、ブランドエクイティが良くない方向に行った時期があり、そうした議論の場で厳しいお言葉をいただくこともありました。しかし、近年はブランディングの効果もあり、「この間Uber Eatsを使ったよ」という会話からスタートできたりします。
一般的にブランディングというと、エンドユーザーの消費者を想定した文脈で語られることが多いですが、ユーザーだけでなくそれ以外の大多数、“パブリック”に対して与える影響も実は非常に大きいんですよね。
経営戦略は、マーケティング戦略そのものである
小林:私は新卒でポーラに入社し、7年くらい経った時に社内ベンチャーで敏感肌向けのスキンケアブランド「ディセンシア」を立ち上げ、約8年このブランドの経営をしていました。キャリアとしては少し特殊で、いわゆる部課長やCMOなどを経験せず、係長レベルしか経験がない状態で“経営者”になった形です。
長年BtoCの化粧品ブランドの経営をしてきて思うのは、BtoCビジネスでは経営戦略そのものがマーケティング戦略に非常に近しいということ。実際、ディセンシアでは経営者でありながら、実質的にはCMOの役割も果たしてきました。ブランド存続のために、経営戦略としてのマーケティングが必須だった――ブランドが生き延びるためにそうしていくしかなかったとも言えます。

2002年に株式会社ポーラへ入社。2010年にポーラ・オルビスグループの社内ベンチャーで起ち上げた敏感肌専門ブランド株式会社DECENCIA(ディセンシア)社長に就任。同ブランドを飛躍的に成長させた後、2017年にオルビス株式会社 マーケティング担当取締役、2018年社長に就任。リブランディング、構造改革を実行し再成長に導きV字回復を実現。2025年、株式会社ポーラ 代表取締役社長に就任。ポーラ・オルビスホールディングス取締役を兼務。早稲田大学大学院MBA(経営学修士)。
木村:小林さんはその後、ポーラ・オルビスホールディングスの基幹ブランド「オルビス」の代表としてV字回復をリードされました。この時も経営者としてのマーケティングへの向き合い方は同様でしたか?
小林:そうですね。オルビスのようなダイレクトの商売で大きくなった会社は、コロナのダメージが非常に大きく、当時はターンアラウンド(事業再生)が必要不可欠でした。その場合、経営戦略≒マーケティング戦略にトップがコミットしないと構造改革が進みません。ですので、オルビスでもブランド代表とCMOを兼任するような形を採っていました。
なお、私はオルビスでも、現在代表を務めているポーラでも「マーケティング部」という組織をすべてなくし、「CRM」「新規獲得」といった役割別の組織に再編しています。というのも、社内で「それはマーケがやっていることですから」という会話を耳にすることがあり、よくよく聞いてみると「広告を担当する部署=マーケティング」という認識になっていたようでした。
しかし、私の中では顧客価値創出のプロセス全般がマーケティングであり、それをマーケティング部門のやることとするのは危険です。少し極端かもしれませんが、全社マーケティングを実現するためにも、マーケティングの部署は置いていません。